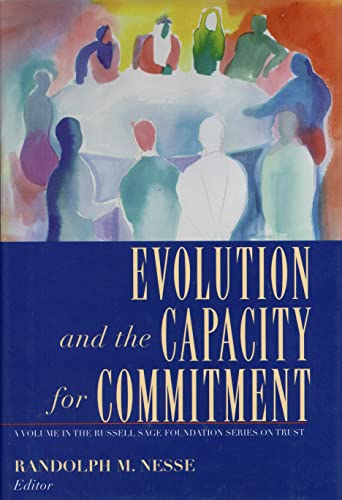- 作者: 倉谷滋
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 2019/03/13
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
本書は進化発生学(エヴォデヴォ)の日本の第一人者である倉谷滋による新書.倉谷は最近「分節幻想」と「新版動物形態進化学」という大著を2冊書いているが*1,本書はこの2冊を執筆しながら,書き切れなかったテーマに絞った一冊ということになるのだろう.そのテーマは「生物の形が変わるとはどういうことか」という進化発生学の最も深い疑問になる.
倉谷の解説は冒頭「はじめに」のところから深い.発生学は「卵がいかにして成体になるのか」を扱う学問だが,還元主義的にのみ突き詰めてもシステム全体は見えてこない.パターン把握を行う構造主義の視点も重要になる.進化学以前の観念形態学においては構造主義的に「基本形」を追い求めたが,進化という足場を持たないまま動物形態のパターンをいたずらに抽象化し続け,ついに科学になり損ねた.分子遺伝学は還元主義に傾き,比較発生学は構造主義を用いたが「反復」にこだわってしまった.本書ではこの「反復」が必要以上に理想化されたモデルであったことを示し,それをいかに越えていくかを扱うことになる.そしてそれを越えるには還元主義と構造主義を併用するだけでは足りない.進化と発生の実装には複雑系と同じ問題が隠れているというのだ.
この難解な導入でついて来られない読者をふるい落とし,そして重厚な倉谷節が始まる.
第1章 原型論的形態学の限界
倉谷はまず様々な形態の動物群があることを示し,しかしそこにはデザインの制約があることを示す.倉谷はこれを「多様性と共通性は表裏一体なのだ」と説明している.そして単純な適応論では体の基本パターンを説明できないと主張する.例えば「我々の体が大まかに左右対称なのは左右対称遺伝子が適応的で集団に固定したからだ」という説明はできないのだ.
ポイントとなるのは発生過程が最後までちゃんと進行するかという問題になる.これによる淘汰は「内部淘汰」と呼ばれる.またマスターコントロール遺伝子,ツールキット遺伝子群のように重要な遺伝子はどのように現れたのかという問題もある.ここには「発生プログラム自体も進化する」という視点が欠かせない.そしてこの視点を持ち,動物の体の多様化について進化的な分岐の際に体を作るメカニズムがどのように変化したのか,その発生の方法とゲノムを調べる分野が進化発生学(エヴォデヴォ)になる.(ここで脊椎動物の胞胚→原腸胚→神経胚→咽頭胚と進む例が示されている)原型論や構造主義では構造そのものの成立や起源を問うことができなかった.進化的多様性の中に保守性があり,胚発生に種を越えたパターンがあるなら,そこには何らかの安定化過程により拘束された状態があるかもしれないと考察すべきなのだ.
ここから倉谷はこれまでの歴史を振り返りながら原型論の限界を示していく.キュビエに始まる比較解剖学者は(1)どの動物もある種の「型」にはまっておりそこから逸脱しない(2)動物の体の部品は常に特定の「型」に属している,ということに気づいた.前者はボディプランと呼ばれ,観念的形態学の「原型」と深く関わっている.後者は「相同性」に関わっている.
倉谷はまず「原型」を取り上げる.ダーウィン以前の形態学者は,原型からどのように変形するのかという視点で動物の体を考察した.ダーウィン以降,原型はイデアとしての地位を失ったが,進化的多様性の中にある拘束された変化パターンとして理解されるようになった.ハクスレーはある動物グループのすべての派生的な特徴を徹底的に排除したらどのようなパターンが残るかを考えた.それは共通祖先の特徴を表すことになるだろう.原型はそういう進化的意味合いを(不完全に)背負うことになった.つまり「原型」には「原初の姿」と「安定化の果てに成立した共通性」という2つの側面を持つことになる.(ここからはこの2つの側面とゲーテ,オーウェン,ジョフロアたちの原型の考え方が解説されている)
第2章 形態学的相同性
第2章は「相同」を扱う.倉谷はいきなり「相同」「相似」は文脈に依存した概念だと始める.
現代の生物学では相同は進化の結果として表れる.ではそれは単に系統内の共有派生形質なのか.倉谷はそれほど単純ではないといい,鱗翅目昆虫の幼虫腹部の疣脚の例をあげる.これはその他節足動物の歩脚と相同なのか.鱗翅目を含めた完全変態昆虫の共通祖先はかつて腹部の付属肢をすべて失ったことがあるので,これは共有派生形質とは言えない,しかし発生的には相同的な分子機構によって形成される.進化形態的には相同でなくとも遺伝子レベルの発生プログラムとしては相同なのだ.これは「深層の相同性」と呼ばれる.
ここで倉谷はダーウィン以前に提唱された「相同」概念自体に立ち戻る.ジョフロアは「異なった動物における互いに同等の器官は体の中で同等の位置を占めて互いに同等な隣の器官と結合している」ことに注目した.これは「形態学的相同性」と呼ばれる.オーウェンはこれをより突き詰めて相同概念を提唱した.これは構造主義的に器官のネットワークを見ているのであり,原型という構造はある特定のパターンで配置された形態的相同性の集合ということになる.このようなとらえ方では,原型とされるボディプランがネットワークを保ったまま変形して多様性が生まれることになる.だから異なるボディプランの説明はできない.
そして進化概念が認められて,相同性は「共通祖先から受け継いだ何らかの同一性」あるいは「半ば拘束された状態」だと考えられるようになった.この「拘束」は進化的な変化の方向にかかるバイアスということになる.そして拘束への考察は,考察者を発生プロセスに注目させるようになる.
第3章 分類体系をなぞる胚
第3章は発生過程を扱う.倉谷は発生過程の性質について「メリハリの利いた段階的構造を備えた因果連鎖」であり,それは時にどちらを採ってもよい代替経路を持つと説明している.発生プロセスは連続した均一のものではないし,単純な連鎖でもない.胚自体もモジュールと呼ばれる他の部分から独立に変化できる原基のセットを形成する.倉谷は,発生機構の構造はモジュールから成り,このモジュールが進化的淘汰の標的になり,進化の様式やパターンを決めていくのだろうと指摘する.
ここでまた話はダーウィン以前に戻る.後成説を唱えたヴォルフと動物の相容れない4つの「型」を提唱したキュビエに影響を受けたベーアは,発生過程を観察して,その途中に「原型」が一時的に胚の形として表出すると考えた(ベーアはこれを「主型」と呼んでいる).ベーアは,脊椎動物の胚が「主型」を見せるのは器官形成期である「咽頭胚」の時期であり,発生初期と発生後期では動物胚の形は分類群ごとに異なるというのちに「砂時計モデル」と呼ばれる考え方を提唱した.これは10年後のオーウェンの「原動物」概念にも影響を与えた.
実際に器官形成期には多くの動物で共通した形態形成遺伝子群が発現し,極性や位置価を与える.極性や位置価は空間上の位置関係を示し,発生学的機構が発動するための要となる.これは進化的淘汰を通じて守られるべき重要な表現型になる.(ここでそれをよく示すホックス遺伝子群の解説が置かれている)1994年にドゥブールはホックス遺伝子群の発現が最も明瞭になるのは咽頭胚期でありベーアのいう「主型」の成立段階に一致することを指摘し,「主型」を「ファイロタイプ」,その発生段階を「ファイロティピック段階」と呼んだ.これが進化発生学の幕開けとなる.発生学的機構論が進化的解釈のための整合的な論理を初めて与えたからだ.
ホックス遺伝子群はよく調べられ,動物群によって様々なルール,つまり発生拘束がかかっていること,しかし脊椎動物全体に共通する拘束も存在することがわかってきた.形態学的相同性が遺伝子の相同性とリンクしている実例も示された.
では何故,このファイロティピック段階という保守的な発生段階が存在するのだろうか.1つの仮説はそれは強い内部淘汰のためだというものだ.発生初期ではまだ胚がモジュール化しておらず,働いている作用も大局的で,ネットワークとして単純なので変形はある程度可能だ.後期には胚の各部が高度にモジュール化されているので多数のネットワークが独立して機能しており,一部の変更方にあまり影響を与えない.しかしファイロティピック段階では大局的なネットワークが複数あって相互に関連しているので,発生プログラムのわずかな変更が胚の死につながりやすいと考えるのだ.
この仮説を調べるためにファイロティピック段階に機能する遺伝子レパートリーの保守性を調べる研究が行われている.一部肯定的な結果も報告されているが,確実なところはまだわかっていないということらしい.
第4章 進化をくりかえす胚
第4章では第3章で示した発生過程の背後のロジックが考察される.ここまでの説明で胚のファイロティピック段階においてホックス遺伝子群が最も明瞭に発現し,胚形態はボディプランを構成する基本形態パターンが目に見えるようになっていることがわかった.観念形態学の基本理念と分子遺伝学的発生機構がつながっているように見える.では何故そうなっているのだろうか.
ベーアの指摘は「基本形ができた上で,その上に個別的・独自的な特徴が加わる」というものだ.しかし(例えばヘビの脚のように)いずれなくなる特徴でも一度発現させるのはなぜなのか.これは「発生拘束」と捉えるべきで,この中身を知ることが進化の方向性の理解につながると考えられる.「分節繰返し性」「(繰り返し要素のそれぞれが独自に変化する)変形」のような古典的形態学の基本概念は内部淘汰がもたらしたと考えることになる.「原型」も原初のパターンではなく二次的に成立し固まったシステムということになる.こう考えると発生の時間と進化の時間も同じではなくなる(反復説の基本的な誤りはここにある).
ここで倉谷はホックスコードと形態学の概念構築の関係の深さを具体例をもって解説する.「同型」「同名」「同称」などの「形態的同一性の概念群」(相同性の様々なタイプ)は「発生プログラムの使い回し」がヒトの形態パターン認知に形式化されたもので,背景にはある種の分子的な機能モジュールがあるとみることができる.「不完全相同性」はモジュール自体もまた随時細分化・複雑化する現実を示すものだ.
ここから倉谷はベーアの法則とヘッケルの反復説に入り込む.ベーアの法則は「発生において形態的特徴の出現する序列は分類体系の階層的系列をなぞる」というもので分類学的な入れ子関係が発生過程において出現する順序とパラレルであると主張する.これはヘッケルの反復説と同じようにも見えるが,ベーア自体は進化(そして当時の自然の階梯的な一直線に進む進化観に基づく反復説的考え)を否定しており,多様性の階層的分布パターンを捉え,キュビエ的ボディプランの重要性を指摘していたつもりだった.そしてヘッケルはダーウィン以降に系統進化と比較発生学と統合し,入れ子式の分類体系を系統進化過程に読み替え,19世紀の新しい反復説を提唱したという経緯になる.系統進化を認めるかどうかだけでなく,原型の重要性についての認識がこの両者では異なっている(ヘッケルにとってはファイロティピック段階は動物門の成立時期の相当する一里塚という相対的な重要性しかなかった).
この相対的重要性の話を置いてから,倉谷はファイロティピック段階以降の発生過程の保守性に話を進める.ファイロティピック段階の保守性については先ほどの説明があるが,その後についてはなかなかうまく説明できていない.これを説明する試みが「発生負荷」の概念になる.例えばなぜ脊索は脊椎動物の発生においていつまでも残っているのだろうか.それは「脊索が発生を進めるための重要な機能を持つから」と考えられる.脊索はのちの発生過程に「責任を負っている」と考える.この責任を「発生負荷」と呼ぶ(これは発生拘束の要因の1つとなる).発生負荷があると結果的に反復パターンが現れることも説明できる.
ここで倉谷は発生過程が目的論的になりやすいことにも言及している.小さなステップを踏み台にして複雑な発生プログラムが組み上げられているとヒトはそこに目的を見てしまう.また一旦成立した発生プロセスは常に保存を強いられるのかということも問題になる.しかし無尾ホヤでは生涯にわたって脊索の出番がない.これは後期形態形成上の脊索の役割が小さい(発生負荷が小さい)と取り外しが可能であることの例になる.すべての発生原基や発生パターンが保存されなければならないわけでもないのだ.つまり発生過程も進化し,その進化は階層的で,明瞭に変更しやすい部分(発生負荷が大きい部分)としにくい部分(発生負荷が小さい部分)があることになる.そして原型や相同性の認識の源泉はこの発生拘束にあるのだろう.すると原型は類縁性の近い動物の比較を行う際にたまたま便利であるに過ぎなく,現象の正しい理解の方便でさえもないことになる.それは構造主義と同じ限界を持つことになる.
第5章 反復を越えて
では正しい進化的な発生の理解を行うにはどうすればいいのか.倉谷は反復説の例外現象である「ヘテロクロニー」(系統進化と発生過程の順序が食い違うこと)を取り上げる.ヘテロクロニーには部分ヘテロクロニーと全体ヘテロクロニーがあり,前者には有袋類で前脚の形成が前にシフトするような現象,後者にはいわゆるネオテニーがある.これについてゼヴェルツォッフ*2は1930年代に「アルシャラクシス理論」を提唱した.これは以下のような理論になる.
- 進化の過程で祖先の発生タイムテーブルが変化し,それによって新しい形態を持つ子孫ができる方法には3つある
- アナボリー:祖先の発生過程の終末に新しい形質が付加されるもの(ヘッケル的反復と同じ)
- アビーレン:発生過程の中期に変更が生じ,全く異なった発生経路が成立し反復効果がキャンセルされるもの
- アルシャラクシス:発生の初期から変化が生じ抜本的な形態進化が生じるもの
これによるとボディプラン進化にはアルシャラクシスつまり発生のタイムテーブル全体の大規模な書き換えが必要ということになる*3.そして発生の経路が変わる際の発生段階により,異なったタイプの拘束の変化が生じると考える.倉谷はこの「系統分岐する発生拘束」という考え方がボディプランの系統進化を解き明かす鍵だと指摘する.こう考えるとオーウェンのように「すべての動物の器官に相同性が確認できるはずだ」として複雑怪奇な原動物を想定する必要もなくなり,相同性は1つの保守性でしかないことが説明できるのだ.そしてボディプランの進化機構を複雑な発生ネットワークの組換えや,それを可能にするゲノム変化として理解しようと進む事になる.(倉谷はここで「原型」の問題点を脊椎動物の顎の例を引いて詳細に論じている.)
第6章 進化するボディプラン:アロモルフォーゼ
倉谷はボディプラン進化(ドイツ発生学的にはアロモルフォーゼと呼ぶ)がどういう過程であったのかという現代進化発生学の大きな課題に進む.ボディプランの進化については,原型と反復では対応できない.祖先型に同等の構造のない(相同性の喪失を伴う)進化的新奇形質の獲得,従来の発生拘束のキャンセルと新しいパターンの創成という不連続イベントが必要になる.
そしてゼヴェルツォッフは(現生動物A,Bにおいて)発生過程をA→Bではなく,(共通祖先をDとし)そこにアルシャラクシスをおき,D→A,D→Bとして,考察しようとした.
また遺伝子発現レベルの分析によりファイロティピック段階はいくつかの脊椎動物種において遺伝子発現レベルで実在することが確かめられつつある(入江直樹による一連の研究が紹介されている).しかしより広い脊椎動物全般ではまだ吟味がなく,脊索動物まで広げると共有されていないようだ.これはあるグループにのみ特異的な共通パターンが存在することを示しており,ゼヴェルツォッフ的な進化的考察と整合的になる.
ここで倉谷はその典型的な反ヘッケル的な現象の例として脊椎動物における椎式の進化を細かく論じている.これによりわかるのはホックスコードの成立過程が進化を反復しておらず,アルシャラクシス的にのみ解釈可能になるということだ.
片方でアルシャラクシス的過程とヘッケル反復的な過程が外側からは区別しにくい場合もある.倉谷はトコロフォア幼生から様々な環形動物や軟体動物が発生していく過程がどちらの見方からも解釈できる例をあげて説明している.しかしこの場合も全く異なるボディプランの中に形態的相同性を遺伝子発現プログラムとして保持されているなら(そしてそれはいま次々と発見されている),それはボディプラン進化がアルシャラクシスを経ていることを示唆していると考えることができる.
本章ではボディプラン進化はヘッケル反復的と解釈するよりアルシャラクシス的と解釈する方が観察と整合的であることが論じられた.そして最終章でそれが本当に可能なのかが扱われる.
終章 試論と展望
倉谷はここでもう一度古典的な「反復」と「原型」の理論の限界を整理する.この枠組みではすべての発生現象を説明できないし,相同性と原型はトートロジカルにならざるを得ず,異なるボディプランを持つ動物間の比較が不可能になる.形態パターンと分類学にのみ凝り固まった考えでは進化において本当に保存されているものを見逃してしまい,相同性の概念をよりダイナミックに拡張するべきであることに気づけないのだ.
倉谷はまず「相同性」から考察する.異なるボディプランを持つ動物に共通した細胞型のレパートリーや(ホックス遺伝子群を含む)発生制御のツールキット遺伝子群が見つかっている.これは相同性の概念を揺るがすものだ.古典的にはある器官や構造の相同性を認めるには(原型を含む)それより上位のレベルの相同性に依存しなければならないと考えてきた.
しかし実際の動物ではボディプランのレベルと細胞型のレベルで保守性が乖離している.全体の設計と部品の作成では異なるレベル・ロジックで保守性が現れる.つまりボディプランと部品の相同性は異なるレベルの現象だと考えるべきことになる.これは進化では使い回せるのは使い回すからだろう.そうであれば様々な左右相称動物群が皆トコロフォア幼生のような単純な形態から進化する必要はない.そして実際に左右相称動物の共通祖先はある程度大きな解剖学的複雑性を持った動物であったのではないかというシナリオ(アルシャラクシスをおこして,ボディプランを大きく変えながら,個々の部品の遺伝子発現については使い回した)をサポートするデータが集まりつつある.
次に倉谷は細胞型の保守性がどのように維持されるかを考察する.様々な動物の細胞型の遺伝子を分析すれば,細胞型の系統樹を書くことができるだろう.これは動物種の系統樹より遙かに複雑なものになるだろう.これは細胞系譜の系統樹と一致するだろうか.大まかには胚葉説が示すように一致する.しかしこれは必然,そして形態的相同性の根拠となるものではなく,むしろ遺伝子発現を安定化させるための発生拘束により結果的にそうなっていると考えるべきだ.実際に胚葉成立後も細胞型決定過程では発生経路の組換えや遺伝子制御ネットワークのリワイヤリングが生じる.
ここで倉谷はボディプランの相同性がないが下部構造の中に相同性が見いだせるような別の例を考察する.これにあたると思われる現象にはコ・オプションと発生システム浮動(相同な形質の下部構造が進化的に変化するもの)がある.
コ・オプションとは発生プログラムが新しい場所に移植されそれまでに存在しなかったパターンをいきなり獲得するという現象を指す.これは進化においては頻繁に生じており,昆虫の角や脊椎動物の手足も最初はそうやって獲得されたと考えられている.昆虫の角の発現は歩脚の遺伝子発現の使い回しによる.コ・オプションは発生モジュールの上位の位置するマスター・コントロール遺伝子の異所的発現がキーになっていると予想される.角と歩脚は通常の意味で相同ではないが,深層的には相同なのだ.そして(個々の遺伝子にも遺伝子モジュールにも染色体にも相同がありうるのだから)そもそもこの深層の相同性こそが相同性本来のあり方であり,その後マスター・コントロール遺伝子群がボディプラン進化の過程においてツールキット化され,観念形態学的秩序構造の認識に結びついたのだ.そしてボディプランの保守性を考えるためには発生拘束の考察が重要だということになる.
そして倉谷は異なるボディプランを持つ動物間で共通の遺伝子発現プロファイルで定義される細胞型が得られることはアルシャラクシスで生じたのか(真の相同性),コ・オプションで生じたのか(深層の相同性)を区別できるかと問いかける.倉谷はアルシャラクシスであるためには祖先動物の比較的初期の発生過程で同じ遺伝子群が別のいかなる場面においても用いられていないことが確かめられなければならないと主張し,脊椎動物と節足動物の背腹反転と分節の起源の問題を取り上げる.現在では左右相称動物は元々節足動物が他の背腹パターンを持っており,それが後口動物の祖先に引き継がれたが,脊索動物の分岐に伴って背腹反転したと考えられるようになって来ているが,初期の議論ではこれはコ・オプションであるという異論もあった.しかし背腹軸決定以前にこの遺伝子モジュールが必要になるような大局的な発生現象が見つからず,この異論は勢いを失った.またこの議論は前口動物の分節構造と脊椎動物の分節が相同かどうかという論争とも関連する.これはまだ決着がついていないそうだ.このあたりの解説は深く,わかりにくい*4
ここまでの議論を経て倉谷はようやくボディプランの多様化がアルシャラクシスで説明できるのかという問題に取りかかる.そしてまず結論として,観察事実は,一旦できあがった複雑な体制の動物がアルシャラクシスを経て別の動物群を創り出したというシナリオを支持しているとする.そしてそのシナリオを具体的に解説している.ここは読みどころの1つとなる.
- カンブリア紀より前には現在では幼生とされるような単純な生物がそのまま性成熟して生活環を回していただろう.
- その一部はヘッケル的過形成を模索するうちに大型化して新しいボディプランが獲得されていっただろう.カイメン,板形動物,有櫛動物*5はそのようにばらばらに成立した動物系統かもしれない.
- しかし刺胞動物の祖先の出現により状況は一挙に変わった.刺胞動物とすべての左右相称動物の中では,異なった動物門の間に相同な細胞型からなる同一のパターンを持つ器官系が頻繁に現れるようになった.おそらくすべての左右相称動物は刺胞動物の内群ということになるのだろう.
- さらに左右相称動物では三胚葉が確立し,細胞型の相同性が堅固になり,遺伝子制御ネットワークと細胞型の保守性が確立された*6.
- つまり細胞型,諸器官,諸構造の形態学的相同性を保持したままボディプランだけが進化している.これは初期発生過程が変更された結果新しいボディプランが生じたとするアルシャラクシスを支持するものだ.(ここではさらに対立する考え方を丁寧に批判している)
ではどのようにボディプラン進化は可能になったのか.ここからは倉谷の「試論」になる.
- ダーウィン,ライエル的な「微小な変化の積み重ね」ではなく,「ラディカルなモジュールの繋ぎ替えによって進行した」と考える.ボディプランの変更が「微小な変化の積み重ね」で生じるとするのは飛び越えるべき適応地形の谷を無視しており,控えめに言っても説明不足だ.
- ボディプランが保存されていれば進化は比較的速やかだが,ボディプランが大きく変更する進化は一般的には難しい.しかし過去においては現実に可能だった.*7
- 新しいボディプランの進化とは,基本的体制の軸や極性を再定義し,器官の配置を再統合することを意味する.これらは初期発生プロセスであらかた決定されてしまう,だからアルシャラクシスのみがボディプラン進化を説明できることになる.
- このような変化にあたって,器官・構造の相同物が祖先と比べて形態学的にシフトした位置に現れる場合がある.そのような場合は深層的相同物として理解できるような様々なタイプの類似性同一性を見ることになる.また異なったボディプランに進化的に保存された細胞型が現れる場合も同じシナリオで理解できる.これらの深層的相同物が機能的意義を偶発的に得たときにその新しいボディプランが淘汰圧をくぐり抜ける見通しが得られることになる.
- 新しい位置関係やシフトしたタイミングは新しいパターンを生む.それが滞りなく生じるために,発生過程のあちこちに拘束が生じる必要があり,安定化淘汰によりもたらされる.それは発生経過のエピジェネティック地形のキャナライズとして理解できる.これはボディプランが離散的であることを説明する.
- 胚発生は典型的な複雑系であり,還元主義的なアプローチを拒んでいる.それはほんのわずかな違いで大きな違いを生むことや,遺伝子の相同性と形態要素の相同性が時折乖離することを説明する.
- キャナリゼーションは1種のキャパシタを作り上げ,頑健な発生経路をもたらすが,複雑系であるために潜在的な進化の爆弾をいくつも抱え込むことにもつながる.相同的形質が保存される一方で下部構造は変化しうる(経路が網目構造をしているなら,同じパターンに行き着く代替経路が存在する).形態学的相同性に新しい遺伝子モジュールが結合する一方,古いモジュールが乖離する(発生システム浮動).
- 片方で器官形成の発生ネットワークのモジュール性とその堅牢性は動物門の創出を加速させる効果を持った.抜本的なトポロジーの変更においても局所的な整合性がある程度保たれるからだ.
- 詰まるところボディプラン進化の本質は,安定化淘汰,アルシャラクシス,そしてコ・オプションなのだ.
倉谷は最後に「結語」を置き,ここまでに解説したシナリオを統合的に説明したのち,課題としてゲノムの内容とボディプランの関係の解明をあげ,本書を終えている.
本書は新書という外観に反して大変濃密な書物であり,進化発生学の深いところを解説してくれている.発生の本質はデザインと製作という工学的な問題であるために,その進化は単純な適応度極大化だけでは語り尽くせない.それは進化産物で複雑系であり,さらに発生経路自体が淘汰圧を受ける.そのためにボディプランの変更は非常に難しくなるが,初期段階で生じるアルシャラクシスによる大きなトポロジー的変更,下部構造のモジュール性とその使い回し,安定化淘汰によるキャナリゼーションにより可能になるのだ.そして観察事実との整合性,動物門の起源シナリオの提示などが次々となされている.エヴォデヴォに興味にある人にとっては必読の副読本ということになるだろう.
関連書籍
倉谷の本

形態学 形づくりにみる動物進化のシナリオ (サイエンス・パレット)
- 作者: 倉谷滋
- 出版社/メーカー: 丸善出版
- 発売日: 2015/04/26
- メディア: 新書
- この商品を含むブログ (5件) を見る

- 作者: 倉谷滋
- 出版社/メーカー: 工作舎
- 発売日: 2016/11/25
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 倉谷滋
- 出版社/メーカー: 東京大学出版会
- 発売日: 2017/01/13
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (3件) を見る

- 作者: 倉谷滋
- 出版社/メーカー: 工作舎
- 発売日: 2017/02/18
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (4件) を見る
*1:さらに「ゴジラ幻論」という楽しい一冊も書いている
*2:ゼヴェルツォッフはロシアの学者でドイツで学びドイツ語で論文を書いたために現在ほとんど知られていない.倉谷はこの経緯について結構細かく書き込んでいる
*3:ここで倉谷は「『生物には高等下等の序列がない』というためには.単に『それは生物学的厳密でない』と終わらせるべきではない.ヘッケルの『より発生後期に生ずる変化の方がより高等』という議論を打破する必要があり,このアルシャラクシスを認めて発生力の差が無いことまで考察すべきだ」と力を込めて主張していて,なかなか面白い
*4:そもそもある現象がアルシャラクシスなのか,コ・オプションなのかは1か0かで区別できるものなのだろうか,厳密に区別する意味は何かなど気になるところがあまり解説されていない.詳細は「分節幻想」を読んで欲しいということのようだ.
*5:最近の研究によると有櫛動物はかつて考えられていたような刺胞動物の近縁グループではなく,かなり古く分岐した系統であり,独自の細胞型を多く含んでいるそうだ
*6:細胞型の相同性の興味深い例として体性部分と臓性部分の区別が解説されている
*7:アルシャラクシスにより新しいボディプランを得る困難さに関する議論があり,個人的には麻雀で役満を連続10回上がるという事象が感覚的に近いと感じられるという言い方をしていて,いろいろ面白い