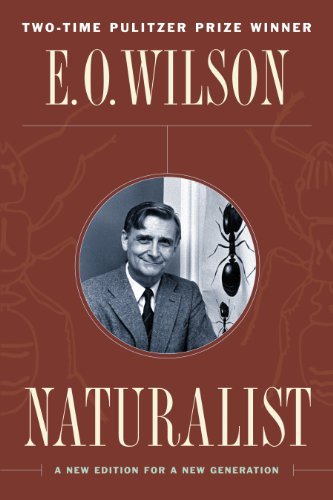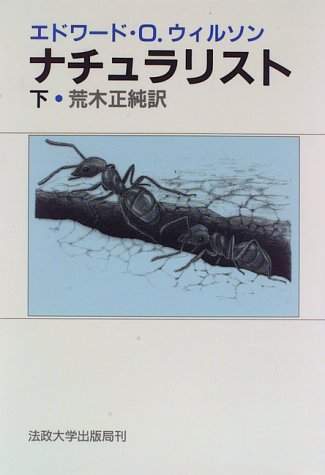本書は1929年生まれで(原書出版時の2020年時点で)90歳を越えるE. O. ウィルソンにより書かれたアリの本だ.
ウィルソンは進化生物学の世界ではもはや生きる伝説とも呼ぶべき巨人だ.もともとはハーバードのアリ専門の学者だが,若き日にロバート・マッカーサーと仕事をしたことをきっかけに,数理生物学や生態学などのさまざまな生物学分野の統合の仕事を精力的に行い,1975年に「Sociobiology(邦題:社会生物学)」を刊行.そこで最終章にヒトの章をおいたことから(ハーバードの同僚であった)ルウォンティンやグールドたちから(今でいう)ポリコレ的な批判を徹底的に浴び,いわゆる社会生物学論争に巻き込まれる.いろいろ辛酸もなめたが,そこから,ある意味「社会生物学」最終章に関する自分自身の仕事と位置づけられる(今でいう人間行動生態学の走りのような試みの)「On Human Nature(邦題:人間の本性について)」と(専門のアリについての分厚い専門書である)「The Ant(未邦訳)」という2冊のピューリッツァー賞受賞の本を出し, 1990年代には「The Diversity of Life(邦題:生命の多様性)」を書いて生物多様性についての啓蒙の先頭に立った.また1998年には「Consilience(邦題:知の統合)」を刊行し,自然科学と社会科学や人文科学の統合を提唱した.この頃のウィルソンはまさに輝く知の巨人であり,私のインテレクチュアルヒーローの一人だった.
しかしその後ウィルソンは(社会生物学を書いたときにはその理論を大いに称賛していたにもかかわらず)ハミルトンの包括適応度理論を否定するようになり,ノヴァクの筋悪な包括適応度理論否定論文の共著者として名を連ね,それにそってナイーブグループ淘汰的な記述が各所に現れる「The Social Conquest of Earth(邦題:人類はどこから来て,どこへ行くのか)」を2012年に書くに至った.これはまことに悲しい本であり,私はお別れの書評(
https://shorebird.hatenablog.com/entry/20130823/1377258574)を書いてウィルソンと決別することにし,(それまでは出された本は必ず読んできたが)その後の本を特に追うことをしなくなった.(とりわけ「The Meaning of Human Existence(邦題:ヒトはどこまで進化するのか)」とか「Genesis: The Deep Origin of Societies(邦題:ヒトの社会の起源は動物たちが知っている)」あたりの書物は怪しい雰囲気満載で遠ざけていた)
そんな中で出版されたのが本書である.アリの本ならまた読んでもいいかなと思って手に取ったということになる.原題は「Tales from the Ant World」
冒頭の「はじめに」でウィルソンはこの本はアリ学の驚きに満ちた冒険物語として書いたと説明している.そしてこれまでアリについての質問で最も多かったのが「キッチンに来るアリはどうしたらいいですか?」だったが,それには「なぜ昆虫がキッチンを訪れてはいけないのか」と問い返したいと不満を表明し,餌を与えて観察しようと提案している.まさに人生をアリに捧げた学者の心意気というものだろう.
第1章は「アリの生活にはヒトのモラル向上のために真似できることは何一つない」と断言することから始めている.単純な自然主義的誤謬の話ではなく,アリの社会は1億5千万年かけてジェンダーリベラリズムが暴走している(働くアリや戦うアリはすべてメス)とか,ハンディキャップを持つアリはコロニーを出て行く(ほぼ必然的に死ぬ)ようにプログラムされているとか,他コロニーに対してきわめて好戦的だということが説明されている.このあたりは「Consilience」に書かれている「シロアリのモラル」の話が思い出されてちょっと楽しいところだ.
第2章と第3章において自伝的な内容が綴られている.ウィルソンは「Naturalist(邦題:ナチュラリスト)」という自伝を書いているが,そこに書き漏れたエピソードも加えてフロリダやワシントンDCやアラバマで過ごした少年時代の思い出(最初の昆虫愛の対象はチョウだったそうだ),戦後の特別法によりアラバマ大学に入れることになり,学者への道が開けたことなどが振り返られている.
そして第4章から第26章までがさまざまなアリの話が語られる本書の中心部分になる.面白いと感じたところをいくつか紹介しておこう.
- ウィルソンは13歳の時にアラバマ州モービルでヒアリのコロニーを発見したが,これは北半球での最初の目撃記録になった.アラバマ大学に入ってすぐの19歳の時にはヒアリの専門家として有名になっていて州当局から個体群の分布と被害の調査依頼を受け,女王アリが8キロもの距離を飛ぶこと,2年以内に新しい世代の女王アリを生み出すことなどを調べ上げた.1958年からのアメリカ南部での殺虫剤の大量散布によるヒアリ駆除計画はこのような生態を無視していたものであり,失敗に終わった.
- 同じくアラバマ大学に入ってすぐの時期にヒメグンタイアリのビバークを発見し,すくい上げて大学に持ち帰った.そこで好蟻性の甲虫を発見した(当時としての大発見であったような書き振りになっている).彼等はパラリムロデス属の甲虫でアリの体表面の油性の液体を栄養源としていた.後世の研究者たちは南アメリカで数百種にわたるグンタイアリに寄生する好蟻性の寄食者集団を見いだしており,その中にはアリの大顎の内側の曲面に乗って生活するダニ,触角の基部に死ぬまでくっついているダニ,後肢の先端に付着して血を吸い,アリの後肢の一部としても機能するハエダニなどが含まれる.
- 1518年から19年にかけて当時のスペイン領イスパニョーラ島で人を刺すアリが異常発生し,一時は植民地放棄の瀬戸際まで追い込まれたがその後沈静化した.このアリが何だったのかは長い間謎とされていたが,2004年にウィルソンはフィールド調査の大量のデータを使ってそのアリがアカカミアリであることを突き止めた.彼等は幅広い食性を持ち,浜辺で繁殖可能で,当時のガレオン船のバラストとして使われた土や岩に潜んで侵入したようだ.
- ウィルソンによる好戦的なアリセレクション:特定の種の低木と共生関係にあり,それを守ろうとして攻撃するキバハリアリ(Myrmecia属94種),クシフタフシアリの一種(Pseudomyrmex triplar),ナガフシアリ(Tetraponera属),着生植物に寄生してそれを守るオオアリの一種(Camponotus femoratus).いずれも防衛が可能で資源的に価値のある巣を守るアリになる.
- アリには外洋を超える能力がほとんど無いようだ.ハワイには現在21属36種のアリがいるがすべてヒトが持ち込んだものだ.ガラパゴス諸島はたった1種だけ在来のアリ(オオアリ属の一種)がいるが,複数種に適応放散はしていない.(なお別のところでキバハリアリの一種がオーストラリアからニューカレドニアに到達している話が出てくる)
- キッカイアリ(Thaumatomyrmex属)の熊手状の大顎がどのような獲物のための適応なのかは長らく謎だったが,ウィルソンがアリ学者たちに呼びかけた記事により,獲物がフサヤスデであることが判明した.
- 最も速く歩くアリはアゴヒゲアリ,最も遅いのは不潔なことで知られるカクレウロコアリだ.カクレウロコアリはカモフラージュにたけ,獲物を待ち伏せ捕食する.(アゴヒゲアリのスピードの適応的な理由については触れられてなく,採取の苦労話が語られている)
- アフリカのマタベレアリはシロアリ捕食に特化しており,大きく,重厚なキチン質のよろいを持ち,集団で高速移動する.また腹部の針による攻撃はアリ界で最悪のもののの一つだ(ライバルはサシハリアリ).彼等は隊列を組んでシロアリのコロニーを襲い,獰猛なシロアリの兵隊集団との集団戦を制して,殺したシロアリの死体を集めて巣に持ち帰る.これは(ウィルソンの評価では)熱帯生物学の中で最も驚くべき現象の一つであり,アフリカに行ったら宿泊施設を抜け出してでも観察する価値がある.
- ウロコアリは大顎をきわめて速い速度で閉じ合わせる.この獲物が何であるかはウィルソンが飼育実験で発見したもので,彼等は素早く飛び跳ねるアヤトビムシ類と軍拡競争していた.このウロコアリとアギトアリの大顎を閉じるスピードは動物界最速のものとされてきたが,マダガスカルのヘラアゴハリアリは大顎の先端を強く押し合わせてからスライドさせる仕組み(指パッチンと同じ原理)でさらに速い時速320キロを達成していることが見つかった.
- 中生代のアリの琥珀封入化石が最初に見つかったのは1966年で,これはウィルソン自身が調べてアケボノアリとして記載した.その後類似の琥珀化石が数多く見つかり,アリの進化軌跡がわかってきた.彼等は直線的に進化したわけではなく,何度も適応放散を繰り返していた.現代のアリは中生代後期に適応放散した1種かごく少数種から進化したものだ.中生代の化石からは大顎を上下に開閉するアリ(ハイドミルメクス属)が見つかっている.
ある特定のアリのグループの話になったり,生態的な特徴の話になったり*1,コミュニケーションの話になったり,アリの専門家として肩の力を抜いて自由に語っている感じが出ていて楽しく読める.自伝的な部分にも味があり,またもう一度「ナチュラリスト」を読みたくなってしまった.私にとってはちょっと疎遠になっていた頑固なおじいちゃんと再会し,その最良の部分とまた出会うことができたような一冊になった.
関連書籍
ウィルソンのアリの本
ピューリッツァー賞を取った超有名なアリ本.ヘルドブラーとの共著
一般向けにかかれた同じくヘルドブラーとの共著
同邦訳.現在では入手困難になっているようだ
ハキリアリについても同じコンビで一冊書いている.
同邦訳.私の書評はhttps://shorebird.hatenablog.com/entry/20120804/1344075902
自伝
同邦訳