
- 作者: ブルース M.フード,小松淳子
- 出版社/メーカー: インターシフト
- 発売日: 2011/02/18
- メディア: 単行本
- 購入: 7人 クリック: 101回
- この商品を含むブログ (12件) を見る
本書は発達心理学者で認知神経学者である著者によるヒトの超自然を信じる傾向(超自然を感じる心を本書では「スーパーセンス」と呼んでいる.)に関する本である.
これが宗教的信仰心のあるなしとは無関係にかなり普遍的に見られることを,著者は「連続殺人犯が着ていたカーディガンを着ることに抵抗があるか」と読者に問いかけることによって示している.確かに忌避の程度に個人差はあるとしても,それはかなり普遍的に見られる心情だろう.著者は様々な場所でこのようなことに関する実験*1を行っており,ほとんどの人が着るのを嫌がることを確かめている.少数の若い男性は時に自分のロジカルさをディスプレーしようと平気だと言い張るが,そのときに見られる最も興味深い現象はとなりの若い女性が傍目にもわかるほど引くことだといっている.つまりこのようなスーパーセンスに逆らうのは現代社会であっても対人関係上問題があり得るということなのだろう.
著者はこのスーパーセンスが何故見られるのかについて,まず「世界にパターン・目的・意図を見つけようとする」,「それがコントロールできることを見つけようとする」という生得的な心の設計図があり,それが他人や動物やものの内面に何らかの「本質」があるという推論を生み,それが文化や個人的体験により強化されるからだと説明している.これは,適応的生得的な心の傾向がうむ副産物という説明に近く,アトランやボイヤーによる宗教の説明と同じ種類の議論だろう.
本書ではこのような説明の骨格を示した後,まず発達心理学の歴史と絡めて,このスーパーセンスが子どもの成長とともにどのように発達していくかを丁寧に追っている.素朴物理学や素朴心理学の発達段階とともに,アニミズム的な本質主義的推論が生成される様子が議論されている.
その後は「他人」「動物」「もの」の素朴理解が本質主義であることを個別に議論する.ここでは「スーパーセンス=本質主義」の具体例が豊富に紹介されていてなかなか面白い.
- 他人の理解については,心身二元論が素朴理解の基本になる.これは人には意図・目的があると考える傾向から生みだされる.そして個人のアイデンティティの基本が,脳というハードでも,単なる記憶でもない「心」であるという理解になり,それは来世や幽霊という超自然信念につながる.
- 動物・生命については本質主義は「生気論」につながり,それが理解の基本になる.これはすべてがつながっている全体論(ホーリズム)とも結びつきやすい.こう考えることにより,遺伝子組み換えに関する嫌悪(それは何か生命の本質を汚している)が説明できる.ホーリズムは何らかのつながりによる薬効があるという超自然信念につながり,漢方薬やホメオパシーの信仰につながる.
- さらに「本質」は接触により伝わるという推論が生みだされる.(本書では指摘されていないが,これは伝染病などのリスクから,汚物に触れないようにすることが適応的な傾向であると議論されるところだ)この傾向で説明できる超自然信念は多い.ここでは,カニバリズム,細胞記憶説,臓器移植への恐怖,ヤギの睾丸移植法,ロイヤルタッチ,移民の死に際してアイルランドの土を棺桶に入れることなどが取り上げられている.
- この推論は拡張され,「もの」にも本質があるということになる.私達はどんなにそっくりでもオリジナルとコピーはまったく異なると感じる.ここでは安心毛布,原子レベルで複製された人間は別人か?などの話題が取り上げられていて面白い.また家族をすり替わった別人だと感じるようになるカプリグラ症候群についてこれは「本質主義」を失ったことにより説明できるのではないかという示唆があり興味深い.
この後,文化や個人的体験による「強化」がどのように起こるかという議論がなされている.著者は確証バイアスや因果推論にかかる傾向などにより強化されやすいのだと主張し,「他人の視線を(背後からでも)感じることができる」という信念がどのように始まり,どのように強化されるかを示している.そしてこのような超自然信仰の傾向に個人差があることは,知性の問題ではなく,前頭側外側部の「計画,直感の抑制,評価」の働きの強さによると主張している.個人差のリサーチはこれからなのだろうが,適応的にはなかなか興味深い問題だ.
最後に著者はこのスーパーセンスの効用についての議論を行っている.著者によるとスーパーセンスは「神聖な価値」を可能にし,それを共有することによりコミュニティの結束を固めるという機能があるのだと主張している.著者は(これによって「本質主義は副産物ではなく適応だ」と主張しているわけではなく)単に機能を指摘しているだけだから,これはこれでいいのだということになろう.しかし私のような適応的起源に興味がある読者にとっては,この説明は少なくとも素朴グループ淘汰的な議論に止まっており,起源の適応的説明としては不十分だ.本質主義が適応か副産物かという問題はなかなか興味深いところだが,このグループレベルの機能だけでは適応と考えるには弱いだろう.
全般的に本書はスーパーセンスの進化的起源についてはほとんど議論していない.最初の「世界にパターンを見つけようとする心の設計図」が適応だという示唆があるだけで,その後の本質主義については議論されていない.*2なかなか面白い素材なのでちょっと物足りないと感じる部分ではある.
「ヒトの本質主義的傾向が何らかの適応的な心の性質から生まれるものだ」というのはこれまでもところどころで議論されているが,本書ではそれが一冊にまとめられているのがセールスポイントだということになろう.私のような読者にとっては.このような本質主義に適応的側面があるのか,個人差はどこから来るのかなどについて思い巡らすよい機会になった.また本質主義の様々な具体例が議論されているところも充実していて,読んでいて楽しい一冊だ.
関連書籍
原書
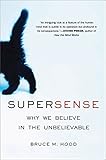
SuperSense: Why We Believe in the Unbelievable
- 作者: Bruce M. Hood
- 出版社/メーカー: HarperOne
- 発売日: 2009/04/01
- メディア: ハードカバー
- 購入: 1人 クリック: 11回
- この商品を含むブログ (4件) を見る