
From Darwin to Derrida: Selfish Genes, Social Selves, and the Meanings of Life (English Edition)
- 作者:Haig, David
- 発売日: 2020/03/31
- メディア: Kindle版
第1章で生物学における目的因の歴史を振り返ったヘイグは,第2章では「利己的遺伝子」と「延長された表現型」の思考の延長部分の説明に入る.なかなか深い.やや詳しく紹介しよう.
第2章 社会的遺伝子
- ドーキンスの「利己的な遺伝子」は私が大学に入る前の年(1976年)に出版され,今でも版を重ねて読まれ続けている.それはとても強い感情を引き起こす本だ.

The Selfish Gene: 40th Anniversary edition (Oxford Landmark Science) (English Edition)
- 作者:Dawkins, Richard
- 発売日: 2016/06/02
- メディア: Kindle版

- 作者:リチャード・ドーキンス
- 発売日: 2018/09/29
- メディア: Kindle版
- 多くの崇拝者達にとって,難解な概念を明晰に表現するこの本は,生命に対する啓示ともいうべきものだ.
- しかし批判者にとってはこの本は邪悪だということになる.批判者の一部はこの本のメッセージを「我々は基本的に利己的で,善なる性質は幻想に過ぎない」と受け取る.また一部は「生命体の否定と遺伝子の栄光」に異議を唱える.別の一部は文化変化をミームの進化とする表面的な視点に反対する.典型的な議論はこの否定反応をめぐってのもので,しばしば心身二元論のねじれを伴っている.
- 「利己的な遺伝子」は自然淘汰産物を説明する際に臆面もなくエージェンシーと目的にかかる言葉を用いている.多くの生物学者は,特に生命科学と物理学の連合を目指す学者は,意味と目的にかかる言葉を排斥しようとする.これは彼等の科学の純粋性を汚すものだからだ.またドーキンスの遺伝子のエージェンシーにかかる用語を非難する生物学者もいる.エージェンシーは人に限られるべき概念だという理由だ.
- 「利己的な遺伝子」は,一般的に人気がある「グループのための進化」「種のための進化」を断固として否定する.ドーキンスは自然淘汰は遺伝子や個体のための良さに向かって進むのだと議論する.ほとんどの箇所で個体と遺伝子を同様に扱っているが,自然淘汰の受益者は遺伝子という立場で一貫している.遺伝子は潜在的に不死であり,生物個体の多くの世代の中で受け渡されていく.生物個体は遺伝子を広げるために進化した精妙な生存機械(ヴィークル)に過ぎない.
- しかしながら「グループのための進化」という議論は消え去らなかった.グループ淘汰擁護者は利己的遺伝子擁護者と激しい論争を繰り広げた.なかでもDSウィルソンは個体淘汰とグループ淘汰が共に働くモデルを作り上げた.彼の数理モデル自体は正しかったが,前提や解釈をめぐって激しい批判がなされた.例えば「彼の言うグループは真のグループではない」とか「彼のモデルは結局個体淘汰を表しているに過ぎない」とかだ.ウィルソンは反撃し,議論はエスカレートした.

The Natural Selection of Populations and Communities
- 作者:Wilson, David Sloan
- 発売日: 1980/12/01
- メディア: ハードカバー
- グループ淘汰擁護者は「淘汰や適応は複数のレベルで起こる」「遺伝子レベルの淘汰はその最下層のレベルの淘汰に過ぎず,何か特権的な立場にあるのではない」と主張した.この議論は当初「階層的淘汰」と呼ばれたが,現在「マルチレベル淘汰」と呼ばれている.Google Ngramによるとこの呼び方の転換は1996年頃だ.私はこのミームシフトには政治的な思惑が絡んでいると考えている.複数的包摂的な「マルチレベル」という用語は権威主義的貴族的な「階層」より魅力的だったのだ.

- このマルチレベル淘汰をめぐる論争を政治的な文脈なしで読み取ることは難しい.マルチレベル淘汰擁護者は自分たちのモデルを「個体がやさしく非利己的である」ことを含意するかのようにプレゼンした.これは(自分たちが利己性の擁護者だと描写されるように感じた)利己的遺伝子擁護者達を激怒させた.どちらも同じように淘汰の結果個体の利他性が進化することを認めていたからだ.
- 私から見ると両者は同じ用語を異なる意味に用いていた.彼等の不一致は大半が意味論の問題だ.それぞれの用語法においてはどちらも正しい.
このあたりのヘイグの利己的な遺伝子(および包括適応度理論)とマルチレベル淘汰論争に関するコメントはなかなか面白い.これで宗教を擁護しようとするDSウィルソンのレトリックは当初より徳シグナリング的であり,論争全体は論理的に用語の定義をめぐる不毛な議論だったということになる.
- 私が「利己的な遺伝子」を読んだのは1980年代になってからだ.ラック,ウィリアムズ,ハミルトン,トリヴァース,メイナード=スミスの議論はドーキンスの明晰な解説を読む前にオリジナルに触れていた.だから多くの生物学者とは異なり,この本によって人生や世界観が大きく変わったわけではない.しかし2冊目の「延長された表現型」は出版直後(1982年)に読むことになった.そしてそれは私の院生生活における啓示になった.それは私にとって生命個体の統一性を根本から覆す本だった.
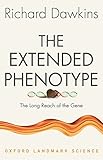
The Extended Phenotype: The Long Reach of the Gene (Oxford Landmark Science)
- 作者:Dawkins, Richard
- 発売日: 2016/10/01
- メディア: ペーパーバック

- 作者:リチャード・ドーキンス
- メディア: 単行本
- ドーキンスは「私にとって包括適応度は自然淘汰における個体のレベルを救おうとする最後の試みに見える」と書いている.ドーキンスの視点では「遺伝子はその表現型がその遺伝子の複製効率に与える影響にかかる淘汰に服する」ということになる.このような表現型効果は生物個体の身体範囲を越えることがある.ドーキンスはこの本の定理をこう表現している.「ある動物個体の行動は,その行動のための遺伝子の生存を最大化させる傾向を持つ.そしてその遺伝子はその行動個体に内在するものに限らない」
- 「延長された表現型」の2番目のテーマはある生物個体内にある遺伝子間の不和だ.異なる遺伝子は異なる目的を追求している.性染色体にある遺伝子は常染色体にある遺伝子と異なる行動を好む.核遺伝子とミトコンドリア遺伝子は息子の価値について意見を異にしている.歪比遺伝子はならず者でありメンデル法則を守る遺伝子の犠牲において利益を得る.私は確信的な遺伝子淘汰主義者になり,ゲノミックコンフリクトの擁護者になった.
- 「延長された表現型」は,複雑な行動や構造について,それは個体ではなくそれにかかる遺伝子のための適応としての自然淘汰産物であると捉えている.
- よくある批判は「生物個体は統一体であり,どの遺伝子も他の遺伝子の助けなしには複製できない」というものだ.ここで含意されているメタファーは「生物個体は機械であり,遺伝子は機械を作るアッセンブリーラインに指令を行う」というものだ.しかし別の「遺伝子は社会グループの一員だ」というメタファーも可能だ.社会も機械と同じく入り組んだ相互依存と精妙な分業が可能だ.しかし機械と異なり,社会はデザインされたものではない.協力と調和が当然の前提になるわけではない.もし協力や調和があるならそれは説明がなされなければならない.社会理論には様々なものがある.一部の理論は個人の行動の力を強調し,一部の理論は社会の個人の自由の制限を重視する.本章は生物個体を遺伝子達の社会としてみる.そして社会を乱す遺伝子間のコンフリクト,それを和らげる社会契約を探求していく.
- 遺伝子視点の理論は,それが持つヒト社会への含意のためにしばしば罵倒される.しかし遺伝子が自分の複製効率だけを優先する邪悪で利己的で欺瞞的な存在だとしても,それはヒトが同じように利己的であることを意味しない.生命体は集合的な存在であり,集合体の行動や決断はその構成メンバーのそれを反映するとは限らないのだ.私がこの文章を書いている今この時にも,私の遺伝子達は常に争いあっているだろう.しかし私は何とか切り抜けている.私は自分が淘汰単位でなかったことをありがたいと思うのだ.
ヘイグにとっては「延長された表現型」こそが目から鱗を落としてくれた本だったという回想も面白い.確かにこの「延長された表現型」の方がよりロジックは深い.ともあれ,ヘイグもドーキンスの影響を大きく受けてリサーチの道を突き進んだということがわかる.
関連書籍
多くの生物学者が自分がいかに「利己的な遺伝子」に影響を受けたかを語っている本.私の書評は
https://shorebird.hatenablog.com/entry/20060909/1157762907

Richard Dawkins: How a Scientist Changed the Way We Think
- 発売日: 2006/03/09
- メディア: ハードカバー