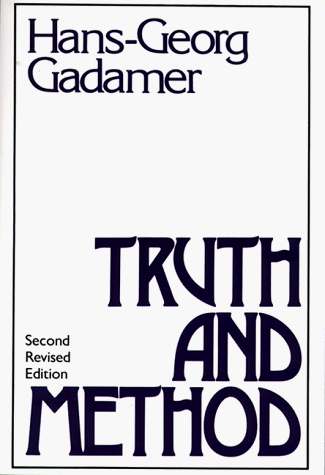最終章「ダーウィニアン解釈学」.文理の学問の違いを議論し,人文学には直感的経験的把握という要素があることを指摘し,ヘイグは「意識」の問題に入る.そして自動的行動においては無意識下でも世界の入力が解釈され続けていることを指摘し,自由意思をめぐる哲学のハードプロブレムにも言及し,その考察については進化適応的な視点が重要だとコメントする.そしてそこには全体の理解と部分の理解をめぐる解釈学サークルの問題が立ち現れると解く.
第15章 ダーウィニアン解釈学 その7
客観的現象 その1
- 個人の自己認知は人生の閉回路の中のゆらめきにすぎない.それが,なぜ個人の(判断ではなく)偏見が,彼の歴史的なありようのリアリティを構成しているのかについての理由なのだ.
ハンス=ゲオルグ・ガダマー
ガダマーは第11章と第12章の幕間で登場した解釈学アプローチをとるドイツの哲学者だ.前回と同じく引用は「真理と方法」から.
ここからヘイグは自由意思をめぐる哲学のハードプロブレムから,別の哲学の問題「客観性は存在しうるか」に移る.
- それほどハードではない哲学の永遠の問題は,知覚世界の中で客観性がどのように存在することができるかだ.知覚以外からの入力なしでは全ての知識は主観的だという感覚がある.個人は物事に直接アクセスすることはできない.アクセスできるのはその解釈だけだ.
この問題に関してはデカルトの「我思うゆえに我在り」が登場するのかと思ったが,ここではそこには深入りせずに,一見主観的でしかないと思われる感覚入力の解釈も,進化適応的な観点から考えると,客観的な世界のガイドとしてある程度信頼できるものであることが説かれる.これは進化生物学者としては当然のことだろう.
- しかし生物個体の解釈能力は世界の中で効率的に行動できるように進化した.この理由からそれは有用なガイドを提供してくれると信頼できる.私たちの判断には根拠があるのだ.
- 個人は過去の偏見を現在の判断に持ち込む.過去の偏見はガダマーのいう「その歴史的なありようのリアリティだ」.客観的「事実」とは私たちが皆同意できることだ.ある生物種のメンバーに世界の物事の性質についてのおおむねのコンセンサスがあるのは,それらが進化史を共有しているために似たような知覚や解釈のメカニズムを持つからだ.
すると私たちが「客観的事実」と考えるものは,進化適応的に生じた種普遍的なメカニズムによるある程度信頼できる「解釈」であることになる.
- カントはこう書いている:「物事がそれ自体なんであるかを私は知らない.そして知る必要もない.なぜなら物事は私の前にただ現れるからだ」.純粋理論とはかくも役立たずなものか! そもそもある物事の客観的真実を必要とする実践的理由は,逃げなかったらそれはあなたを捕らえて食べてしまうかもしれないからだ.チータはガゼルを即座に捕らえてその肉体の一部にしてしまうだろう.その外見に食べられるように見えるだけではないのだ(rather than appears to be eaten by an appearance.).主観性は知る必要に客観的に埋め込まれている.
そしてここは進化的視点を持たない場合にどのような袋小路に入り込んでしまうのかをカントをディスることにより明示していることになる.引用は「純粋理性批判」から.なおこの光文社の新訳古典文庫版は全7巻になっているようだ.