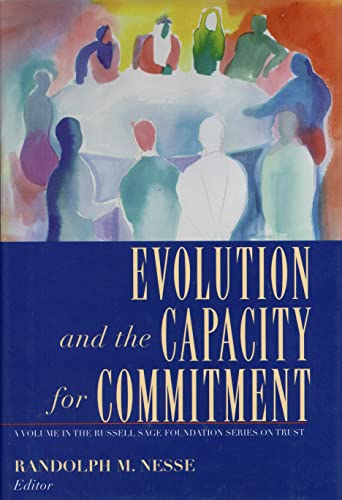本書は三中信宏による理系研究者のための読書論,書評論,そして執筆論の本だ.一気呵成に迸るように書かれた文章は迫力十分で,そしてすべては自分の(研究の)ためというポリシーが圧倒的に壮快だ.
第1楽章 読む:本読みのアンテナを張る*1
冒頭は「本との出会い」から始まる.本との出会いは一期一会でこれはと思う本は逃してはいけないこと,探書アンテナを張ることの重要性,ランダムな出会いもまたよいこと,多言語蔵書の深みなどが語られている.
そこからいかに深く本を読むかというテーマになる.読むにはまず本を読みきって何が書いてあるかを理解するという段階,そして次になぜこの本が書かれなければならなかったかを問いかける段階があるという.そして本を学べばより世界は広がり,得られた知識ネットワークは信頼するにたる基盤となるのだ.
ここから三中は電子本と物理本(特に物理本の擁護)について語る.何度も「数々の電子本のご利益は理解している」と留保しつつ,物理本のトークンとしての固有性や実体性,(電子本でしばしば生じる)薄切りにならないことによる知識の体系化,参照元としてのフィジカルアンカーの完全性と信頼性を熱烈に擁護する.そして便利な電子本を利用するときには物理本もともに買い求めて蔵書とするぐらいの慎重さが必要だと結論づけている.
また読書においては(読み込んだ本の内容の)忘却との戦いでもあるとして,マルジナリア(本自体への書き込み),別紙へのメモとり,付箋についても熱く語っている.読書は「部分から全体へのアブダクション」と見做すことができ,それには痕跡が重要であり,さまざまな書き込みは積極的かつ生産的な読書行為として不可欠であると言い切っている.優先順位が明確ですがすがしい.さらに本を完全に味わい尽くす姿勢にも一本筋が通っている.“極私的スタイル”として目次,文献リスト,索引はもちろん,註,カバー,帯へのこだわりを語っている.文献リストの奥深さについての記述は読みどころだ.
第2楽章との幕間の間奏曲としてインターリュード「棲む:“辺境”に生きる日々の生活」が収められている.三中のこれまでの研究者としての人生航路が語られ,マイナーな研究分野“限界集落”と蔵書をめぐる世知辛い現実とそれに対する覚悟が記されている.
第2楽章 打つ:息を吸えば吐くように
ここでは三中はまずこれまでの書評人生を振り返る.研究成果の一つとしてアウトプットした書評を記録してきたこと,讀売新聞の書評委員を引き受けてから書評を書くペースが一気に上がったこと,ネット書評とのかかわりなどがつらつらと書き連ねられている.書評を書くことについての三中のモットーは「息を吸えば吐くように」なのだそうだ.
そこから書評世界の多様性が描かれる.日本では理系の本の書評が少ないことに少し触れたあとで,書評には短評や紹介のように短いものから,書かれたものに自分の見解を重ね合わせる比較論評を含む長いものまでさまざまなものがある.そしてそのような多様性の中から,ブックレポート的なもの,長いもの,専門書の書評,闘争的な書評の例を三中自身の書評群の中から実例を具体的に収録している.個人的にはこれらの書評のいくつかはかつて読んだことがあるものでいろいろ感慨深い.特に最後の闘争的書評(具体的にはAlan de Queirozの「Monkey’s Voyage」についての書評と金森修の「サイエンス・ウォーズ」についてのもの)は火を吹くような文章が綴られており,何度読んでも楽しい*2.
そこから「書評分布」の話になる.書籍の執筆者は当然自著の評判が気になる.しかし(ネットの世界も含めると)世の中にはとんでもない外れ値の書評も当然存在する.三中はさまざまな書評に一喜一憂するよりも,書評をまとめてその評価の頻度分布の姿を見ることを勧めている.これにより自著のより平均的な評価(その中には耳を傾ける価値のある指摘がある可能性が高い)を知ることができ,心の平安を得られるというわけだ.ここではあえて同じ本(岡西政典の「新種の発見」)に対して絶賛の書評,敵対的書評,平均的書評を三中自身が書き分けてみるという実験があって面白い.
ここから書評者もその書評のできに対して評価の対象になること,書評メディアの移り変わりについてふれたあと,最後に書評を書くことの(利己的な)メリットが挙げられている.書評を書くことにより読後の備忘メモが整理され,体系化されて記憶が強化される.そして自分の書評群は最も信頼できる書物資料となる.そして書評を書く自分自身を分析できる機会にもなるとされている.このあたりは(書評をこつこつ書いている一人として)いかにもよくわかるところだ.
第3楽章までのインターリュード「買う:本を買い続ける背徳の人生」では蒐書の背徳的な喜びにふれたあと,バイヤールの「読んでいない本について堂々と語る方法」にある蒐書および読書論が解説されている.バイヤールはある本を読むことはその本を取り巻く文化的コミュニティを解読することであり,本はその上位の「本の集合体」があって初めて正しい位置づけを持つと主張している.
本を読むという行為に及ぶときには,どのような集合体が想定でき,どのように読んでいくかが問われることになるのだ.三中は専門知,暗黙知のさまざまな側面にも触れながらこの問いを受け止める.そして最後に決してすべてを読み尽くすことはないだろうがそれでもとても重要な自分の蔵書ライブラリーの有り様を語っている.
第3楽章 書く:本を書くのは自分だ
ここでは理系研究者として単著を出すことの心構えが最初に書かれている.三中曰く,論文は短距離走であるが単著は長距離走であり,書くにあたっては(論文の場合の微分スタンスとは異なる)積分スタンスが求められるということになる.そして本を書くということは体系化を行うことであり,それは何よりも自分にとって役立つと力説されている.
このあと学術書と一般書は区別できるのか(装幀によってはできないが,少なくとも学術書であれば文献リスト・註・索引の3点セットが必須),書くことと研究者ライフスタイル(自分が属する学問分野(関連領域を含む)の歴史的変遷と科学社会学的動態を正しく認識しているかを含む)との関連が描かれる.
そしてここから第3楽章の中心になっている超実践的執筆私論が置かれており,三中のこれまでたどってきた「遅筆」の問題とシルヴィアの「たくさん書く方法」メソッドによる解決がヴィヴィッドに描かれている.ここはこの「時間厳守」「計画厳守」「弁解無用」「細分目標」「公開加圧」「拙速主義」(要するに四の五の言わずにとにかく毎日一定量書く)が生み出す「整数倍の威力」が実例を含めてこれでもかと描写されていて迫力満点だ.
その後は目次,文献リスト,註,図版,カバー,帯についてのこだわりが蘊蓄込みで解説されている.
そして最後に後奏曲としてポストリュード「本が築く“サードプレイス”を求めて」が置かれている.三中にとっての「本の世界」は自宅でも職場でもない第3の場所ということになる.そして翻訳,英語本への寄稿,自著の系統樹について語られている.
本書では三中独自の読書論,書評論,執筆論が熱く語られている.これは多くの本好きの読み手に深く響くに違いない*3.そして本書はさらに読み手に各自の読書スタイルさらには各自の読書人生を省みるきっかけを与えてくれることになるだろう.まさに本好き(そして特に科学書好きな人)には格別の一冊だ.
関連書籍
読んでいない本について堂々と語る方法
たくさん書く方法
読後雑感
そして私も(本好きの一人として)読みながらいろいろ考えさせられた.三中ほど熱くは語れないが自分なりの“極私的”読書,および書評スタイルについて感じたことをここに記しておこう.
本shorebirdブログの書評記事について
「読む・打つ・書く」ではブックレポート型の書評の例として本ブログを紹介いただいている.また本ブログの書評記事は「新刊科学書を広く潜在的読者層にアナウンスするという点で間違いなく〝公共性〟がある」と評価いただいており,まことに恐縮の極みであり,大変うれしく思う次第だ*4.ありがとうございます.
私がブログで書評を公開しているのは,しかし実は三中と全く同じ「利己的なスタンス」で行っているものだ.もともとはただ本を読み散らかしているだけだったが,あるときに行動生態学を体系的に勉強しようと思い立ち,そこで勉強としてこれから読むべき本,そして読んだ本のリストを作り始めた.最初は書誌情報だけだったが,簡単な感想を付けるようになり,さらに何が書いてあったかのメモを付けるようになり,最終的にやや詳しい要約と所感を書くようになった.これをエクセル上で管理していたが,この要約を含む蔵書データベースは検索可能であるために,「あそこに何が書いてあったのか」とか「ある事項について確かに何か本を読んだけど何だったか」という「忘却との戦い」において非常に役立つことに気づいた(このあたりは全く三中の指摘通りだ).そしてますます要約の量が増えていった.
ここで世の中にブログなるものが現れるに至り,さっそくはじめてみた.そしていくつかの試行錯誤の後,ブログ開設以降読んだ本(そして忘却するにまかせたくない本)についてはブログに載せていくことことにした(ここで,もしかしたら世の中の誰かの役に立つこともあるかもしれないと思い,少し体裁を整えて書評記事や読書ノートとして公開するようになった).すると読み返しや事項検索がより容易になり,さらに役立つことになった.というわけで本ブログもその基本的スタンスは「利己的に役に立つ」ために書いている(そして誰かの役に立つことがあるなら望外の喜びである)ということになる.
電子本と物理本について
私はもう圧倒的に「電子派」だ.それは何より自宅の書棚スペースが飽和しているという事情が大きい.職場に膨大な書籍置き場があるわけでもなく,蔵書は基本的に自宅に置くほかない.床から天井までの作り付け書棚が上下9段幅230センチ,上下8段幅230センチ,通常の書棚上下6段が3セット(幅80センチ,80センチ,50センチ)このかなりの部分で手前と奥に2列で本が詰め込まれ,もはやこれ以上はどうにもならず*5,購入しただけ処分する他ない.ほぼそうなっていた10年ほど前に始まった電子書籍革命は私にとってまさに福音だった.電子本は何か別の本を処分せずとも購入できるのだ.そして物理本しか出ていない本を購入して別の本を処分する場合も,電子化されているものであれば読みたくなったらまた電子で買えばいいという割り切りとともに心安らかに処分できる.これがどんなにありがたかったことか.
また洋書の場合はタップ辞書が使えるかどうかが圧倒的に大きい.このほか老眼に優しいとか書籍内のみならずWeb検索できる*6とか便利な点には事欠かない.少なくとも読むには電子本の方がいいと感じる.あと「見かけた本は一期一会でとにかく買っておかなければ」という強迫観念からかなり自由になれるのも福音の一つだ*7.また三中も人生の終末期と蔵書の運命について語っているが,これも電子書籍はアカウント消滅とともにこの世からきれいさっぱり消えるという潔さで,後の人に(これ以上)迷惑をかけることがないというのもすがすがしい.
では三中が力説する物理本の重要性についてはどうか.三中はいくつか論点をあげているが,そのうち多くは(特に日本の)出版社の姿勢によるところが大きいと思う.電子化の際の情報の抜け落ちは出版社側の制作姿勢の問題だ*8.特に問題なのはページ数を表示する機能がKindleなどのプラットフォームにはあるのに日本の出版社があまりそれを使っていないことだ*9.これでは三中の言う通り引用するためにだけ物理本を見る必要が生じてしまう.また図版の解像度も,電子本の性質から言えば物理本の印刷よりはるかに解像度の高い画像データを入れることもできる*10わけだから,これも出版社の姿勢によるところが大きい.
とはいえ現状を前提にすると抜け落ちがありうる以上,研究資料として利用するなら三中の言う通り物理本をおさえておくことが必要になる.これはその通りだ.日本の出版社におかれては電子化の推進とともに*11,ぜひこのあたりの姿勢を改めて電子本の情報を完全化し,そして物理本と電子本の同時発売*12を推進していただきたい.
だから残る本質的な論点はトークンとしての実在性,フィジカルアンカーとしての重要性ということになる.ある意味安心感の問題なのかもしれないが,自分が引用するものの基礎が確実にどこかにあることの保証を求めるのであれば(将来的に電子本にかかる何らかのデジタルデータ認証システムが実装されない限り)それは三中の言う通りということなのだろう*13.
目次,文献リスト,索引,註,カバー,帯などについて
目次,文献リスト,索引*14の重要性について三中の見解に異論は全くない.
註については少し感覚が異なる.三中は読書動線が切られることを嫌い,註について否定的だ*15.しかし私は註のある文章を読むのも書くのも好きだったりする.伝えたいメッセージはまっすぐに本文に記し,枝葉は註に落としておく方が,真に伝えたいこととどうでもいいが書き残しておきたいことが区別でき,論旨はより明瞭になる.註はとりあえず(まあはっきり言ってどうでもいい)蘊蓄を書いておきたいときにはとても便利だ.読むときにも読み方は読み手の自由であり,とにかく本筋が知りたいなら註を無視すればいいし,枝葉を楽しみたいときにはしっかり全部読むことができる.一度目は本文のみ,二度読みするときに註までという読み方でもいい.これは伝えたいコンテンツはネットワークあるいはツリー構造であり,文章はリニアにしかならないこととも関連するように思う.
註について私が特に好きなのはドーキンスの「利己的な遺伝子」改訂第二版以降の詳細な註だ.この註をなめるように読めたのは至福の一時だった.
カバーは三中の言う通りに大事にしたいが,問題は帯だ.私もかつては帯をつけたままにしていたが,本棚に入れたり出したりするたびにちぎれそうになって精神衛生上よろしくない.帯だけどこかに保存しておくのも面倒だ.それにほとんどの帯は著者の伝えたいメッセージではなく,出版社の(場合によっては羊頭狗肉の)宣伝文句が(これもしばしば下品に)強調されているような代物だ.というわけで,あるときから購入する本の帯はすべてきれいさっぱり捨てるようになった.確かに例外的に創意工夫のある帯もないわけではないが,いまのところ後悔するような事態は生じていない.それにそもそも帯は書店で付け替えられる場合もあり,三中の言うフィジカルアンカーの一部にはなりえないのではないかという気もする.
忘却との戦いについて
私はかつては本自体への書き込みをためらい,「別紙へのメモ」派だった*16.しかし最近はもはや(スペース確保のために処分することはあっても)できるだけ高値で古書店に売らなければならない状況になることはまずないだろうと思えるようになり,ためらわず書き込むようになった.この点でも電子書籍はとても便利だ.何色ものアンダーラインが自由自在(消去も可能)で,メモも余白スペースの大きさにとらわれずに好きに書き込め,一覧表示も検索もテキストのコピペも可能だ.そしてこのようなメモを書評の形に書き直してブログに載せておくのが(前述した通り)自分的には最もいい忘却との戦い方になっている.(それに単純に昔の自分の書いたものを読み返すのは結構楽しいものだ.それにしても10年も経つと本当に忘れていることが多くて驚く.)
私にとっての読書
ドーキンスの最新書評本ではないが「本は人生を豊かにしてくれる」.
思い返せば私は小さい頃から本の虫だった.子どものころは虫取りなんかもしたが,断然本の方が好きだった(テレビとどっちが好きだったかは微妙だ)*17.親が当時よくあった毎月一冊ずつ刊行される少年少女世界文学全集のシリーズを購入してくれたのはありがたかった.配達されるたびに楽しみに読み込んだものだ*18.また通った小学校の図書室が(当時としては)とても充実していたことにも感謝の念しかない.常に何かしらの本を借りて学校の机の中に置いていた.
小学生のころはフィクション(お気に入りはヒュー・ロフティングのドリトル先生シリーズとアーサー・ランサムのツバメ号シリーズ)とノンフィクション(世界なぜなに物語とか子ども向け恐竜本とかが好きだった.バージニア・バートンの「せいめいのれきし」の様々な描写は特に印象的だった)をそれぞれ読んでいたが,だんだん(SF以外の)フィクションは映像もの(あるいはコミック)で楽しむ方が好みになり*19,長じてから読むものは科学書と歴史書が中心になった.作り話を読むよりも,探求の努力の上に明らかになった事実を知り,その背景のロジックが明らかになることに圧倒的に迫力を感じたということだろう.
大学に入学したばかりのころデズモンド・モリスの「裸のサル」を読んで,ヒトを理解するためには生物学的な考察が最も重要で本質的ではないかと思うようになり,科学書の中でも進化関連の本を特に読むようになった.そして衝撃的な読書経験となったのが1980年代後半にドーキンスの「利己的な遺伝子(初版は「生物=生存機械論」というひどい邦題だった)」に出会ったことだ.まさに目からウロコがとれたような鮮烈な読後感だった.そこで一念発起して行動生態学に集中して1から学ぶこととし,当時出版されたばかりの様々な教科書を読み込み,また数理的な理解のために微積分,微分方程式,線形代数,確率統計も(極く初歩だが)勉強した.基礎から学んだことにより大きく視野が広がり,読み込みも深くなり,ますます進化関係の本を読むのが楽しくなった*20.訳書が出るまでのタイムラグを我慢できずに原書を読むようになったのもこの頃だ.しばらくすると進化心理学が勃興し,それにも熱中して今日に至るわけだ.
映像エンターテインメントもいいが,やはり本当に深いところを楽しむには本が一番だ.振り返って考えてみて,本は本当に私の人生を豊かにしてくれたと痛感する.昨今は読書離れがしばしば話題になるが,このような体験を与えてくれた日本の出版文化の将来に幸あれと祈らずにはいられない.
ドーキンスの書評本.私の書評はhttps://shorebird.hatenablog.com/entry/2021/07/21/100036
出会った本たち
ドリトル先生アフリカゆき 本家英国ではバンポ王子の描写が人種差別的だということで発禁になりかかっているそうだが,いまのところこの岩波本は大丈夫のようだ.
ツバメ号とアマゾン号
せいめいのれきし
裸のサル 現在では文庫化されているようだ
生物=生存機械論 初版はこういう題だった
註が素晴らしい第2版
その他特に印象的だった本たち
Narrow Roads of Gene Land I
Foundations of Social Evolution
延長された表現型
Language Instinct
How the Mind Works
The Mating Mind
進化遺伝学
人間はどこまでチンパンジーか
Evolution and the Capacity for Commitment
The Handicap Principle
Genes in Conflict
Cuckoos, Cowbirds and Other Cheats
*1:なぜ「楽章」なのかについて三中はあまり語ってくれていない.クラッシック音楽の嗜みを垣間見せているだけのように見えて実は何か深い意味があるのかもしれない.あるいは単に「本は読むのも書評するのも書くのも楽しいのだ」ということかもしれない
*2:特に「Monkey’s Voyage」についての書評は自分の読み方の浅さに気づかされてくれたものでもあり,懐かしい
*3:私の観察範囲では,本好きは皆「本や本屋について書かれた本」が大好きだ.
*4:事項索引や書名索引にも記載されていて,全く恐縮するほかない
*5:いったん床置きを始めたらあとは歯止めがなくなり,間違いなくまともな生活が不可能になる未来が見える
*6:何らかの生物の名前が出てきたときにすぐにその場で画像含めて検索できるのはとてもうれしい
*7:もちろん電子書籍も出版サイドの意向でサイトから引き上げられることはあるだろうが,物理本のようにはっと気づいたときには実物が書店店頭から消えてしまいどうにも手に入らないなどということが生じることは劇的に減るだろう.とにもかくにも見かけたものはとりあえず買っておくという必要はなく,ほしいものリストに入れておけばその気になったときにすぐ購入してその場で読み始められる.物理本積ん読の様に物理スペースを圧迫せず,ほしいものリストがどんどん長大化するだけという感じになる.Kindle購入積ん読もなくなるわけではないが,私の場合それはセール価格絡みで生じることが多い.
*8:なお薄切りの問題は,それしか入手できないわけではないから,むしろ読者側の問題だろう.
*9:英米の多くの科学書ではページ数を入れるようになっているだけに日本の出版社の姿勢が問われるところだと思う
*10:現在でも一部の電子本には物理本よりも解像度の大きい図版が実装されている
*11:多くの大学系を含む学術出版社がなお電子化に消極的なのは本当に残念だ.
*12:これも大いなる不満の種だ.英米では同時発売がほぼ常識化しているのに,なぜわざわざ電子本を遅らせるのか? 誰得なのか? 電子本を好む潜在読者を不快にさせ,結局買い控えを招き,場合によっては購入意欲を冷めさせてしまうだけではないか.出版社に得があるとは思えない.くわえて日本の出版社のかなりの部分が「電子本が(あとであれ)出るのかどうか,出るならいつか」という情報をあまり公開しないという姿勢であるのにもさらにいらいらさせられる.
*13:もっとも物理本を確保したとしても火災や水害のようなことはありうるわけで結局相対的な安心感の問題ということになる様な気もする
*14:電子本においては本文内の検索が可能だから索引の重要性は大きく下がるが,著者がどの語を重要と考えているかを示唆するという役割は残るだろう
*15:これも電子本であれば,タップ一つで註が開きタップ一つで元の本文に戻れるので,動線が切られるダメージは(なくなりはしないが)小さくなるように思う
*16:電車で読んでいるときなどによく使ったのは書店で被せてくれるブックカバーの裏側だった
*17:敬愛するドーキンスの自伝には「小さい頃はアフリカで育ったが自分は自然観察よりも本の方が好きだった」とあって,とても親しみを覚えたものだ.
*18:「十五少年漂流記(2年間の休暇)」とか「小公子」とか「家なき娘」とかが収録されていた.いくつかの物語は今でもあらすじを覚えている.(追記:懐かしくなってググってみたら,私の読んでいたのは小学館の「少年少女世界の文学全集」全50巻だったことがわかった.当時の少年少女向け全集物の中では高級感あふれる装幀で,各巻の表紙には世界の名画があしらわれている.ネットにはいろいろ写真もあって,ことさら懐かしい.)
*19:フィクションは登場人物の心の動きが重要になり,表情や声調があるものの方が私的にはより楽しめるということだと思う
*20:同じ頃,世界歴史全集を4~5シリーズ読み終えて,歴史書についてもそれまでの手当たり次第の読書からどこかを深堀したくなって古代ローマ関係を集中的に読むようになる.その中でも古代ローマ法に関する本については日本語で入手できるものはほとんど読み込んだ.昨今は大学法学部における(日本法の継受元である)古代ローマ法の講座がほとんど無くなり,古代ローマ法に関する日本語の新刊がほとんど出なくなっていて,これも寂しいものだ.いずれにせよ歴史書の読書体験はまた別の話になる.