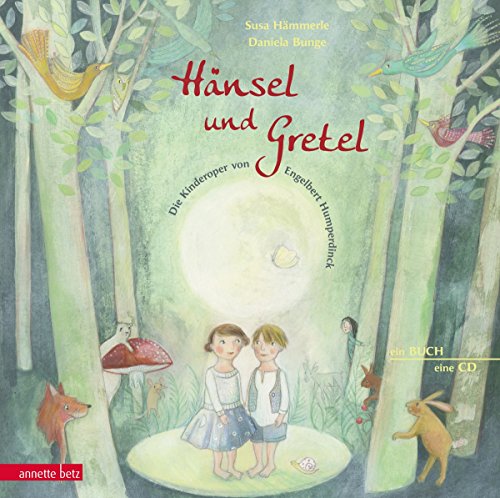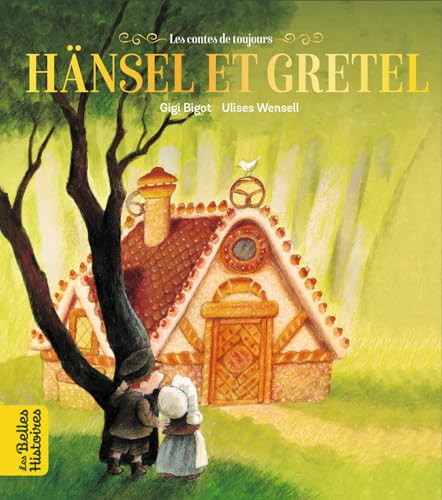本書は進化的視点から精神病理学の包括的な枠組みを構築する試みを解説する一冊.著者のマルコ・デル・ジュディーチェは進化心理学者で,パーソナリティの進化,自己制御,アタッチメントスタイル,精神病理の進化などをリサーチテーマにしている.本書では精神病理を生活史戦略の視点から捉え,FDSモデル(早い生活史戦略,遅い生活史戦略,防衛メカニズムの挙動という軸で様々な病理を捉えるモデル)を提唱し,その後個別の精神病理を解説していく書物となっている.原題は「Evolutionary Psychopathology: A Unified Approach」
導入
導入では進化精神病理学の現状と本書の試みが述べられている.
- 進化理論は正常な行動を研究するための基盤であるだけでなく,精神障害や精神病理と正常の境界を理解するための強力なツールだ.過去10年でいくつかの研究は進展したが,包括的な枠組みが欠如しており,進化精神病理学はまだその真の可能性を発揮していないことは明らかだ.
- 進化精神病理学がDSMに代わる進化分類を提唱しきれていないのは,この分野の概念構造がなお曖昧であるためでもあるだろう.現在併存症パターンに基づく精神病理の構造モデルが主流になりつつあり,それは(DSMと異なり)機能に焦点を当てているにもかかわらず,進化学者はこれを傍観してきた.
- 本書は生活史理論を用いて精神病理学の真の統合的アプローチに向けた一歩を踏み出そうとするものだ.
第1章 人間の本質についての概説
第1章では進化生物学,人類学の基礎知識が概説される.
チンパンジーとボノボの系統からの分岐,ヒトの狩猟採集生活における適応形質複合体,社会脳,文化伝達,農業革命と新奇環境,至近要因と究極要因,自然淘汰と適応,包括適応度とハミルトン則,利己的遺伝子と(遺伝子)適応度を最大化するエージェントとしての個体,グループ淘汰(マルチレベル淘汰と包括適応度理論が数理的に等価であることが明確に述べられている),個体間コンフリクト,ゲノム内コンフリクト,性淘汰,社会淘汰,配偶システム,配偶者選択と配偶戦略,協力と利他性,大規模協力と道徳規範,集団の凝集と分裂,発達,可塑性と水路づけ,個体発生的適応と遅延適応,ライフステージとステージ間の移動(胎児期,乳児期,小児期,青年期,成人期と老化)などが概説されている.
第2章 適応的なこころ
第2章では進化心理学,神経科学の基礎が概説される.
適応としての心理メカニズム,進化的適応環境,機能的特化(領域特異性あるいはモジュール)*1,動機づけシステムと情動(主な動機づけシステム,その至近的目標,関連する情動が一覧にされ,かなり詳しく解説されている*2),防衛メカニズムと火災報知器の原理,動機づけと情動の脳活動と脳部位,意思決定とベイズ原理とヒューリスティックス,意思決定におけるトレードオフ,リスク感受性とトレードオフ,自己制御(フィードバック,実行,意思決定との関係),認知(心を持つものに対する心理主義的認知および心の理論と,心を持たないものに対する機械論的認知について詳しく解説される),神経生物学的システム(内分泌,ホルモン,神経伝達物質,自律神経系)などが概説されている.
第3章 個人差と性差
第3章では個人差と性差が概説される.精神病理はある意味個人差を扱っているので「差異の起源と構造」は非常に重要な解説ポイントになる.
<遺伝的多様性,非遺伝的多様性>
- 遺伝子多型が生じるメカニズムとして,突然変異-淘汰バランス,突然変異-浮動バランス,平衡淘汰(超優性,性的拮抗淘汰,頻度依存淘汰)がある.
- 非遺伝的な多型には発達的可塑性(条件付き適応)があり,社会淘汰,性淘汰で生じやすい.また環境変動に対しての両賭け戦略としての多様化も生じうる.
<個人差の心理学的研究>
- 個人差を扱う心理学研究は,パーソナリティを扱う分野と認知能力を扱う分野の2つに大きく分かれている.前者は機能の差,後者は機能性の差と見ることができる.前者の多様性は本質的に戦略的で同一の基盤プロセスの「代替」設定と見ることができる.
<パーソナリティ>
- パーソナリティは動機づけと自己制御の個人差から現れる(いくつかの例が挙げられている).これらのパーソナリティ特性は次元的に捉えられており,「ビッグファイブ」という5因子モデルでよく記述できることが知られている.各因子はさらに下位のファセットに分解でき,動機づけメカニズムや自己制御メカニズムと関連する.ビッグファイブの次元は独立ではなく,2つの高次因子(α(安定性),β(可塑性))が提案されている.
- 進化学者たちはパーソナリティの進化的な説明として,空間的,時間的,頻度依存的な変動淘汰*3を挙げてきた.現状の遺伝相関の知見は変動淘汰(および平衡淘汰)を支持しているが,突然変異-淘汰バランスも働いているだろう.
- パーソナリティ特性は可塑的であり,(条件付き適応として)環境条件により調整されている可能性があるが,この部分についての知見は乏しくよくわかっていない.また別の可能性として寄生体からの操作などもありうる.
- よく議論されている論点には,パーソナリティ特性にかかる淘汰圧が農業革命以降変化したか,自己家畜化が影響しているかがある.
<認知能力>
- 認知能力の個人差は驚くほど単純な形をしていること(正相関性を持ち,gと呼ばれる単一の一般因子でよく説明できる)がわかっている.gはパーソナリティ特性とはあまり相関を持たないが,神経症と弱い負の相関がある.
- ただし認知能力の差をgで完全に記述はできず,その下に特殊因子があると考えられる.そして実際には言語,知覚,心的回転の3因子でほとんど要約できる.
- 認知能力の個人差の遺伝要因は突然変異-淘汰バランスが大きいだろう.近年の知見では一般知能の遺伝的多様性の半分程度が稀な突然変異によるものだとされている.
<性差>
- 性淘汰,社会淘汰により男性と女性は異なる生態学的淘汰圧に晒されていると考えられる.これによりある形質の平均,分散に性差が生じうる.性淘汰圧の強さ,代替配偶戦略の選択肢の多さから男性の方が分散が大きくなると予想され,実際に様々な形質において男性の方が多様である.
- パーソナリティにおいては,神経症傾向と調和性は女性の方が高い.また誠実性と外向性も女性の方がやや高い.このような効果の大きさには文化の違いがあり,男女平等的な社会の方が性差が大きい傾向がある.(動機づけメカニズムの性差についても記述がある)
- 一般知能については性差はないか極めて小さい.分散は男性の方が大きい.下位次元では女性は言語因子において優れ,心的回転因子において劣る(さらに細かく説明がある)
このあと遺伝と環境についての概説がある.遺伝率,遺伝環境交互作用,行動遺伝学的知見,可塑性の個人差,敏感期,発達的スイッチポイントが簡単に解説されている.
第4章 生活史戦略
第4章では生活史理論が紹介される.本書では生活史理論をパーソナリティ,発達,成長に関する多様性を互いに結びつける理論として位置づけている.
生活史理論は基本的にはリソースの配分戦略の問題で,ここでは,基本的なトレードオフ(現在と将来,子孫の質と量,配偶努力と養育努力),重要な環境条件(外因性死亡率,個体群の成長率,資源の利用可能性),性差,制御メカニズム(内分泌系と心理メカニズム)がまず解説される.
そして戦略の多様性の軸として,早い生活史と遅い生活史の軸を据える基本モデルが説明される*4.そしてこの軸に添って様々な形質に相関が見られることが解説されている(この軸と動機づけ,意思決定,自己制御の様々な形質との関連,パーソナリティのビッグファイブモデルへの当てはめ*5,認知能力との間には関連性を期待する理由がないことが整理されている).
続いてこの基本モデルの拡張として,ヒトにおける複雑な社会と名声をめぐる競争,農業革命以降の環境変化を入れ込み,早い生活史戦略の分離可能な区分として「敵意・搾取」戦略,「魅惑・創造」戦略*6,遅い生活史戦略の分離可能な区分として「向社会・養育」戦略*7,「熟達・供給」戦略*8があることが提唱されている.
ここから戦略分布の性差,戦略を方向づける環境要因*9,遺伝要因,遺伝と環境の交互作用,集団差についての考え方が解説されている.
第5章 進化と精神障害
第2部では精神病理学についての統一的な進化的アプローチが展開される.まず第5章で精神障害とは何かが取り扱われる.
- ここでは精神障害について,狭義の精神障害を「有害な機能不全」という危害基準と機能不全の基準を満たすものとして,広義の精神障害を「望ましくない状態」として定義する.
- 広義の障害に対する脆弱性の説明としては,自然淘汰の制約(トレードオフなど),自然淘汰の速度的限界(寄生体の操作,環境変動(進化的ミスマッチ)などに追いつけない),自然淘汰が個体の幸福ではなく遺伝子複製の最大化に向けて進むことがあることが挙げられてきた.また集団レベルで適応的であっても特定の個体には不適応になることもある(クリフエッジ型の適応度関数に由来する場合には重度の障害となりやすい).そして狭義の障害(有害な機能不全)は突然変異荷重,寄生体の操作により生じうる.
- 自然淘汰の制約:条件付き適応は,条件の誤認識,環境変動,不適応的な学習などにより失敗しやすいメカニズムであり,不適応的な帰結に至りやすい.高リスク戦略は(期待値が高いとしても)失敗することもあり,個人レベルでの不適応の帰結をもたらしうる.進化的にコンフリクトがある場合には当事者の少なくとも片方にとって不適応的な帰結をもたらしうる.
- 防衛反応は,利得の偏りから高い偽陽性を受け入れるように調整される(火災報知器の原理)ので,偽陽性による不適切なメカニズム活性化と調節機能不全の境界線が曖昧になる.これは不適切学習によりさらに複雑になる.なお偽陰性が多いような調整不全の場合,本人には苦痛が生じにくいので認識されにくいが,防衛に失敗するという問題が生じうる.
- 適応だが望ましくないもの:防衛メカニズムには強い嫌悪感情を伴うものがある.これは本人にとっては苦痛となる.この場合適応的な防衛状態なのか,機能不全であるのかの見極めは難しい.逆に反社会性パーソナリティ障害のように周りに害を与えるタイプの防衛の場合,適応的かどうかにかかわらず精神障害とみなされるのが通常である.また他の人々の利益のために当人に大きな犠牲を強いる自己犠牲的な帰結をもたらす適応的利他行動調整メカニズムの機能不全もありうる.
ここから精神障害をどう捉えるかの既存のアプローチが扱われる.
- 古典的な精神医学アプローチでは精神障害は質的に異なる離散的なカテゴリーとされ,カテゴリーごとの単一の基礎的な機能不全が一貫した症候群(シンドローム)を引き起こすことが期待されている.これはDSM分類に反映されている.
- ここ数十年でこの考え方の限界が明らかにされてきている.単一病因を探る試みはうまくいかず,これまで単一とされてきたカテゴリーが異質の要因を持つ複数の状態からなることがわかってきた.統計的分類分析は,ほとんどの精神障害は個別のカテゴリーというより正常な分布の極端な例として記述する方がよいことを示している(例外はある).
- そして新しく次元的に捉える見方と,単一の症候群から特定の神経・心理学的メカニズムとその機能不全に焦点を移す動きが生じている.進化的にみると,広義の障害には機能不全から適応的行動戦略まで幅広く含まれることが期待され,すべてが次元的という見方を保証するものではない.一部には不連続的な機能不全もあるだろう.しかしメカニズムの機能と働きの個人差に依存するもの(つまり次元的で連続的なもの)も多く含まれると考えられる.
- 機能不全と症状の併存状況の関係については古典的な単一障害モデル,次元化の見方(RDoCアプローチ)からの特異的機能不全モデル(機能不全ごとに症状群があり,その併存パターンが障害を決める),症状同士が互いに原因や結果をなりうるという見方(ネットワークアプローチ)からの症状ネットワークモデルがある(それぞれ説明がある).これらのアプローチにはそれぞれ長所と短所がある(詳しく説明がある).進化的にみるとすべての精神障害が同じ因果構造を持つと想定する理由はなく,障害ごとに特定機能不全モデルや症状ネットワークモデルが個別に当てはまりうるだろう.
第6章 生活史の枠組みとFSDモデル
第5章で既存のアプローチの限界を議論した後,本章では著者たちが提唱するアプローチモデル(FSDモデル)が解説される.
- 本書では生活史(早い生活史戦略(F型)と遅い生活史戦略(S型))の機能的基準で精神障害の分類を試みる.そして生活史基準に防衛メカニズム活性化障害(D型)という新しいカテゴリーを加えて補完する.これをFSDモデルと呼称する.
- 生活史基準は代替的な生活史戦略の現れとして機能的に理解されうる.そして生活史戦略から精神病理へは複数の経路がある(適応的特性が病理とみなされる,平均的適応形質が個人にとって不適応となる,適応的特性が特定の脆弱性を高めるなど).
- 防衛メカニズム活性化障害は防衛メカニズムが強く活性化して生じる障害で,適応的に有益な場合もそうでない場合もある.
- 生活史基準と防衛メカニズムの関連は,防衛メカニズムの制御が生活史戦略とからみ,両極端で過敏になる理由がある*10ので複雑だ.
ここでFSDモデルによる分類体系,併存症パターンの概要が解説され,その後,早い生活史スペクトラム障害(F型),遅い生活史スペクトラム障害(S型),防衛メカニズム活性化障害(D型),それぞれの構成する障害,指標,性差,発達パターン,リスク要因が詳しく解説されている.F型の典型的障害は反社会性パーソナリティ障害,統合失調症など,S型の典型的障害は自閉スペクトラム症,強迫性パーソナリティ障害など,D型の典型的障害は抑うつ障害,不安症,PTSD,恐怖症,パニック症などが挙げられている.障害にはFSDの2つ以上のサブタイプに分かれるものがあることも示されている.
さらにFSDモデルの特徴が議論されている.
- FSDモデルの興味深い特徴は,逆境への暴露と(苦痛,痛みへの反応性などの)心理的帰結のJ字型の関連性という不可解な実証的知見を説明できることだ.逆境がほとんどないとS型障害リスクが生じ,逆境が強いとF型障害リスクに加えて強いD型障害リスクが生じるとして説明できる.そしてこれは適度なレベルの逆境経験がレジリエンスの向上などの「予防接種」的な働きを持つと考えることもできる.
- FSDモデルは基本的に戦略の多様性を強調するが,認知能力も重要な要因として扱う.まず突然変異荷重は精神障害リスクの要因となる.認知能力が低いと防衛能力も低くなり,様々なリスクに晒されやすくなり,防衛メカニズム活性化障害リスクを高める.また適応的な学習効率も下がり,反社会的戦略の要因となりうる.
またここではFSDモデルと診断横断的モデルの差異についても細かく議論されている.
第3部 一般的な精神障害
第3部は各論になり,様々な精神障害ごとに障害の概要(症状,遺伝,発達,リスク要因など),進化モデル,FSD分類(何型か,メカニズム的考察)がまとめられている.ここでは特に進化モデルの記述を中心に紹介したい.
第7章 反社会的障害と素行症
- この障害は反抗や攻撃などの外在化スペクトラムの要素に関するクラスターを形成する.典型的な発達コースにはいくつかのパターンが報告されている.
- 進化学者は攻撃性,反社会的行動をハイリスク戦略と考えてきた.進化精神病理学では反社会的障害は潜在的適応的戦略とみなされる.そしてこれを「裏切り者」戦略とする主張,早い生活史戦略の現れとする主張がある.
- サイコパスについては「欺瞞と操作に基づいた低頻度の裏切り者戦略」であるという仮説が有力だ.そして農業革命以降,都市と匿名の群集が現れ,適応的頻度が上昇したという考え,遺伝的な頻度依存淘汰と条件付き適応の2つの経路があるという考えが議論されている.経済ゲームを用いて中程度のサイコパスが広範な条件下で適応的であるという主張もなされている.
- FSDモデル的には反社会特性は早い生活史戦略の行動要素と考えられる.これは裏切り者戦略と排他的な説明ではない.生活史的観点は遺伝子の頻度依存淘汰の範囲を拡大する補完説明となる.また発達経路タイプの違いを生活史戦略の違いとして解釈する主張もなされている.
- これらの適応的な説明に対しては,発達的撹乱や有害突然変異の蓄積の要素もあるのではないか,クリフエッジ型の不適応なケースもあるのではないかという議論がある.また早期発症型がうまく説明できないという問題*11もある.現代社会においては進化的ミスマッチの要素もある可能性がある.
第8章 統合失調症スペクトラム
- 精神病性スペクトラムには統合失調性スペクトラム障害(SSD)と双極性障害(BD)の2つのクラスターが認められてきたが,明快な境界はなく,最新のDSMでも合成カテゴリーが作られている.精神病性スペクトラムには明確な機能性の勾配がある.
- 統合失調症スペクトラムにはパーソナリティの正常範囲内から重篤な状態までの広がりがある.パーソナリティには陽性,陰性,解体性の3側面が認められている.
- 統合失調症は遺伝的な要素が強く有病率(1%)も比較的高いが個人的には明らかに不適応(生涯繁殖成功で女性が一般人の50%,男性が20%程度とされる)であり,進化的なパラドクスだ.これを説明するための仮説としては副産物説と発症しない場合に有利であるとする説(適応的性質としての傾性説)が唱えられている.
- 副産物説は,卓越した認知能力を得たことにより脆弱性がもたらされたというもので,さらにその詳細について特に社会脳を強調するもの,その際にクリフエッジ型適応地形を強調するものなどいくつもの説が唱えられている.
- 適応的特性としての傾性説は,精神病をもたらす素因は適応的に有利であり,発症した時のデメリットを相殺しているとするものだ.これには超優性を用いる平衡多型モデル,カリスマ性のリーダーとなれるメリットを強調するもの,特に陽性統合失調型パーソナリティが異性に魅力的であるという性淘汰モデル*12などがある.
- クレプシとバドコックは自閉症と精神病の統合的モデル(相反モデル)を提案している.それは心理主義的認知(メンタライジング含む)と機械論的認知の連続体から個人差を捉え,SSDにおいては過剰にメンタライジングが機能していると考えるものだ.またこれは遺伝的にはゲノミックインプリンティングがからむことを示唆している.
- この相反モデルには批判もあり,論争が続いている.統合失調症について性淘汰モデルを採るなら,統合失調症は短期的配偶戦略,自閉症は長期的配偶戦略の側面を示しているとも考えられる.*13
- FSDモデル的には陽性統合失調性パーソナリティは早い生活史戦略に大枠で一致する.そういう意味でSSDは魅惑・創造的プロフィールと関連のあるF型障害に分類できよう.
第9章 双極スペクトラム
- 双極性障害(BD)の中核症状は躁病だ.実証研究によると障害には複数のタイプがある.
- 双極スペクトラムについての進化的観点からの研究は少ない.ほとんどのモデルが軽躁病特性に適応上の利益を仮定している.
- 躁状態と鬱状態が支配システムの勝ち負けプログラム(支配行動と敗北行動)に対応しているという考えは多くの研究者が提唱している*14.
- シャーマンは最終氷期の長く厳しい冬と短い夏の気候パターンへの適応が現代環境でミスマッチになったとして双極スペクトラムを説明する仮説を提唱した.このモデルは推測によるところが大きく,双極性障害の重要な特徴が説明できていない.
- 双極性障害は複数の機能的サブタイプを含んでいる可能性が高い.軽躁病特性は早い生活史特性と関連しており,FSD的にみて双極性障害が基本的にF型であることを示唆している.しかし割合は少ないが,自閉症との併存がみられるS型のサブタイプもあると考えられる.
第10章 自閉症スペクトラム
- 自閉症は連続的に分布している認知行動特性の極端な発現として考えることができる.自閉症スペクトラム障害(ASD)では社会性の障害,コミュニケーションの障害,時局的反復的行動という3種類の症状群があり,(古典的には単一症状群とされているが)遺伝的にも表現型的にも互いに弱い相関しかなく,多様な症状の組み合わせがある.性差は男性に大きく傾いている(ASD全体で4:1,高機能症例では10:1).
- 自閉症の認知基盤について様々な理論が提唱されている.具体的には弱い中枢性統合モデル(局所的情報処理へのバイアス),高いシステム化と低い共感化モデル(極端な男性脳),亢進した知覚機能モデル(低いレベルの知覚情報処理機能向上),インテンス・ワールド理論(局所的な神経回路における過剰な反応性と過剰な可塑性,および遠くの脳領域間接続の減衰),計算論ベイズアプローチ(情報処理において事前確率を軽視するバイアス)などがある.
- バロン=コーエンは自閉症様特性がヒト進化の中で道具製作などの特殊なニッチで淘汰を受けた適応的なスキルだと推測した.クレプシは長期化した脳発達に伴う副産物の可能性を模索した.
- 最近では遅い生活史戦略における男性に典型的な特徴だとして生活史の観点から捉えられるようになってきている.その嚆矢となったのは第7章で触れた精神病と自閉症の相反モデル(自閉症を機械論認知が向上し,心理主義的認知が低下した状態だと考える)だ.これは特に高機能自閉症の特徴をよく説明する.
- 自閉症様特性は,熟達・供給的プロフィールと関連する遅い生活史戦略(配偶努力を下げて養育投資を促進する)の男性に典型的なバリアントと考えられる.この養育投資促進の観点は父親由来インプリンティング遺伝子が自閉症リスクを上げるという知見と整合的だ*15.これは自閉症がすべて適応的と考えているのではなく,不適応症例が潜在的適応形質の過剰発現や質的な機能不全による可能性を認めるものになる.
- 自閉症の中の高機能タイプは遅い生活史戦略からよく説明できる(S型).知的障害を伴う重度自閉症は新奇突然変異や染色体異常と関連し,FSDモデルの外側にO型として暫定的に位置づけておくのが適切だと思われる.
第11章 注意欠如・多動症(ADHD)
- ADHDは多動性,衝動性と不注意を特徴とする障害の診断名になる.この2つの症状には中程度の相関があり,一般人口内に連続的に分布している.ADHDは知能の低さと深く関連しており*16,全般的な認知障害から生まれると仮定するのが妥当だろう.
- ADHDは遺伝性が高く(遺伝率70~80%),母方からより強く伝達されるエビデンスがあり,母由来のインプリンティング遺伝子の関与の可能性がある.性差は男性に傾いている(2:1).
- ADHDは自閉症スペクトラム,精神病スペクトラムと複雑な重複を示し,いくつかのサブタイプの存在を示唆している.
- 進化的には多くの推測的な仮説があるが実証研究はほとんどない.
- ハートマンはADHDは狩猟文化の中で迅速な警戒,探索,興奮希求という特性を進化させたものであり,現代環境化でミスマッチになっていると主張している.しかしADHDはしばしばリスクを無視するし,狩猟には忍耐が必要だという知見とも矛盾する.*17
- ベアードは,ADHDは単に注意機能や自己制御メカニズムの有害な機能不全だと主張した.これは興味深いが実証研究はない.
- ADHDの特徴をすべて説明できる単一の仮説がないのは,ADHDカテゴリーが内部に著しい異質性を持つからだろう.
- ADHDの大多数は精神病,反社会性障害と重複する早い生活史スペクトラム(F型)と考える充分な理由がある.この他に一般知能の低さと広範な実行機能障害を持つサブタイプがあり,これは有害突然変異などと関連する暫定的なO型と考えておくべきだろう.さらにASD,強迫性パーソナリティと重複する稀なサブタイプがあり,これは遅い生活史スペクトラム(S型)と考えられる.
第12章 パーソナリティ障害
- パーソナリティ障害とは,広範で持続的な,柔軟性のない非機能的な行動パターンとして定義され,その極端な形の病的な形態と結びつきうるものだ.その分類は難しく論争の元となってきた.代替DSM-5では統合失調性(SPD),反社会性(ASPD),境界性(BPD),自己愛性(NPD),回避性(APD),強迫性(OCPD)の6つの類型を識別している.しかし多くの障害は次元モデルの方が当てはまりがよく,安定性にも疑問がある.ここではその点に留意しつつ,境界性(BPD),自己愛性(NPD),強迫性(OCPD),回避性(APD)の4類型について考えていく.
境界性パーソナリティ障害(BPD)
- BPDの特徴は感情,対人関係,自己イメージの持続的で著しい不安定さだ.多くの症状はアタッチメントなどの動機づけシステム中心に展開し,極端に高い不安と回避が併存している.
- マクガイアとトロイシはBPD(およびその他のパーソナリティ障害)は適応的な行動戦略を実行しようとする試みの失敗として理解されうると主張した.これはBPDの低知能との相関と整合的な説明だ.
- ブルーネはBPDをリスクテイキングや短期的配偶と関連する早い生活史戦略の不適応的な極端さの反映だと議論した.ブルーネはBPDは不適応的だが,そこまで至らない境界性特性は搾取的な文脈で適応的である可能性を論じている.
- BPDが適応的な不適応的かという問題は未解決だ.
- FSD的には基本的に早い生活史戦略(F型)と考えられるが,魅惑・創造的特性と敵意・搾取的特性とともに関連しており,やや不可解な側面を持つ.
自己愛性パーソナリティ障害(NPD)
- NPDの特徴は極端な自己愛とされる.大規模研究で3つのサブタイプ(誇大・有害型,高機能・顕示型,脆弱型)があるとされている.動機づけにおいて過活性化された地位システムが主要な役割を果たしている.
- 進化学者たちはNPDにあまり注目してこなかった.最近ではダークトライアドの他の特性をまとめて一貫して早い生活史戦略と結びつけられて論じられている.
- FSD的には早い生活史戦略(F型)と考えられる
強迫性パーソナリティ障害(OCPD)
- OCPDは秩序正しさ,完全主義,自己制御の広範なパターンとされる.動機づけシステムにおいては嫌悪感受性との関連が高い.
- ハートラーは更新世の人類の放散により寒冷地域に定住するようになったあとの気候ストレッサーに対する適応的な戦略(持続的生存に対する準備のための過度の誠実性)としてOCPDが進化してきた可能性を指摘した.ハートラーはこれが現代社会とのミスマッチになっていると考えているが,特定のニッチでは現代においても適応的である可能性がある(高い収入,関係安定性の高さと関連している).
- FSD的にはOCPDは極端な誠実性の特徴に伴う遅い生活史戦略(S型)の現れと考えられる.
回避性パーソナリティ(APD)
- APDは社会的抑制,強い不全感を伴う低い自尊心,否定的評価に対する過敏性の広範なパターンとされる.
- 社交不安は地位競争の敗北に対する行動的防衛としての役割を持つと考えられる.APDに対する進化的考察はあまりなされていないが,社交不安症への考察がほぼそのまま当てはまるだろう.
- FSD的には恐怖クラスターの防衛メカニズム活性化障害(D型)と考えられる.
第13章 摂食障害(ED)
- EDの中で重要なのは拒食症(AN)と過食症(BN)だ.ANは体重増加に対する激しい恐怖と身体イメージの乱れを伴うエネルギー摂取制限と体重低下が主な症状になる(DSMではANの中に過食排出型と摂食制限型のサブタイプを認めている).BNはコントロールの喪失感を伴う過食の繰り返しと自己誘発嘔吐などの代償行動で定義される.ANとBNはともに女性に典型的な症状で,性比は1:10以下だ.
- ANとBN,およびANのDSMサブタイプは通常別の障害と扱われるが,リサーチは異なる症状の組み合わせが安定した基底的疾患に対応しないことを示している.カテゴリー間で診断が移り変わり,ある程度の進行モデルもある.全体としての分布は次元モデルに適合し,自己飢餓サイクルと過食・排出サイクルの2つの自己強化サイクルから分析できると考えられる.
- パーソナリティと依存症のプロフィールの視点からはEDに高機能型,過剰制御型,制御不足型の3つのサブタイプが認められる.
- 女性患者の繁殖成功の低下はデータから明らかであり,進化的にみて非適応状態と考えられる.現在の進化学者たちは,EDを進化的ミスマッチか,摂食と飢餓の調整メカニズムの機能不全のどちらかであると考えている.
- ANにおいてはエネルギー制限下における過剰な運動と激しい自己抑制下における一時的な衝動性がみられる.運動の亢進は個人の採餌範囲を広げるため,衝動性は小さな即時報酬を高く評価するという意味で適応的な性質を持つ.これらの調整メカニズムの機能不全がANを引き起こすという指摘がある.ただし,これだけでは自己飢餓サイクルの開始動機や女性に偏った性比を説明できない*18.
- 繁殖抑制モデルはストレス下で妊孕力を調整するようにデザインされた適応メカニズムの機能不全と考えるものだ.これはもっともらしいが,実証的なデータの裏付けはない.このモデルは同性間の競争がEDの引き金になること,都会の社会経済的地位の高い女性の発症率が高いことは説明できないが.特定タイプのEDを説明できる可能性がある.
- 性的競争モデルは身体的魅力に関する競争の激化に対する不適応反応とみなすものだ.女性の体型が男性の配偶選考の対象であるという事実があり,現代環境で女性から知覚される競争状況が激化しているために性的競争プロセスが暴走した状態だと考える.このモデルは都市生活がEDリスクを高めていること,性的競争の激しさがEDと関連することなどをうまく説明できる.ただし,一部のEDは性的魅力というより,道徳的精神的な懸念により動機付けられていること(女性間の地位をめぐる競争を示唆している)を説明できない.
- FSD的には,EDのパーソナリティからみたサブタイプのうち,制御不足型は早い生活史戦略(短期的配偶をめぐる同性間競争)(F型)と,高機能型と過剰制御型は遅い生活史戦略(長期的パートナーをめぐる同性間競争)(S型)と分類される.後者の2つのサブタイプは地位競争的なパターンと関連する.
第14章 抑うつ
- 抑うつ障害群は重度で長期的な落胆気分,興味や喜びの喪失を特徴とする.またストレス反応システムの活性化と関連する食欲,睡眠,性欲,覚醒にかかる身体症状も呈する.認知的には自尊心の低さ,ネガティブな価値観,将来への悲観が特徴になる.ネガティブな認知バイアスについて,脅威と報酬に対する反応を決定する閾値の調整としてベイズ的に考察する計算論的モデルが提唱されている.
- 進化的にみて抑うつ症状が防衛機能を果たすことにほとんど疑いはない.しかし何に対しての防衛かを正確に定義することは困難であり,様々な仮説が提唱されてきた.進化モデルは大きくわけて,不確実な報酬や脅威に直面した時の一般的な意思決定戦略として考えるものと,社会的脅威に焦点を絞り,服従とリスク回避の関連性を強調しているものがある.また一部の論者は重度の抑うつまで適応的だと主張している.うつ病は死亡率や健康・社会的コストと関連しているにもかかわらず,繁殖成功が一般集団と比べて大きく下がらないこと(男性で90%,女性はほぼ100%)は注目される.
- 一般的意思決定モデル:ネシーはこのモデルを詳細に論じ,抑うつ気分は達成不可能な目標からの撤退という意味で適応的であり,より一般的には期待される報酬期待値が低すぎる時にエネルギーと資源を節約するのだと主張した.ネトルとベイトソンは2つの独立した意思決定における閾値(罰に関するものと報酬に関するもの)に基づく2次元モデル(罰の閾値が低いと不安と警戒心が生じ,報酬の閾値が高いと悲観主義や疲労を特徴とする抑うつ状態となる)を提唱している.これらのモデルは有用な洞察を提供してくれるが,それらはかなり抽象的で臨床的な実像とは間接的にしか結びつかない.
- 社会的競争モデル:プライスやギルバートによる社会的競争モデルは,抑うつ気分を個人の社会的地位が低下していると知覚された場合の適応的反応だとする.これは抑うつ気分を敗北や排斥の後に伴う不本意な従属を生じさせる防衛メカニズム(新しい地位への順応,あるいは競争からの自動的段階的撤退戦略)と考えるものになる.そして進化ミスマッチが競争の側面を悪化させている可能性も示唆する.抑うつ症状と知覚された低い地位との関連についてはかなりのエビデンスがあり,抑うつと社交不安症の強い併存もうまく説明できる.ただし,自殺願望はうまく説明できず,身体症状の役割も不明という問題もある.
- 社会的リスク仮説:アレンとバドコックは,社会的に特に重要な関係から排除されることのリスク認知が抑うつ気分の引き金になるという考えを中心にこれまでのモデルを統合化した.リスクにはアタッチメント,親和,地位,権力などの様々な領域に及ぶとされている.この仮説は抑うつの機能をリスク回避を促進するものと捉える.バドコックはこれをベイズ計算論的にモデル化している.この仮説はこれまでのモデルによる示唆を完結に要約しているが,リスク回避ですべてを説明できるかどうかは明らかではないし,自殺願望はやはりうまく説明できない.また抑うつ患者が経済ゲームで協調的に振る舞わない傾向があることも説明できない.
- 駆け引き戦略仮説:ハーゲンは,抑うつを,集団の他の構成員とのコンフリクトで協力の選択肢が有効でなくなった時の最後の駆け引き戦略(協力が不可能と認知され,大きな罰を受けずに裏切り(撤退)が可能になる一種のストライキ戦略)として適応的だと主張している.この駆け引き仮説によると,自殺願望(自殺リスク)はシグナルの信憑性を高めるためのコストとして説明可能になる.
- 社会的ナビゲーション仮説:ワトソンとアンドリューズは,複雑な社会関係の中で,ある社会的関係から別の社会的関係へ優先度を振り替えるどうかが問題になった場合に,抑うつは,認知資源を熟慮・反芻に割り当てるとともに,他者に援助・支援・譲歩を強いる受動的戦略として機能すると提唱した.これは自殺願望や経済ゲームでの振る舞いを説明できる興味深い仮説だが説得力のある証拠は少ない(産後うつに関しては周囲からの援助を増やせるというエビデンスがある).また軽度のうつが駆け引きツールとして役立つのかという疑問もある.
- 分析的反芻仮説:アンドリューズとトムソンは社会的ナビゲーション仮説を元に,抑うつ的反芻の適応的モデルを構築した.これは(抑うつによる)反芻的な思考スタイルを適応度的に重要で複雑な問題を分析するために特別にデザインされた適応的メカニズムだと考えるものだ.ただし抑うつ的反芻が現実世界の状況で体系的に有益であることを示すエビデンスは得られていない.
- 病原体からの防衛仮説:抑うつは免疫系に資源を優先的に割り当てる適応的な防衛として進化したが,現代の衛生環境でミスマッチになったという主張もある.抑うつと免疫の関係は明らかに重要だが,その生理的な詳細は明らかではなく,精神病理学にとっての意味も明らかではない.
- FSD的には,これらすべてのモデルが抑うつが防衛的(D型)であるということで一致している.ただその中で早い生活史型(自殺願望の強い衝動的なタイプ)と遅い生活史型のサブタイプがある可能性がある(複雑で一貫性のないセロトニンの役割を説明できる可能性がある).
第15章 全般不安症(GAD)
- GADは過剰でコントロールできない不安や心配を抱く慢性的な状態と定義される.患者は恐怖を感じる出来事が生じる可能性及びその結果の大きさを体系的に過大評価する.
- 心配や不安は明らかに防衛的な機能を持っている.ベイトソンはGADを脅威や危険に対する低い検出閾値が一般化した状態だと考えた.これは脆弱性が高い人においては適応的なのかもしれない.
- FSD的には防衛メカニズム活性化の典型的な障害(D型)だと考えられる.ただ心配は未来志向的な性質を持つので遅い生活史戦略と機能的に関連する可能性がある.
第16章 心的外傷後ストレス障害(PTSD)
- PTSDはトラウマ的な出来事を経験した後に生じる深刻で長期にわたる反応(反復的な夢,不随意的な記憶,フラッシュバック,トラウマ的状況からの持続的回避,過度の警戒心,激しい怒りを伴ういらだたしさ,睡眠障害,過剰な驚愕反応,トラウマの一部の側面の想起不能,過剰に否定的な信念,感情麻痺など)を指す.
- PTSDと他の精神病理の併存率は著しく高い.
- 精神病理の度合いの低い「シンプル」なサブタイプ,度合いが高いものについて反社会性,薬物使用,抑うつなどとの関連に基づいて「内在的」サブタイプ,「外在的」サブタイプがあるとされている.
- PTSDという概念の妥当性について科学的,政治的,倫理的な論争がある.これまでのリサーチによると少なくとも「特定のトラウマ的出来事」を強調するのは適切ではなく,より広いストレッサーに起因しうることがわかってきている.
- カンターはPTSDについて警戒防衛モデルを提示し,捕食者や同種個体からの脅威に対する適応的な防衛メカニズムの現れだと論じた.症状は様々な防衛反応と一般化された過警戒から説明でき,ネットワーク分析では過警戒が症状の中心だと考えられる.また防衛的宥和が複雑性PTSD(ストックホルム症候群などを含む)を説明できる可能性があることも注目される.
- PTSDは,早い生活史スペクトラム障害との併存が(遅い生活史スペクトラム障害との併存よりも)多い.重度のトラウマが早い戦略(F型)への急速な移行を引き起こす可能性が指摘されている.
第17章 限局性恐怖症
- 限局性恐怖症は特定対象への恐怖や不安が重大な苦痛や日常生活の支障をもたらすほと持続的で過酷なものとされる.多くは安全システムと恐怖システムが活性化されるが,(虫やネズミなどに対する恐怖により)回避や嫌悪が活性化されるタイプ,(血液・注射・負傷(BII)に対する恐怖により)自律神経反応を示すようなタイプもある.
- 恐怖は進化環境で危険をもたらす原因となった対象や状況と関連している.そしてより危険な対象をより怖がるような傾向(強く水路づけられた条件づけ)が進化したことが考えられ,このような傾向は現代環境とのミスマッチでより強化される可能性が高い.
- 準備性モデル:オーマンとミネカは選択性や自動性やカプセル化という特徴を持つ進化した恐怖モジュールがあると主張している.これは一旦対象との間に選択的連合が形成されたら(対象と何らかの危険の兆候の関連が学習される必要があると考える),その後は自動的に恐怖が生じるようになり,意識的なコントロールを介入させないと想定することで,表面上不合理で制御不能な恐怖症の性質を説明する.この準備性モデルの予測は実証研究で一貫して支持されているが,カプセル化の概念が硬直的だという批判もある.
- 非連合モデル:準備性モデルと異なり,(対象と出くわすだけでよく)厳密な意味の学習を必要としない(通常はその後に安全と学習することにより恐怖が治まる)と主張する研究者もいる.この見解によると恐怖症は恐怖消去の失敗と捉えることになる.準備性モデルは実験結果において支持されているが,恐怖症患者による自伝的な報告は(準備性モデルより)非連合モデルの方が当てはまりがよい.おそらく両方の過程が関与しているのだろう.
- これらの見解にはいくつか批判がある.クモ恐怖症については,クモの大半は危険ではなく,虫やネズミに対する嫌悪の一種として感染症防御として進化したのではないかという議論がある.
- またBII恐怖症の自律神経系の反応も準備性モデルや非連合モデルで上手く説明できない.BII恐怖症の血管迷走神経性失神がなぜ生じるのかはよくわかっていない.大量失血への予期反応とする説もあるが,失神のデメリットを上回るかは不明だ.
- 系統種間比較によるリサーチは,霊長類がヘビを素早く検知するのに特化したメカニズムを共通に持つことを示唆している.ヘビ恐怖症の基盤は他の一般的恐怖とは重要な点で異なっている可能性がある.
- 今後の展望としては,ベイズモデリングによる準備性モデルと非連合モデルの統合方向,恐怖症のサブタイプの存在の可能性の検討が望まれる.
- FSD的には限局性恐怖症は防衛メカニズム活性化障害(D型)と考えられる.
第18章 パニックおよび広場恐怖症
- パニック発作は自律神経活動の亢進とともに恐怖と苦痛の急速な高まりが生じる劇的エピソードだ.心拍数の増加,動悸,発汗などの身体症状に差し迫った危機感と圧倒的な逃亡衝動が伴う.再発を繰り返す慢性状態はパニック症と呼ばれる.
- 広場恐怖症は開放空間や閉塞空間に対する持続的な恐怖,不安によって定義される.パニック症患者はしばしば二次的反応として広場恐怖症を発症する.これはパニック発作を起こした時に逃げるのが難しいという不安と関連している.
- パニック症に至らない通常のパニックは進化的防衛反応であり,闘争・逃走反応の構成要素であると考えられる.動機づけからみると恐怖システムの作動モードの1つであり,パニック症は極端な逃走反応であるといえる.パニック症自体は明らかに不適応状態だが,おそらくパニックと機能的な連続性の上にあり,過敏な警報システムの誤報と捉えられる.
- ネシーは広場恐怖症について,ヒトの防衛システムは安全な避難が保証されない開放空間や閉鎖空間に特に敏感になるように進化したと推測している.ブラチャは進化環境では樹木が避難場所の候補であり,患者は樹木のない風景に特に敏感なはずだと議論している.
- FSD的にはパニック症と広場症候群は防衛メカニズム活性化障害(D型)と考えられる.
第19章 社交不安症(SAD)
- SADの特徴は他者の注視を浴びるような社会的状況に対する持続的恐怖および不安だ.動機づけの特徴は,地位やアタッチメントに関する目標が失敗したと知覚されることになる.
- 進化的には社交不安は地位と承認をめぐる競争を結びついていると考えられる.社交不安行動は地位の更なる喪失や排除を防ぐためのリスク回避戦略と捉えられる.これは抑うつの社会的競争モデルと同じ概念的枠組みになり,実際に抑うつとSADは高い割合で併存する.
- ほとんどの進化学者は軽度の社交不安は適応的だと考えており,SADの弊害について現代社会におけるミスマッチと捉えている.
- FSD的にはSADは恐怖クラスターに属する防衛メカニズム活性化障害(D型)と考えられる.
第20章 強迫症(OCD)
- OCD患者は自身の思考や行動を制御できない苦痛を経験する.侵入的,持続的,反復的な思考やイメージが生じてしまい(強迫観念),それが強迫行為を引き起こす.これには4つの次元(汚染,タブー,対称性,ため込み)があるとされている.
- OCDのサブタイプとしては,自発性と反応性の分類,特徴的なサブタイプとしての(主に対称性にかかる)しっくりこない感覚を伴うもの,重度のため込み症の区別が提案されている.
- 進化的にはOCDは何らかの認知心理的メカニズムの機能不全と捉えられる*19.
- 危害防止モデル:初期の理論は洗顔や確認の強迫行為について一種の心理的免疫メカニズムの機能不全と捉え,メタ認知過程の重要性,潜在的脅威に対応する動機づけシステムのロジック(火災報知器の原理)が指摘された.
- これらを受けてゼクマンとウッディは強迫症を「停止の病理」と捉えた.システムの活性化は正常だが,内部からの目標達成知覚から生み出される停止信号が減衰,欠如した状態だと考えるのだ.これは拡張されて儀式化された行動の一般理論も提唱されている.(統合モデルの詳しい説明が図示されている)
- FSD的には強迫症は防衛メカニズム活性化障害(D型)と考えられる.ただしっくりこない感覚から生じる強迫症サブタイプについては自閉症パーソナリティとの併存,完全主義の高さから遅い生活史(S型)と考えられる.
第4部 まとめ
第4部は第21章のみで,この研究分野の現状と将来の展望についての著者の考えが述べられている.
第21章 将来への展望
- 進化精神病理学はおおむね進化医学の基本原則に基づいており,様々な進化モデルを提示してきた.
- 最先端の知見は障害ごとに異なっている.OCDの危害防止モデルや自閉症と精神病の相反モデルなどは理論的に洗練され実証的に支持されたモデルになっており,至近的分析レベルへの橋渡しをしている.ADHDや限局性恐怖症のように予備的な仮説しかないものもある.抑うつの研究は,競合モデルが多数あり,コンセンサスや理論的統合がなく,この分野のダイナミズムと断片化された様子をよく示している.
- 生活史の枠組み,FSDモデルは精神病理学の分類に概念的一貫性をもたらしており,この分野をさらに発展させる基礎となるだろう.
- そしてここでは3つの更なる発展のためのトピックを検討する.
- 至近的メカニズム:現状において進化精神病理学はメカニズムにはあまり踏み込まず,計算論的精神医学は進化論的アイデアをほとんど取り込んでいない.進化的アプローチは計算精神医学のモデリングに重要な貢献ができるはずだし,情報処理メカニズムを詳細に検討することで進化的な理論を方向づけることができるだろう.分子的な基盤まで解明できれば現状の神経伝達物質などの実証データが断片的で矛盾している状況を改善することができるだろう.エピジェネティックな要因も今後の解明が期待される.
- 疫学:有病率,リスク要因などの疫学的なデータを検討することで,特定の疾患に関する競合した進化モデルを間接的に検証することができる.FSDモデルを動機づけシステムの様相を取り込んだ詳細なものにしたり,環境要因をより詳しく特定したりすることによりさらに検証の精度は上がるだろう.また進化ダイナミクスを考慮した集団間差を扱う深層疫学の試み*20にも期待できる.
- 発達:この分野は初期に発達システム論*21を取り込んだため,進化心理学との統合が数十年も遅れてしまった.発達システム論の呪縛から解放されれば進化精神病理学は発達学者からの貢献により多大な利益を得ることができるだろう.特に発達的可塑性とライフステージ間の移行の研究は重要だ.最近ではベイズ的なアプローチで敏感期の進化,発達軌跡,可塑性の多様性を捉える研究が数多くなされている.
- 進化精神病理学の将来は刺激的な機会に満ちている.最も重要なのは理論的統合だろう.
以上が本書の概要になる.様々な精神障害についてできるだけ統一的な枠組みから理解分類しようという意欲的な試みが本書の中心となっており,様々な研究者の見解が幅広く紹介されているのが特徴になる.
概念的枠組みとしては,精神病理を(1)個人差を生み出す条件付き戦略としての早い生活史戦略と遅い生活史戦略の軸,(2)心理的防衛メカニズム活性化障害(特に火災報知器原理によりフォルスアラームが出やすい)を特に重視して分類し,現代環境とのミスマッチ,トレードオフ,突然変異荷重や寄生体操作によるメカニズム機能不全などの説明はそれぞれの分類の中で補完的な説明として扱うというスタンスをとっている.やや強引で収まりの悪いような障害もあるような印象だが,分類・統合の試みの第一歩としてこういう形になっているのだろう.
進化仮説については様々な仮説が広く紹介されており,障害ごとのその進展や議論の深さが興味深い.(特に深い分野としては,抑うつがあり,そして統合失調症,自閉症,摂食障害も議論が盛んな分野となる)また上記要約からは省いたが,至近的メカニズム,発達過程,リスク要因なども障害ごとに整理して示してくれているのもありがたいところだ.
進化精神医学(Evolutionary Psychiatry),進化精神病理学(Evolutionary Psychopathology)について日本語で読める本としては,ネシーのものが現時点で最も深くて面白いと思うが,本書はより広い視野から総説的な解説が読める貴重な本ということになるだろう.この分野に興味のある人にとっては大変素晴らしい邦訳だと思う.
関連書籍
原書
ネシーの進化精神医学本.私の訳書情報は
https://shorebird.hatenablog.com/entry/2021/09/16/103003
同原書.私の書評はhttps://shorebird.hatenablog.com/entry/2019/06/16/083813
この分野の初期の代表的な著作
最近はこういう本も出ているようだ