
Ten Thousand Birds: Ornithology since Darwin
- 作者: Tim Birkhead,Jo Wimpenny,Bob Montgomerie
- 出版社/メーカー: Princeton University Press
- 発売日: 2014/03/01
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログ (4件) を見る
本書は行動生態学者のティム・バークヘッド,若手リサーチャーのジョー・ウィンペニー,さらにやはり行動生態学者のボブ・モンゴメリーによるダーウィン以降の鳥類学の歴史を語った本だ.バークヘッドは少し前に「The Wisdom of Birds」というやはり鳥類学の歴史を扱った本を書いている.こちらはアリストテレスまでさかのぼって,鳥に関する謎がどう考えられてきて,それが現代科学でどう解決したかについて書かれている本だ*1.おそらくこの前著を書いているうちに,より詳しい現代鳥類学史を書きたくなったのだろう.本書では,分野ごとに,それをリードしてきたリサーチャーの伝記的な要素も加えながら記述されている.また各章の扉にはそのテーマにふさわしい鳥の図が,章末には著名な鳥類学者の自伝エッセイがコラムとして掲載され,本文の中にも美しい鳥の写真が満載されている,全524ページ,本文429ページというゴージャスな本に仕上がっている.また充実したコンパニオンサイト http://myriadbirds.com も公開されている.なお私はこれをKindle版で楽しんだ.こんな大部な本だが,どこにでも持っていって気軽に読み続けられる.そして美しいイラストはデスクトップの大画面で色鮮やかに楽しめる.その上タップ辞書付きだ.これほど電子書籍のありがたみを感じたことはない.
序言において,鳥類は動物学の発展においてそのほかのどんな動物群よりも重要だったと強調されている.昼行性で観察しやすいことが大きかったのだろう.そしてこれまで鳥類学史はいくつも書かれているが20世紀以降を扱ったものが少ないことを指摘して,本書をそれを埋めるものだと位置づけている.
ダーウィン以前の鳥類学は分類と野外観察の記述が中心だったが,ダーウィン以降適応の視点が加わる.そしてダーウィン自身鳥類を題材として多く扱っており,彼を本書のスターティングポイントとするとしている.
第1章は「昨日の鳥」と題し,鳥類の起源学史を扱っている.扉絵はもちろん始祖鳥だ.本章のヒーローはデイノニクスを発掘し,新しい恐竜像を世に送ったオストロムになる.有名なコープとマーシュの発掘合戦も紹介しながら,シンプソンに師事したオストロムの研究歴を紹介し,そして始祖鳥の発掘へと話はさかのぼる.
始祖鳥化石はダーウィンのOrigin刊行の2年後に発見される.ダーウィン学説を快く思っていなかったオーウェンはそれを単なる鳥だと同定した.オーウェンを敵視していたハクスレーはオーウェンの骨の同定の誤りを暴いた後それは爬虫類と鳥類の中間形態だとした*2.その後50年ほど,古鳥類の化石はヘスペロルニス,イクチオルニスなどごくわずかの骨の断片が見つかっただけだった.
1926年ヘイルマン*3は鳥類の起源について初めて正面から議論し,ワニに近縁の偽鰐類が起源グループであり,恐竜と翼竜は別のオルニトスクス類から起源したと主張した.これは特に間違いだとする根拠もなかったため広く受け入れられた.(ハクスレーがコンプソグナトゥスを引き合いに出して恐竜起源を主張していたとされることもあるが,本書ではそれは複雑でわかりにくく,はっきりした主張ではなかったとされている)
そしてデイノニクスを発掘したオストロムは,ヘイルマンが間違っていることに気づき,鳥類と獣脚類の近縁性を確信した.オストロムは分岐分類学の立場に立ち,鳥は恐竜の一種なのだ*4と主張した.これはより正式な分岐学の専門家ゴチエにより裏付けられた.ここに現代的な鳥類起源論争が勃発する.これは一部分岐学論争に関わることになったため論争の様相はナスティなものになった.
フェドゥーシアたち反対論者の論点は始祖鳥と獣脚類恐竜の時期の違い,羽毛の起源,前肢の指の相同問題だった.これらは一つづつ説得的に反駁され(最後の問題の解決は2013年),また片方で1990年代以降羽毛恐竜が次々と発見されることによってようやく大勢は鳥類恐竜起源説に傾きつつある.本書では羽毛恐竜の発見の経緯も詳しく紹介されている.
関連したもう一つの論争は羽毛の起源だ.それが爬虫類の鱗と相同なのか*5,滑空のための適応形質として起源したのかが焦点になる.前者は異なるケラチン起源ということで1990年代に決着する.後者は滑空説のほか,保温説,捕獲説,走行補助説などが主張された.こちらはまだ決着という状況ではないが,本書では走行補助説を好意的に紹介している.
なおここでは関連して鳥類の飛行の航空力学的,生理的理解の進展も紹介されている.これも詳細が理解されたのは最近のことになる.
本書では各章にその分野の学説史の年表があり,重要論文と著書が紹介されている.ここでも章ごとに紹介しておこう.

Feathered Dinosaurs: The Origin of Birds
- 作者: John Long
- 出版社/メーカー: Oxford Univ Pr
- 発売日: 2008/09/01
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログを見る
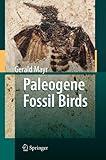
- 作者: Gerald Mayr
- 出版社/メーカー: Springer
- 発売日: 2010/10/19
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログ (1件) を見る

Glorified Dinosaurs: The Origin and Early Evolution of Birds
- 作者: Luis M. Chiappe
- 出版社/メーカー: Wiley-Liss
- 発売日: 2007/03
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログを見る
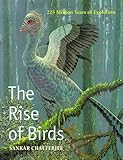
The Rise of Birds: 225 Million Years of Evolution
- 作者: Sankar Chatterjee
- 出版社/メーカー: Johns Hopkins Univ Pr
- 発売日: 1997/11/01
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログ (1件) を見る
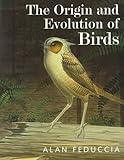
The Origin and Evolution of Birds
- 作者: Prof. Alan Feduccia
- 出版社/メーカー: Yale University Press
- 発売日: 1996/09/25
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログを見る
第2章は「種の起源と多様化」で,扉絵はハワイミツスイの適応放散図.
最初のテーマは形質置換とガラパゴスフィンチだ.ここで鳥類学界の巨人デイヴィッド・ラックが登場する.ラックはガラパゴスフィンチ研究の嚆矢となり,種分化のドライビングフォースは餌を巡る競争だと論じた.
ボウマンは競争の役割の細かな論点を巡ってラックに論争を挑み,ガラパゴスで長期研究を始め,ガラパゴスフィンチの様々な適応放散の様相を調べる.次のガラパゴスフィンチの研究者はグラント夫妻だ.本書は有名なエルニーニョによる自然実験の結果も含めグラント夫妻のリサーチを詳細に紹介している.本書は,これらの研究は基本的にラックの競争を重視した視点が正しかったこと*6を示していると結論している.
次のテーマは遺伝学の勃興.烏骨鶏と赤いカナリア*7が登場する.ベイトソンは烏骨鶏を使って遺伝的変異を調べる.これは初期の遺伝学に非常に重要な洞察を与えたが,後のショウジョウバエを使ったリサーチの陰に隠れてしまう.またカナリアは遺伝学のモデル生物としても使われると同時に,愛好家による赤いカナリア作成競争を生み出し,その結果羽毛の色にかかる遺伝と環境(カロチンの摂食)の影響の理解を深めた.そして1930年代に遺伝学とダーウィン学説の「現代的統合」がなされる.本書では集団遺伝学者たち(フィッシャー,ホールデン,ライト)と,その外側の進化生物学者たち(マイア,ドブジャンスキー,シンプソン,ジュリアン・ハクスレーなど)の双方の貢献について,後者に重心を置きつつ,さらに鳥のリサーチの役割を紹介しつつ描いている*8.ここで現代的総合に大きく影響された鳥のリサーチの例としてオダネルのクロトウゾクカモメの色の多型にかかる性淘汰と遺伝のリサーチ,クックによるハクガンの多型の適応的差異と遺伝のリサーチ,ニュートンによるハワイミツスイの適応放散のリサーチが紹介されている.
また種分化と適応放散に関してはクレイクラフトによる分岐分類と大陸生物地理を統合したゴンドワナ大陸分裂による鳥類の大きな系統の分岐の説明リサーチ,そのほか数多くの鳥にかかる同所的種分化,種分岐の開始,さえずりによる繁殖分離のリサーチが紹介されている.
このエリアでは2000年以降,分子遺伝学の進展によりさらにリサーチが加速しているそうだ.

- 作者: Trevor Price
- 出版社/メーカー: Roberts
- 発売日: 2007/07/01
- メディア: ペーパーバック
- 購入: 1人 クリック: 6回
- この商品を含むブログ (2件) を見る

The Birds of Northern Melanesia: Speciation, Ecology, & Biogeography
- 作者: Ernst Mayr,Jared Diamond,H. Douglas Pratt
- 出版社/メーカー: Oxford Univ Pr on Demand
- 発売日: 2001/12/06
- メディア: ハードカバー
- クリック: 3回
- この商品を含むブログを見る
第3章は「系統樹の上の鳥」で扉絵はヒクイドリ.最初の登場人物はウォルター・ロスチャイルドだ.彼の収集した鳥類標本コレクション*9は彼の破産とともに1931年にAMNHに渡り,そこでマイアに幸運をもたらすことになる.
ここで本書はドイツの鳥類学の発展史を語る.ロスチャイルドのキュレーターだったハルテルト,その伝統を継いだドイツ鳥類学界の巨人シュトレーゼマンの業績が紹介されている.彼らは標本を元に鳥類を記載分類した.
ここでは亜種を巡る論争史*10も紹介されている.そしてもう一つの分類学の大問題はどのように高次分類を決めるかということだった.ヘッケルやハクスレーは直感に基づいた系統樹を作成した.また分類群をどのような順序で並べるかも問題になった.いずれにせよ当初はそれは権威で決めるしかなかった.
ここでエルンスト・マイアが登場する.彼はシュトレーゼマンに師事し,才能を認められ,ニューギニアの調査旅行に参加を許され,AMNHの調査の責任者の後任に推挙され,その後1931年にアメリカに渡ることになる.そしてそこでロスチャイルドコレクションが彼を待っていたのだ.彼は片方で現代的統合に関わりながら,片方で南太平洋の鳥類の系統分類に没頭し,多くの弟子を育て,人脈を築く.その結果マイアの元で,進化生物学に基づき,個体群を考察する新しい分類学が勃興するのだ.マイアは測定,記載,生物地理,集団生態学の知見を総合し,自ら鳥類の分類体系を構築する.
しかしマイアの天下は長く続かなかった.分岐学論争が始まったのだ.本書はその顛末も詳しく追っている.結局1980年以降,最節約法,そして分子データと最尤法を使う系統推定法が大勢になり,様々な統計的ソフトウエアによって系統樹が描かれるようになった*11.そしてシブリーによるかなり信頼できる鳥類の系統樹*12も得られている.
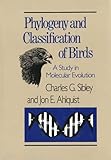
Phylogeny and Classification of the Birds: A Study in Molecular Evolution
- 作者: Dr. Charles G. Sibley,Dr. Jon E. Ahlquist
- 出版社/メーカー: Yale University Press
- 発売日: 1991/01/23
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログ (1件) を見る
第4章は「満ち引き」でテーマは渡り,扉絵は夜間の渡りをする小鳥たちだ.
渡りは鳥類学の大きなミステリーだった.本書のその探求物語は19世紀末のアルフレッド・ニュートンから始まる.ニュートンはそれまでの知見をまとめた.渡りは1か0かという性質ではなく,種内で一様でもない.当時の論点は天候の役割,渡りのルート,そしてどのように渡りのルートを見つけるのかということだった.ニュートンの整理を読むと,最後の論点には渡りの至近的メカニズムだけでなく進化的な説明も含まれているのがわかる.
渡りの適応的意義の説明はウォレスに始まる.彼はまた進化史として渡りの距離がどんどん伸びていったのではないかと考えた.トムソンはその説明に氷河期の存在を加えた.マイアは南半球にも渡りをする鳥がいることからそれに反対した.マイアは自分のリサーチから19世紀以降ヨーロッパセリンの渡りルートが変わっているのを知っていた.渡りは可塑的な行動特性なのだ.本書ではそれにかかる様々な鳥たちの渡りの詳細リサーチが次々と紹介されている.
次のテーマは渡りのルート解明だ.これはヨーロッパのリサーチャーやアマチュアによるヨーロッパの夏鳥のアフリカにおける冬の分布の知見が明らかにされることにより徐々に知られていった.そこからは技術革新史になる.バンディングはデンマークのモーテンセンが19世紀末に始める.プロシアのティエネマンは20世紀初頭それを組織的に行った.アメリカでは軍事目的から軍が資金を提供したこともあったようだ.第二次世界大戦後はレーダー観測が行われる.そして1960年代にラジオトラッキング,1980年代にサテライトトラッキングが始まり,現在ではGPS技術が使われている.本書ではいくつかの渡りルートの解明リサーチが紹介されている.
適応的意義については,ウォレスは南へ渡ることについて採餌による利益を挙げた.しかしこの説明では北へ返る理由にはならない.いろいろ議論されたが,初期の議論は至近因と究極因が混同されていたようだ.現在では比較研究により渡りの環境要因としては緯度,食料,ハビタットの予測力が高いことが知られている.
行動生態学の勃興は最適な渡りをエネルギーの観点から解析するリサーチを充実させた.これによりなぜオグロシギがアラスカからニュージーランドまでノンストップフライトするのかが説明できるようになった.
どのように渡り行動が生じるのかという問題は「本能」を巡る議論につながった.ダーウィンの説明は本能的で,1870年代からすでに学習派の主張がなされている.本書では,これが,生得的な傾向と学習が混在し,さらに種によっても詳細が異なるという複雑な現象であることがわかる過程が詳しく説明されている.
次の議論はルートを見つける至近的メカニズムだ.これも単一のメカニズムではなく,天体の動き,地磁気,臭いを含む様々な手がかりをコンティンジェンシープランとして持っているということがわかっていく過程が詳しく記述されている.本書のこのあたりのリサーチの歴史記述は大変おもしろく,読みどころの一つになっている.
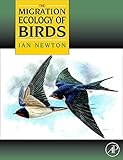
The Migration Ecology of Birds
- 作者: Ian Newton
- 出版社/メーカー: Academic Press
- 発売日: 2010/08/04
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログ (1件) を見る

Bird Migration: A General Survey (Oxford Ornithology Series)
- 作者: Peter Berthold,Hans-Gunther Bauer,Valerie Westhead
- 出版社/メーカー: Oxford University Press, U.S.A.
- 発売日: 2001/09/27
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログを見る
第5章は「繁殖にかかる生態的適応」.扉絵は生態リサーチの対象になったヨーロッパの鳥たち*13の美しいイラストだ.
ここでの主人公はデイヴィッド・ラックになり,冒頭はオックスフォードでのヨーロッパアマツバメのリサーチとそれをまとめた「Swifts in a Tower」(邦題 天上の鳥アマツバメ)が紹介されている.このリサーチにおける一つのテーマは一腹卵数(クラッチサイズ)の適応的な説明だ.ラックはロンドンの裕福な家庭に生まれ,順調にケンブリッジに進んで鳥類学者になる.北極圏のリサーチ経験の後,ナワバリ性に興味を持ち,ロビンの長期リサーチを始める.これも後に「The Life of the Robin」(邦題 ロビンの生活)という本になる.そして英国における鳥類研究の総本山 Edward Grey Instituteのディレクターに就任する.
ラックは1940年代より野外研究において一腹卵数や繁殖タイミングなどの生活史戦略の適応性をリサーチし,それまで標本を用いた分類に傾いていた鳥類学の革新を行った.当初は一種ごとに生活史をリサーチしていたが,60年代には生態的な適応について多くの分類群を比較し総合するような本も書くようになった.これは後の行動生態学の隆盛につながると評価できる.(なおここでは英国,大陸ヨーロッパ,北米での鳥類学の進展の違いなども記述されている)
本書では特に一腹卵数と繁殖開始タイミングの適応性についてのリサーチ史が詳しく取り上げられていて読み応えがある.当初生理的限界に目が向けられていたが,その後適応的な説明が求められ,さらに様々な生態要因との関連がリサーチされるようになるのだ.その中では,至近因と究極因の区別,何が集団全体の個体数の級数的な増大を止めているのかという淘汰の単位に関わる議論,適応度を決めるキーになる生態要因は何か(餌だけか,営巣場所は問題にならないのか,捕食の影響はどの程度かなど),家禽学や遺伝学の知見との統合,ウィリアムズによる生涯繁殖成功と残存繁殖価の議論,それを測定するための実験法を巡る議論(卵除去実験は卵生産コストを無視しているのではないかなど),繁殖開始タイミングと一腹卵数の関係などが解説されている.
また生活史戦略の議論はr-K淘汰の議論につながり,種間比較は,系統性を考慮に入れた統計的手法の開発につながる.
本章はラックの成功要因(進化的重要性をみることのできる観察者だったこと,鳥類についての扱いやすいリサーチ系を確立したこと,個体淘汰の重要性について明確な視点を持っていたこと,登場する時代に恵まれていたこと,よいコミュニケーターだったこと)を考察して終わっている.ラックに対するリスペクト章という位置づけだろう.

Lifetime Reproduction in Birds
- 作者: Ian Newton
- 出版社/メーカー: Academic Pr
- 発売日: 1990/01/01
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログ (1件) を見る

Ecological Adaptations for Breeding in Birds
- 作者: David Lack
- 出版社/メーカー: Chapman and Hall
- 発売日: 1968/07
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログ (1件) を見る
第6章は「形態と機能」と題され,様々な鳥の解剖学的特徴が扱われる.扉絵はオオハシウミガラスとウミガラス.
最初の話題は鳥類としては例外的なカモ類の長大なペニスだ.これはアリストテレスの頃から知られていたが存在理由は謎だった.そして現在ではこれはEPCを巡る性的コンフリクトの結果アームレース的に進化したものだ(そしてメス側の器官も精子の選別のために複雑になっている)ということがわかっている.
19世紀の鳥類解剖学はただ特徴を記載するものであり,それは20世紀に入って事実上停滞してしまった.そしてその後鳥類学の他の分野での進展に伴ってそれに関連する解剖学的生理的メカニズムが注目されるようになる.そして進展のあった主なエリアは,年周期,体温調節,エネルギーシステム,水分と電解質の調節,卵だと指摘し,ここでは,厳しい環境への適応,感覚器,年周期のリサーチ史を取り上げるとしている.
最初は厳しい環境への適応だ,カモなどの潜水する鳥は心拍レートを著しく落とすことができる.そしてどのように潜水病を避け,心臓死や脳死を避けているのかのメカニズムが探求された.これらは最近ではデータロガーをつけたリサーチにつながっている.海鳥は鼻腺で塩分を排出することが理解されたのは1950年代のことだ.
鳥の感覚については前著「Bird Sense」のダイジェストになっている.ワシタカ類の中心眼窩を2つ持つ視覚,紫外線視覚,左右両眼の非対称的使用,脳の性差,さえずりの脳神経系の再構成,嗅覚を持つことの確認などのリサーチの歴史が記述されている.
年周期についてはマーシャルの業績が強調されている.マーシャルはニワシドリをリサーチし,性腺が年周期によって変化していることを見つけ,1960年代にそれまでの年周期のメカニズムについての様々な知見を総説した.基本的には日長で季節を把握しているのだが,やはりここにもバックアップシステムがあることがわかってくる.このリサーチはホルモンと(渡りの開始を含む)行動のリサーチに,概日リズムのリサーチにつながっていく.
著者たちは鳥類のメスの繁殖にかかる生理的メカニズムにはなお謎が多いことを指摘して本章を終えている.

The Flexible Phenotype: A Body-Centred Integration of Ecology, Physiology, and Behaviour
- 作者: Theunis Piersma,Jan A. van Gils
- 出版社/メーカー: OUP Oxford
- 発売日: 2010/11/04
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログ (1件) を見る
第7章は「本能の研究」.テーマはエソロジー,扉絵はミツユビカモメの営巣の写真になる.登場するのはもちろんティンバーゲンとローレンツだ.この二人の巨人にとっても最もよくリサーチした動物は鳥なのだ.本章ではティンバーゲンとローレンツを語りながらエソロジーの歴史をみていくことになる.
行動のリサーチに道を開いたのはここでもダーウィンだった.鳥の野外での行動観察は1900年頃セラスが行ったのが嚆矢になる.1920年代には,これにカークマン,ハワードが続く.これに進化の視点を入れ込んだのはジュリアン・ハクスレーになる.
片方で,ロシアのパブロフは行動を学習による条件付けで説明する.この流れは北米のワトソン,スキナーにつながり,ダーウィンを無視し,すべては環境だと考える行動主義を生み出す.(これらはウィットマンやクレイグの動物行動にかかるアメリカの先駆的研究を覆い隠してしまった)
鳥を愛するナチュラリストは納得しなかった.ハインロートはカモなどの配偶行動を研究し,ローレンツに大きな影響を与える.ローレンツは若い頃からの動物好きで,後年「刷り込み」と名付けた現象に早くから親しんでいた*14.ローレンツは様々な業績とともにドイツの学界の大立者になっていく.彼は動物行動の理解の天才であると同時に,実験デザインや統計を軽視し,攻撃的でドグマティックだった.しかし刷り込みの発見は衝撃的だった.彼は動物行動のリサーチの全く新しい方法を示したのだ.1935年にはコクマルガラスのリサーチをまとめ,環世界というコンセプトとともに社会的性的相互作用を含む動物行動を説明した,本能についてさらに考察を重ねたローレンツは1936年に,ライデンで開かれた動物本能の学会でティンバーゲンと出会う.ティンバーゲンはオランダ生まれで,若い頃から鳥に魅せられ,生物学を志し,ライデン大学に進んでいた.2人は生涯の共になり,共同でエソロジーを立ち上げる.初期のテーマは「サイン刺激に対する固定的な行動パターン」の提示だった.そして有名なカモメの嘴の赤点とヒナの餌ねだり行動の実験が行われる*15.
そしてナチズムの台頭と第二次世界大戦が,ティンバーゲンをナチの収容所に,ローレンツをソ連の収容所に送ることになる.ローレンツはナチ政権の中で職を得るためにナチに協力もしていたが,ソ連の収容所から1948年に解放されると2人の友情は復活した.ラックはティンバーゲンをオックスフォードに招き*16,エソロジーはそこで花開く.ティンバーゲンはカモメの比較研究を行い,ローレンツは水力学的モデルを提示する.本書ではその後勃発したティンバーゲンやローレンツとレーマンの間に生じたエソロジー論争(主にエソロジーが扱う概念が単純化しすぎで,背後のメカニズムの複雑さが無視されているのではないかという批判が論争の中心になる),ホールデンのエソロジー批判も紹介している.また2人の巨人以外のエソロジー学者としてはソープが登場している.彼はさえずりのリサーチの先駆者となった.ヒンデやマーラーがその後に続いている.またベイトソンは刷り込みの詳細をリサーチした.1973年,ローレンツとティンバーゲンはフリッツとともにノーベル賞を受賞し,エソロジーの栄光はピークを迎え,その後動物行動のリサーチはエソロジー的なものから行動生態学などの取り組みに移り変わる.
本書はここでエソロジーを総括している.エソロジーの功績について,動物行動を記述し測定する方法論を与えたこと,行動が環境に対する適応として進化する可能性を認識させたこと,ティンバーゲンの「4つのなぜ」でリサーチのフレームを明確化したこと,本能と学習の二元的見方が間違いであることを示したこと,そして最後に鳥類の行動について多くを明らかにしたこととしている.そしてティンバーゲンのフレームは行動の適応的意義にリサーチャーの注意を向けさせ,それは行動生態学につながっていったのだ.
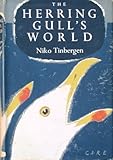
Herring Gull's World: Study of the Social Behaviour of Birds (Collins New Naturalist)
- 作者: Niko Tinbergen
- 出版社/メーカー: HarperCollins Distribution Services
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログを見る

- 作者: K. Lorenz,R.W. Kickert
- 出版社/メーカー: Springer
- 発売日: 1981/09/23
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログ (1件) を見る
第8章は「適応としての行動」扉絵にはファンタジーフィールドガイドのための鳥のイラストが用いられている.テーマは行動生態学だ.
1970年代初頭,動物行動の野外リサーチは新しい原理を欲していた.そして行動生態学は若手リサーチャーに熱狂的に受け入れられた.本書は,受容のコアには,仮説検証体系,量的な分析,揺るぎない個体淘汰へのフォーカスがあったとしている*17.そしてその結果,鳥類の行動の理解は大きく進み,鳥類学そのものの性質も大きく変えた.
本書はここで初期の淘汰の単位論争史を解説している.ある意味で行動生態学はウィン=エドワーズ説への反論から始まり,そしてハミルトンの包括適応度理論,ドーキンスの「利己的な遺伝子」の出版に大きく影響を受けている*18.
ここでは行動生態学の鳥類に関する豊穣なリサーチトピックから,共同営巣(ヘルパーの存在),最適採餌,托卵,知性について紹介される.
鳥のヘルパーの報告は1920年代のスカッチによるコスタリカのハイバラエメラルドハチドリの観察から始まる.スカッチはそれについて曖昧なグループ淘汰的な説明を行った.しかしそれはヘルパーからみると利他行為であり,個体淘汰的にみると謎になる.鳥のヘルパーについて包括適応度理論を当てはめようという試みは1970年頃から始まる.カケス類におけるヘルパーで,ヘルパーのいる巣の方がより繁殖成功が高いことがまず示された.しかし血縁を通じた包括適応度上昇分(間接増加分)は小さいことがわかってきた.次に環境制限が考察された.営巣場所の制限などによりヘルパーはとどまった方がましなのかもしれない.この実証は1990年代に行われた.本書では一連のセイシェルムシクイのリサーチが紹介されている.また片方で,ヘルパーの血縁度を測定する技術も進歩し,ヘルパーが常に血縁個体でないことも明らかになった.現在ではそれは多元的に説明され,系統や生活史や環境条件がどう影響するかが議論されている.
最適採餌理論は行動生態学の初期の成果だ.適応度を最大化するためにどこでなにをどう採餌すべきか,様々な観察,実験が行われ,仮説が検証された.本書では理論の要点とシジュウカラなどの鳥を使ったリサーチが数多く紹介されている.
カッコウの托卵習性は18世紀から記述され,ダーウィンもその適応的意義についてOriginの中で触れている.托卵行動は行動生態的には多くの謎を提示していて大変興味深い問題だ.本書ではダーウィン以降の議論から丁寧に学説史を追っている.
鳥の知性についてはガラパゴスのキツツキフィンチの道具使用の発見から語られている.やはりここでも学説史はダーウィンから始まる.初期の知性の研究は,道具使用,空間オリエンテーション,理由付け,抽象化などが中心テーマで,対象動物としては霊長類やマウスと並んでハトやウズラやニワトリのヒヨコがよく使われた.1920年代頃から鳥の野外行動を用いたリサーチが現れ始め,1950年代にソープはそれらの知見をまとめる.ソープは特に「洞察」に興味を持ち,多くの試行錯誤学習だけでは説明できない問題解決行動があると主張した.比較心理学者のリサーチは擬人化的だったが行動生態学者のリサーチは適応による特殊化に向かった.エメリーは生態条件と知性の種間比較を行って,雑食,長寿,幼年期の長さなどと相関することを見つけた.オウムとカラスにはこの説明は良く当てはまる.ここではハインリッチのワタリガラスのリサーチ,ペッパーバーグのヨウムのアレックスのリサーチ,多くのリサーチャーによる様々なニューカレドニアガラスほかのカラス類のリサーチ,そして最後にキツツキフィンチの最新のリサーチが紹介されている.
本章では最後に「行動生態学は鳥類のリサーチにおいて最も広く深い成功をもたらしたアプローチだ」と結論し,その要因,行動生態学の様々な方法論の進展などをまとめている.著者たちが行動生態学者であるので割り引かなければならないかもしれないが,これは偽らざる感想ということだろう.

Cuckoos, Cowbirds and Other Cheats (Poyser Monographs)
- 作者: Nick Davies
- 出版社/メーカー: T & AD Poyser
- 発売日: 2010/09/30
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
第9章は「性淘汰」*19,扉絵はアオフウチョウ.
本章の最初の登場人物は,コクホウジャクを使ってメスの選り好みを実証したマルテ・アンダーソンだ.本書ではそのリサーチの裏話も含めて詳しく紹介されている.性淘汰を最初の主張したのはもちろんダーウィンだ.ダーウィンはDescentにおいてそのアイデアを提示し,鳥類は丸々4章を使った題材になっている.しかしメスによる選り好みというアイデアは最初から論争の種になった.本書ではその論争の流れも詳しく追っている.
最初のメスの選り好みの証拠は1900年代のセラスによるエリマキシギのレックの観察から得られた.しかしこの観察報告は忘れられた.本書は鳥類の性淘汰にかかるその後の様々な観察や実験のリサーチを丁寧に追っている.
ジュリアン・ハクスレーはカンムリカイツブリやエトロフウミスズメのコートシップディスプレーを観察し,それがオスメス同じような動きをし,交尾後も行われることからメスの選り好みのアイデアに懐疑的になった*20 *21.この態度はラックにも受け継がれた.ラックはモノガミーの鳥でメスの選り好みは効かず,ポリジニーの鳥でもオスオス競争のみが効くのだと考えた.本書はそれはラックが生態要因のみに関心があったためだろうとコメントしている.
個体淘汰的に性淘汰を再考察する動きは1960年代のクルークに始まる.クルークはハタオリドリを調べ,配偶システムと生態に相関を見つけ,包括適応度理論に関心を持った.オリアンズはそれを受け継ぎ,有名なポリジニーの閾値モデルを提唱した.ハミルトンとトリヴァースの仕事はオスとメスのリソース投資のあり方にリサーチャーの関心を向けた.トリヴァースはメスのみが子育て投資をする種のオスは交尾機会を増やすために投資を行うはずだと指摘し,レックにおけるディスプレーをそれにより解説して見せた.エムレンとオリングは配偶システムの進化と性淘汰を関連させたアプローチをとり.実効性比の概念を提唱した.
それまで性淘汰の理論的考察はフィッシャーによるランナウェイモデルだけだったが,1970年代以降「良い遺伝子」を巡る理論が現れる.ザハビはハンディキャップ原理を主張し,のちにグラフェンは数理モデルを組み上げる.そしてこれらに触発された鳥類のリサーチが大量に発表されるようになる.本書では美しい写真付きでバーレイのキンカチョウの足輪リサーチ,ヒルのメキシコマシコのオスの色の好みのリサーチなどが紹介されている.さらに,モラーのツバメの尾のリサーチ,鳥類のUV視覚,レックシステム,ニワシドリの延長された表現型,ハミルトンとズックのパラサイト耐性説,冒頭のアンダーソンの操作実験,精子競争とメスの隠れた好み(交尾後の性淘汰),ヨーロッパカヤクグリやウタスズメのEPCなどのリサーチが次々に紹介されている.これらの記述を読んでいると,確かに性淘汰を巡るリサーチは鳥類の行動生態において重要なエリアになっていることが実感できる.

Sexual Selection (Monographs in Behavior and Ecology)
- 作者: Malte Andersson
- 出版社/メーカー: Princeton University Press
- 発売日: 1994/05/27
- メディア: ペーパーバック
- 購入: 1人 クリック: 2回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
第10章は「鳥類の個体群研究」.扉絵はカラフトライチョウが使われている.本章のテーマはラックとウィン=エドワーズの間で繰り広げられた,個体群規模の調節にかかるナイーブグループ淘汰論争だ.これは特に「何が鳥の個体群の規模を抑制しているか」について争われたもので,本書ではこの論争は20世紀の鳥類学の論争の中で最も激しいものの1つだったと評価している.
ウィン=エドワーズは英国生まれ,オックスフォードで研究生活を始めたのはちょうど現代的総合の時期だった.エルトンの生態的ニッチの議論に感銘を受け,ウィン=エドワーズは個体群の最適密度というアイデアにたどりつく.1937年から北極圏のフルマカモメを観察し,繁殖しない個体を見つけた彼は,1950年代に「個体数抑制がナイーブグループ淘汰により生じる」という主張を行うようになる.ラックは自然淘汰は個体淘汰的にしか働かないと激しくこの考えを批判した.ラックもウィン=エドワーズも英国紳士としての態度を崩さず,論争はナスティにはならなかったが,1960年代を通じて双方一歩も引かずに続くことになる.本書は双方のこの間の主張を丁寧に追っていてなかなか読み応えがある.後のマルチレベル淘汰論争につながるウィリアムズやメイナード=スミスのグループ淘汰批判,そしてドーキンスの「利己的な遺伝子」はこのラックとウィン=エドワーズ論争の文脈のうえでなされているのだ.
論争は最終的には個体淘汰主義者の勝利となったが,この論争は理解の深化に役立った.当初のラックの主張は食糧の量的制限による密度依存的な効果を強調するものだ.論争に触発されて多くの長期リサーチがなされ,捕食やパラサイトの効果,様々な要因のトレードオフ,生涯繁殖成功という概念,生活史戦略の重要性の認識,マッカーサーの数理的生態学につながっていく.本書ではそれらについても簡潔にまとめられている.

Population Limitation in Birds
- 作者: Ian Newton
- 出版社/メーカー: Academic Press
- 発売日: 2011/05/26
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログ (1件) を見る
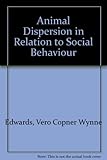
Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour
- 作者: Vero Copner Wynne Edwards
- 出版社/メーカー: Oliver & Boyd
- 発売日: 1972/07/03
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログ (1件) を見る
第11章は「明日の鳥類」.扉絵はロロ・ベックの手による絶滅したガダループカラカラのイラストだ.本章は現在の野生鳥類のおかれた苦境や絶滅,そして保全生態学を扱っている.
冒頭はアオコンゴウインコの絶滅危惧の話から始まる.この美しい鳥の危機は1970,80年代を通じたたった2人の鳥類ディーラーによる標本捕獲によって生じた.そこから本書はリョコウバトや19世紀の婦人帽への鳥の羽の飾りのための乱獲などのエピソードを紹介し,絶滅リスクを全体的に俯瞰し,保全の取り組みの重要性を指摘する.
保全には大衆の理解が欠かせない.本書は一般大衆へ鳥への愛を植え付けた嚆矢はロジャー・トリー・ピーターソンによるピーターソン野鳥ガイドの出版(1934年)だと指摘している.さらにオーデュボン教会の活動,クリスマスバードカウントなどのイベントなども紹介している.
本章の後半のテーマは保全の方法論や取り組み例の紹介だ.方法論は持続可能な狩猟への取り組みとして始まった.そして渡り鳥の避寒地,中継地点の環境保全の重要性,捕獲・飼育による取り組みには行動生態の理解が欠かせないこと,DDTなどの薬剤の影響とそれを巡るレイチェル・カーソンと製薬会社との闘争,カリフォルニアコンドル,カカポなどについての具体的取り組み,ホオジロシマアカゲラやニシアメリカフクロウの保全プログラムと政治的取り組みの重要性などが詳しく記述されている.

- 作者: John Terborgh
- 出版社/メーカー: Princeton University Press
- 発売日: 1989/12/21
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログを見る
最後に「あとがき」が置かれ,何が鳥類学を今日のレベルに推し進めたのかについて考察されている.まずシュトレーゼマン,マイア,ラックに代表されるリーダーたちの役割だ.彼等は素晴らしい本を書き,自然史を愛し,すべてにオープンな態度を保った.そしてそして極めてハードワークで多産であり,多くの人のメンターになったのだ.2番目は1960年代以降の教育の広がりだ.これにより多く有能な若者が鳥類学を志すようになった.3番目には政府による資金的な支援が挙げられている.1950年代から1980年代ぐらいにかけて自然科学には(拙速な見返りを求めない)「ピュア」な西側諸国政府からの資金的な支援があった*22.4番目には技術の進歩が来る.そして著者たちは,「鳥類学はこれらを受けて,理論へのフォーカス,仮説の提示と検証,統計的な分析と数理的なモデリングに傾斜した力強い科学の一部となった」と総括して本書を終えている.

Systematics and the Origin of Species from the Viewpoint of a Zoologist
- 作者: Ernst Mayr
- 出版社/メーカー: Harvard University Press
- 発売日: 1999/10/15
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログ (1件) を見る

The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance
- 作者: Ernst Mayr
- 出版社/メーカー: Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press
- 発売日: 1985/01/22
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログを見る

Darwin's Finches (Cambridge Science Classics)
- 作者: David Lack,Laurene M. Ratcliffe,Peter T. Boag
- 出版社/メーカー: Cambridge University Press
- 発売日: 1983/09/15
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログ (1件) を見る
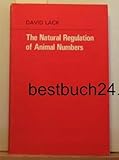
Natural Regulation of Animal Numbers
- 作者: David Lack
- 出版社/メーカー: Oxford University Press
- 発売日: 1970/12/10
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログ (1件) を見る
というわけで本書は進化生物学と鳥に興味のある人には見逃せない素晴らしい本になっている.様々な進化生物学の進展や論争が鳥類学のフレームの中でどのような様相を見せたのか,鳥に魅せられたリサーチャーの人生模様.そして数多く語られる興味深い鳥類の生態.私はこれを読んでいるあいだ中ひたすら楽しかったと告白しておこう.
これはバークヘッドの前著.残念ながら電子化されていない.

The Wisdom of Birds: An Illustrated History of Ornithology
- 作者: Tim Birkhead
- 出版社/メーカー: Bloomsbury UK
- 発売日: 2011/03/01
- メディア: ペーパーバック
- 購入: 1人 クリック: 1回
- この商品を含むブログを見る
*1:この本は美しい図版が満載の厚い本だがなぜか電子化されてない.私はハードカバーを入手して,時折図版をちらちらみて楽しんでいるが,もはやタップ辞書なしでは読む気になれずに,ただただ電子化されるのを待っている状態だ.
*2:ここで始祖鳥がよく論争の種になることの例として,最近の物理学者フレッド・ホイルを抱き込んだ創造論者のフェイク説の顛末も紹介されている
*3:正式なトレーニングを受けいていないアマチュアの研究家として出発し,祖国オランダの学会に無視されるなど苦労したそうだ.
*4:オストロムは同時に,恐竜の温血性,羽毛が飛行以前に進化したことも主張している.
*5:最初の鱗説の提唱者ノプシャ男爵の奇矯な人生模様もここで紹介されている
*6:もっとも初期にはラックは浮動の役割をかなり重視していたが,その後適応論者に変わっている
*8:マイアによるゴールドシュミットの「有望な怪物説」の粉砕,「系統分類と種の起源」の出版,生物学的種概念の提唱などが紹介されている.それらは種分化と適応放散のリサーチにつながる.
*9:ここで20世紀前半の鳥類コレクションの話が語られている.アメリカの鳥類標本収集家ロロ・ベック,マイナーザンゲン大佐も登場する.あわせて初期の鳥類標本収集の実情,コレクションのメンテナンスの苦労,AMNHの標本収集キャンペーンなどもたっぷり語られている
*10:亜種を認めて3命法にするかどうかは当時としては大変な大問題だったようだ
*11:フェルゼンシュタインはこの様子について,系統推定の「どうでもいいじゃない派」と呼んでいるそうだ
*12:少し前の常識からは考えられない知見も多く得られている.本書ではオーストラリアの鳴鳥類が,ほかの大陸の鳴鳥類よりカラス類に近縁であることなどを例示している
*13:シジュウカラ,ヨーロッパジョウビタキ,マダラヒタキ,モリフクロウ,アオサギ,ホシムクドリ
*14:彼はカモが自分に刷り込まれただけでなく,自分もカモに刷り込まれたと語っていたそうだ
*15:ここでは,当時の実験は手順や結果判別手続きがスロッピーで,査読もなく発表され,再現性に問題のあるものもあったことも指摘されている.そしてそれはその後数十年の分析技術を含む科学の進歩を示していることでもあるとしている
*16:ローレンツも招聘する計画があったようだが,実現しなかった
*17:本書は仮説と検証についてはポパーの影響があったとしている.
*18:ここでウィルソンの「社会性生物学」については,「淘汰の単位論争について明確な説明を欠いていた」と辛辣に評している
*19:原題は「Selection in Relation to Sex」とされており,ダーウィンのDescentへのオマージュになっている
*20:ハクスレーはコートシップディスプレーによる調和というグループ淘汰的なアイデアに傾いた.本書はハクスレー自身の結婚生活が調和とはほど遠いものだったことをほのめかし,皮肉なことのなりゆきだったとコメントしている
*21:なお「なぜカンムリカイツブリのように,ペア形成後もオスメス共同して入念なコートシップディスプレーを何年も続ける鳥がいるのか」については現在でも完全に説明することはできない謎として残っていると最後にコメントされている