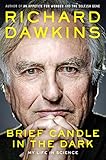
Brief Candle in the Dark: My Life in Science
- 作者: Richard Dawkins
- 出版社/メーカー: Ecco
- 発売日: 2015/09/29
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログ (2件) を見る
本書はドーキンスの自伝の下巻になる.上巻「An Appetite for Wonder」はドーキンスの祖先の物語から始まって「利己的な遺伝子」の出版までだった.下巻は当然そこから物語が続くかと思ったが,ドーキンスは少し趣向を変えている.
タイトルは「暗闇の中の短いろうそく*1」というほどの意味だが,これはもともとはシェイクピアのマクベスの中にでてくる言い回しをカール・セーガンが「科学」についての比喩として用いたことから来ているようだ.自分の行ってきた科学は暗闇を照らすろうそくのようなものであったはずだという自負も込められているのだろう.
巻頭は,オックスフォードのニューカレッジホールで開かれた自分の70歳を記念するセレモニーの席上で去来した思いの吐露から始まっている.アフリカの植民地での子供時代,「利己的な遺伝子」の出版,ゲストの顔ぶれから人文科学と自然科学の融合への思い,ダグラス・アダムスの想い出,そして本書は上巻のように時系列物語ではなくテーマごとのフラッシュバックと逸話集として語られると宣言される.
最初のテーマは大学の教官としての雑務.1970年から1990年までドーキンスはオックスフォードのニューカレッジの動物行動学のLecturer(のちにReader)として勤めたことになる.当初は男子学生ばかりだったのが女性比率がどんどん上がっていったこと,新入生の選抜をめぐるあれこれ(当時は口頭の審問が大きな比率を持っていたようだ.様々なエピソードやドーキンスの選抜に関する考え方が語られている),若き日のアラン・グラフェンやマーク・リドリーの仕振り,学部卒業試験’finals’の過酷さ,試験の採点の順番効果をなくそうとした試み,輪番制で回ってきた’Sub-Warden’(副長)業務のあれこれ*2などが語られている.
次はリサーチ.メイナード=スミスらと一緒になったバロ=コロラドのフィールド経験,そしてジガバチのESS戦略リサーチの顛末(これはハチの専門家ジェイン・ブロックマンと数理に強いアラン・グラフェンとの共同研究でドーキンスにとっても特に実りの多いリサーチだったようだ.詳しく経緯や内容が語られている.内容的にはESSによる戦略多型のフィールドでの実証というところに意義を見いだしている.またこの論文は,通常の形ではなく,実験や観察とともに仮説が次々と生みだされる順序に沿って書かれていてそれも自慢であるようだ.),さらにジガバチがコンコルド誤謬(これはドーキンス自身の命名だそうだ)を行うか*3という有名なリサーチも紹介されている.
次はカンファレンスの想い出.ドーキンスにとって特に印象深かったもの6大会が取り上げられている.まだ若いときに出たカンファレンスでの大物たちの所業.ネクタイの色と模様について絡まれた話*4,社会生物学論争が沸騰している際にEOウィルソンに水がかけられたというまさにその場にいたときの記憶,宇宙飛行士たちとのカンファレンスの楽しい想い出などが語られている.
ここでクリスマスレクチャー.ロイヤルインスティテューション(RI)の子供向けのクリスマスレクチャーはマイケル・ファラディの「ろうそくの科学」に始まる伝統あるもので,これを主催するのは英国人科学者としては大変な栄誉らしい.ドーキンスは緊張して,入念な準備を行ったことを語っている.ドーキンスのレクチャーは5部作になっていて,それぞれ詳しく紹介されている*5.娘や友人のダグラス・アダムズが登場するくだりなどの逸話も面白い.この講演は日本でも3部に縮めた上でなされていて,ドーキンスはその想い出も語っている.通訳を介さなければならないところや,日本人の子供がシャイでなかなか積極的に参加してくれない*6あたりをぼやいている.その他日本の想い出としては,中山賞やコスモス賞の受賞記念で来日したときのこと*7や,ごく最近にダイオウイカの海中撮影に成功した際にその直後にチームに参加したときのことが語られている.
次は出版の話.ドーキンスは自著の出版社を次々に変えているが,それは信頼できるエディターが出版社を移るのでそうなったということが最初に説明されて,編集者や出版代理人たちとの想い出が語られている.翻訳をめぐるドタバタ*8,索引に隠し込むジョークのお遊び*9などの逸話は傑作だ.またアメリカでの代理人ジョン・ブロックマンについては,ドーキンスにララ・ウォードを引き合わせてくれたのだそうで,その後の結婚にいたるおのろけも含めてそのあたりのいきさつが詳しく書かれている.
また後半では「延長された表現型」以降の主要著書の狙いや背景が順番に語られている.ファンには堪えられないところだ.まず嬉しいお知らせとしては「祖先の物語」についてはヤンによる最新の知見の補充を加えた第二版が出されることが告知されている.「悪魔に仕える牧師」についての部分では,愛娘ジュリエットへの手紙が書かれた背景,彼女の母(つまりドーキンスの前妻)との別れの悲しい物語が読者の涙を絞る.「神は妄想である」について当初ブロックマンは「アメリカ市場で宗教に否定的な本を出しても」と乗り気ではなかった.しかしブッシュ大統領の神権政治への傾倒*10がブロックマンをしてそれの出版へ踏み切らせたそうだ.
続いてテレビ番組.ドーキンスは1986年以降多くのテレビドキュメンタリーの制作に関わっている.冒頭で英国で作られたドキュメンタリーの音声が(アメリカ人はブリティッシュ訛りを好まないだろうと理由で)アメリカの声優で吹き替えられることへの苦言があって面白い.*11
最初に関わったのは繰り返し囚人ジレンマにおけるアクセルロッドとハミルトンの発見*12を紹介する番組だったそうだ.これに絡んでIBMヨーロッパの社内研修に呼ばれ,そこで繰り返し囚人ジレンマゲームを(協力の重要性を研修する意味で)行ったところ,4時にゲーム終了ということが参加者に知られることになって最後は裏切りの連鎖になったという傑作エピソードも載せられている.
そこから様々なテレビシリーズの狙いや背景や裏話が紹介される.ほとんどは日本で放映されていないものでそこは少し残念だ*13.またここではこれらを通じて知り合ったダグラス・アダムズやミリアム・ロスチャイルドの想い出も語られている.
またオーストラリアの創造論者たちのだまし討ち取材の顛末や,同じく創造論者に肩入れする放送局に不誠実な編集にあった不快な経験を語り,その後の迷信や宗教関連番組への関与を説明している.また最後には現行のテレビシリーズの作られ方に関してもっと視聴者の知性を信用した番組も作られるべきだと苦言を呈している.
次はディベートと出会いと題されている.冒頭でドーキンスはディベートフォーマットは嫌いだとコメントしている.要するにこれらは法律家のやり方で,自分の信じていることを時には隠し,相手の隙を突くだけで,一緒に真実に迫る方法としては稚拙だということだ*14.また創造論者や迷信支持者たちと対決するスタイルについては,そもそも彼等のトンデモ主張と自分たちの主張がベースとして対等なところから始めなければならなくなるのもおかしいとコメントしている.それはまったくその通りで,これは昨今の日本のトンデモ主張をめぐる論争にもよく見られる歯がゆい構造だろう.ドーキンスが神についてよく「神の存在の確からしさは妖精やユニコーンのそれと同じだ」というコメントを行っているが,そのあたりの事前確率の問題意識ということだろう.そして特に司会者を立てずに語り合う方式を好むとし,ピンカーやローレンス・クラウスとの会話,新無神論者4人の会談などの想い出を語っている.
そしてシモニ教授職.50歳になったドーキンスは研究室で若手を教えることよりも一般大衆に科学を伝えていく方により魅力を感じるようになる.オックスフォードに大衆啓蒙のための教授職を作るアイデアに対しマイクロソフトの創業者の1人のチャールズ・シモニは興味を示す.そしてドーキンスはシアトルでシモニに会い,この話は前に進む.通常この手の話は一代限りのことが多いが,シモニはこの職が永続することを望み*15,そのためのファンドも拠出することになり,ドーキンスは初代the Charles Simonyi Professorship of Public Understanding of Scienceに指名される*16.
シモニプログラムの華は毎年開かれるシモニレクチャーだ.ドーキンスはダニエル・デネット,スティーヴン・ピンカーなどの招聘講演者たちの講演や想い出を語っている.ジャレド・ダイアモンドとのランチの逸話*17はなかなか面白い.
こうして逸話を重ねていって終わるのかと思わせておいて,ドーキンスは自著の主張について最後に長大な章をおいている.1冊ずつ解説するのではなく,著書に流れるテーマごとにコメントを書いている.ここはとりわけ読みどころだ.
冒頭は軽めのエピソードから始まる.「利己的な遺伝子」の出版後に日本のテレビ局がやってきて,どうしてもタクシーの中でインタビューしたいと言い張った話が載せられている.ヴィークルを通訳がタクシーと誤訳したことによるらしいと楽しそうに書いている(これは上巻にも書かれていたエピソードだ.よほど印象深いのだろう)*18.そこからが本題だ.
- 最初のテーマは「遺伝子」:何故「淘汰の単位」とされるもので遺伝子だけが特別なのかについて,グールドが理解できなかった部分も含めて,複製子本体とそれが乗るヴィークルの違いだと解説している.このあたりは年来の主張なので流れるようだ.フィッシャー,ハミルトン,緑髭効果も登場し,包括適応度理論と遺伝子視点からの理解が,同じ物事の二つのとらえ方であることを強調している.そして「本質的な違いが遺伝子とそれ以外のヴィークルの間にのみある」ということは「ヴィークルは個体である必要がない」ことを意味し,「延長された表現型」につながる.ドーキンスは最もよい「延長された表現型」の例はパラサイトによるホスト操作だとして最近のアンソロジーも紹介しつつ解説している.さらにこの考察は,動物の信号自体を相手を操作しようとするものと捉える見方に広がる.そして個体についての見方も変わる.個体とは,多くの遺伝子が出口と運命を共有するために協力しやすくなっているパッケージ(ウィルスの共同体)に過ぎないのだ.ドーキンスはこの一連の考察についてデネットやステレルニーから十分に哲学的な内容があるとコメントされたことについて嬉しそうに書いている*19.なお関連するテーマとして「協力する遺伝子」も扱われている.
- 次のテーマは「適応主義」:ドーキンスとクレブスはアームレースを考察し,その成り行きについていろいろと考察し,適応制約についても深く議論している.「延長された表現型」では丸々一章にそれが当てられている.そこに投げ込まれたのが1979年のカンファレンスで口火を切ったグールドとルウォンティンの適応主義への批判*20だ.ドーキンスはこれは「ありもしないかかしへの批判だった」と苦々しげに書いている.グールドたちの主張について徹頭徹尾反論批判した論文が出た後のカンファレンスでグールドが厚顔にもそれを全く無視したナイーブな主張を繰り広げたことや,ルウォンティンの若書き論文がまさに適応主義的だったことなどにも触れている.ここではこの論争についての解説本としてマレク・コーンの「A reason for everything」が紹介されている.これもなかなか面白い本だった.なおドーキンスはここで(ある動物の身体や行動をエンジニアの視点から眺める)適応主義的な視点は教育の観点からも有効であることにも触れている.
- 「遺伝子の本」:悠久の世代の適応を経た生物のゲノムには,この種の過去の環境が書き込まれていると考えることができる.ドーキンスは「遺伝子の川」「虹の解体」でこのアイデアを膨らませている.ドーキンスは様々な生物の収斂形質についてもDNA分析で共通点を拾えれば,生物間の過去環境にかかる関係図が描けるかもしれないと夢想していて面白い.
- 「人為淘汰プログラム」:「ブラインドウォッチメイカー(盲目の時計職人)」で登場した「バイオモルフ」はドーキンス自身にとっても印象的だったようで,開発時の想い出が詳しく書き込まれている.「不可能の山に登る(未邦訳)」では巻き貝の貝殻形成プログラム「スネイルズ」と体節を持つ動物の発生プログラムを模した「アーソロモルフ」も登場する.コンピュータオタクだったドーキンスとしても思い入れがあるのだろう.それぞれ詳しく紹介されている*21.
- 「進化容易性の進化」:発生を組み込んだ淘汰プログラムの経験はドーキンスに「evolvability: 進化容易性」の概念に到達させる.これはまさに適応万能論の対極にある発想で,ドーキンスはこれについてもいろいろと思いを書き連ねている.
- 「言語の進化」:コンピュータオタクだったドーキンスはサブルーチンになじみがあり,言語の持つ再帰性の重要性に早くから気づいていた.ここでは言語の進化において再帰性の獲得が一種の跳躍進化の例になるかどうかが論じられている.
- 「ユニバーサルダーウィニズム」:ここもドーキンスの思い入れのあるところだ.ラマルク型の進化が生じない理由として,単に事実の問題として獲得形質が継承されないとする論者には不満をぶつけ,(1) そもそも使用したからといって有用になるとは限らず(2)摩耗して壊れていくことも多い (3) さらに機能する生物として作られるには発生プログラムはレシピ型になると考えられ,そうであれば原理的に獲得形質が遺伝子に書き戻され得ない,と議論している.
- 「ミーム」:ドーキンスが「利己的な遺伝子」でDNA以外の自己複製子の例として「ミーム」を持ち出したことはよく知られている.ここでは当時はまだコンピュータウィルスが一般的ではなかったこと(よく知られていればそちらにしただろう),遺伝子との共進化という観点はEOウィルソンの方が早かったことなどを指摘しながら,その後の成り行きを回想している.なおここでは複製の忠実性の問題はミームについての決定的な批判にはならないこと(折り紙などのデジタル性のあるミームはそれぞれの受け手がノーマライズすることによって本質がきちんと伝わりうる)が強調されている.
- 「自分が個人的に信じられないことを根拠とする議論」:これは創造論者の議論(ハリケーンによって部品の山が巻き上げられ747に組み上がるはずがない)を揶揄した言い回しだ.ドーキンスは自然淘汰と偶然を混同している誤解を指摘し,さらに彼等の「そもそも(偶然だとすると)科学者がこの小数点以下80桁以上のありえなさを無視していると想定する傲岸さ」「科学の力と洗練に対する無知」「仮にそれがあり得ないとしても何ら問題が解決されない(そもそも何故神がいるのか)ことを何とも思わないこと」には本当に苛立つとコメントしている.
- 「神の妄想」:「神は妄想である」はベストセラーになっていろいろな現象を引き起こしているが,ドーキンスは回想風にいろいろなことを語っている.あの本で宗教についていろいろと辛口コメントを行っているが,自分ではユーモアのある揶揄表現としたつもりだと書いているのもちょっと面白い.字面ではそうでも,宗教信者から見ると「神聖」なものへの攻撃なので受け取られ方は異なるということだろう.ドーキンスは,それは宗教をオフリミットにしているためだとコメントしている.その他ヴァージニア州での講演で,宗教系の大学からやってきた女学生から‘What if you’re wrong?’と問われてそこで当意即妙に答えたエピソード*22,無神論者の講演に税金を使うのはまかりならんと乗り込んできたオクラホマ州の上院議員の振る舞い,キリスト教の教義の矛盾について貴族の坊ちゃんと執事の会話で示したパロディ(これは傑作)なども書き込まれている.
そして場面はニューカレッジホールの70歳の記念パーティに戻る.ドーキンスは,妻,優秀な弟子,幾多の知人に囲まれて最後の挨拶で詩を披露する.その「最後に残された時間も虹を解きほどきたい」という思いの乗る詩を掲げて本書は終わっている.
というわけで本書は,自伝というよりは後半生をテーマごとに回想したエッセイ集だ.時に感傷的で,時に裏話を披露し,そして自らの主張を最後にもう一度まとめている書物でもある.ファンにとってはたまらない一冊ということになろう.
関連書籍
上巻.私の書評はhttp://d.hatena.ne.jp/shorebird/20131011

- 作者: Richard Dawkins
- 出版社/メーカー: Harper Collins USA
- 発売日: 2013/09/24
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログ (3件) を見る
同邦訳.本書も近日中に訳されることが期待される.なお邦書が出版されて約1ヶ月遅れで電子化もされているようだ.これはKindle版

- 作者: リチャードドーキンス
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 2014/06/30
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
クリスマスレクチャーの邦訳書籍.こちらも1ヶ月遅れで電子化.私の書評はhttp://d.hatena.ne.jp/shorebird/20150104

- 作者: リチャードドーキンス
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 2015/01/29
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログ (4件) を見る
パラサイトのホスト操作に関するアンソロジー.私の書評はhttp://d.hatena.ne.jp/shorebird/20140914

Host Manipulation by Parasites
- 作者: David P. Hughes,Jacques Brodeur,Frederic Thomas
- 出版社/メーカー: Oxford Univ Pr
- 発売日: 2012/07/26
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログを見る
マレク・コーンによる英国の進化生物学者の考え方の系譜に関する本.私の書評はhttp://d.hatena.ne.jp/shorebird/20060331

A Reason for Everything: Darwinism and the English Imagination
- 作者: Marek Kohn
- 出版社/メーカー: Faber & Faber
- 発売日: 2005/09/01
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログ (1件) を見る
*1:何故可算名詞のcandleに冠詞が付いていないのかについては私にはよくわからない.もともともシェイクスピアにおいて無冠詞で使われているようだ.カール・セーガンはa candle in the darkと冠詞付きで用いている.シェイクスピアの頃は不可算名詞でありドーキンスがその古典的な響きを残そうとしているのか,それとも何らかの象徴的な意味があるのだろうか
*2:ディナーテーブルでのラテン語の乾杯の発声の蘊蓄とかいろいろスノッブ的で面白い
*3:行うように見えることを示したことで有名なリサーチ.ドーキンスは,これは自然淘汰の誤謬ではなくアセスメントコストに由来する制約なのだろうとコメントしている
*4:そのときは紫のネクタイだったそうだ.なお最近のドーキンスの派手な動物柄のネクタイは妻であるララの手書きだそうだ
*5:この講演が元になった本が「進化とは何か」というタイトルで日本でも刊行されている.
*6:結局手を挙げてくれたのは英国大使の娘だけだったそうだ.
*7:集合記念写真で撮影助手が全員をきちんと並ばせて姿勢と手を揃えさせようと躍起になっていたこと(よほど不思議だったのだろう).皇太子夫妻の前で緊張してスピーチしたことや,刺身や箸が苦手なことなどが語られている
*8:スペイン語翻訳版はドーキンスの元まで訳が悪いので出し直した方がいいという読者からの投書が届いたそうだ
*9:これは英国の知識人がよくやるお遊びのようだ.ここではSJグールドに対して密かに皮肉った索引「Gould, S. J., /five percent eye, 81, (quoted in 41) /five percent resemblance to turd, 82, (quoted in 41) /mentioned, 275, 291 /punctuated equilibrium, 229– 52, (36) /revealing faux pas, 244, (36) /revealing flaws, 91, (34) /writes off synthetic theory, 251, (35)」の2,5,6行目がそれぞれがアメリカ版で(グールドに気兼ねした出版社によって)「/on dung-mimicking insects, 82, (quoted in 41) /on Darwin’s gardualism, 244, (36) /The Panda’s Thumb, 91, (34)」に書き換えられた話がおかしい
*10:George W. Bush’s lurch towards theocracy: ブッシュ大統領は実際に「神が彼をしてイラクに侵攻させた」と言ったそうだ.
*11:あるときはBBCのシリーズでのディヴィッド・アッテンボローの声をオプラ・ウィンフリーが吹き替えたそうだ.ドーキンスはアメリカのアマゾンレビューでも圧倒的に原音声が支持されていることに安堵しつつ,そもそも何故オプラはこの仕事を受けたのだろうとコメントしている.
*12:アクセルロッドにハミルトンを紹介したのはドーキンス本人で,その顛末も語られている
*13:今ではかなりの部分はネットで視聴可能なのかもしれない.いずれここを読み直しながら検索してみようと思っている
*14:ドーキンスは刑事事件においてすらこの法律家スタイルが嫌いなようだ.アメリカの刑事弁護士が「依頼人の有罪の証拠を知ったときにどうするか」と聞かれ,「本人が無実を訴えているならそれに従ってその証拠は無視する」と答えたのにショックを受けたと述懐している.日本だと依頼人を説得して情状酌量の方向に持っていくというのが模範解答になるのだろうか
*15:シモニ自身がプログラマーであったこともあり,この話が「プログラム」になることにいたく乗り気になったそうだ
*16:なお当時ドーキンスはオックスフォードでまだReaderでありProfessorではなかったためにいろいろ細かなことがあったようだ.そのあたりのごたごたも英国風で面白い
*17:UCLAにダイアモンドを尋ねたところランチでもという話になって,指定された場所で待っていると,おんぼろのフォルクスワーゲンで現れて,近くの川沿いでピクニックランチになったそうだ.ゆっくり話ができて,さらにスイスアーミーナイフで切り取ったチーズとパンは最高だったそうだ
*18:この番組は私も見た憶えがある.私の記憶ではライアル・ワトソンの「生命潮流」を番組化した中にドーキンスが登場していたように思う.ワトソンの本自体はかなり曖昧なスピリチュアルな主張をおこなうものだったのでドーキンスの日本登場の舞台にはふさわしくなかったかもしれない
*19:なおここでは「ニッチ構築」について,それがその論者たちにあまりに曖昧に使われていることに苦言を呈している.ややお気に召さないらしい
*20:これは後にスパンドレル論文になる
*21:なおこのプログラムはMacOSのパスカルで書かれていたために動かなくなっていたが,最近アメリカのボランティアの手で復活し,入手できるようになっている.私も早速ダウンロードして遊んでみた.
*22:‘What if you’re wrong?’でググるとその動画に行き着ける.https://www.youtube.com/watch?v=6mmskXXetcg