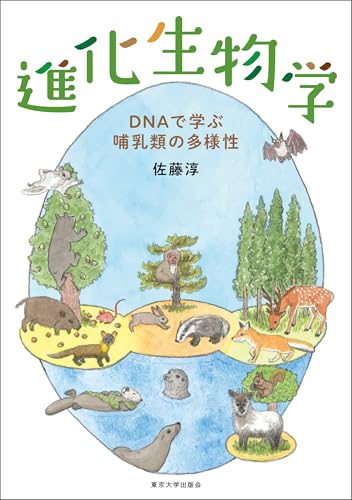本書は進化生物学者佐藤淳による一般向けの進化生物学の解説書.題名は「進化生物学」と大きいが,「DNAで学ぶ哺乳類の多様性」という副題にあるように基本的に哺乳類の分子系統解析や系統地理についての初学者向けの内容が書かれた一冊だ.
第1章 美しい島
冒頭は著者が北海道大学での修士課程終了後,瀬戸内海に面した福山に研究者として移り住んだ頃の心象風景から始まる.著者は美しい島々が点在する瀬戸内海と出合い,「瀬戸内海の島の生き物たちはどのような進化の道をたどってきたのか」という素朴な疑問を抱く.
そこから更新世以降の瀬戸内海の歴史(最終氷期には完全に陸地化,その後海水面上昇とともに内海が形成される.8000年前に古代の紀淡川流域,東予川流域が水没した東西からの海が中央で繋がった)が解説され,本章の登場生物であるアカネズミに焦点が当てられる.(ここでDNAによる系統解析についてかなり詳しく解説がある)
- アカネズミは日本固有種のネズミで,大陸の近縁種と600万年前に別れ,北海道,本州,四国,九州と周辺の島に生息している.瀬戸内海の島にも生息し,本州四国の系統と8000年(年1~2回繁殖で少なくとも8000世代)以上隔離されていることになる.
- 最初に行ったミトコンドリアの分析からはあまりはっきりした結果を得ることができなかったが,のちに核ゲノムをGRAD-Di法で一塩基多型の分析したところ,すべての島のアカネズミはそれぞれ1つのグループにまとまり,島間のアカネズミの類縁関係が明らかになった.それは東予川のかつての流路による分断から得られる予測と一致していた.
第2章 日本列島と進化
第2章のテーマは日本列島の哺乳類の生物地理.冒頭で自然淘汰と中立進化,その結果生じるハプロタイプ多様度と塩基多様度の状況,ニッチ重複と競争,そして種分化についての解説がある.ここでは例として堅果食のアカネズミとヒメネズミの関係が説明されており,(糞中の植物葉緑体DNAの検出により)北海道ではブナ科の堅果の不作年にヒメネズミの食性がブナ科から他の樹種により大きくシフトしており,ヒメネズミがアカネズミとの競争を避けていることが分かったことが紹介されている.
続いて日本列島の地史が語られる.日本列島の原型は1500〜1700万年前にユーラシアから離れて現在の位置に移動してきた.その後北東日本と南西日本がそれぞれ逆周りに回転して,500万年前ごろに今の配置となった(その間は一時海であったのであり,フォッサマグナはそれを示している).(津軽海峡を始めとするいくつかの隔離の歴史も語られている)ここから日本列島の哺乳類の生物地理が説明される.
- 日本列島は哺乳類相の違いから3つの生物地理学的区画(北海道/本州・四国・九州/琉球)に分けることができる.化石やDNAの分岐年代からこれらの区画の哺乳類の起源は琉球が最も古く,次に本州・四国・九州,そして北海道が一番新しい.これは海峡の深さに大きく影響された結果だ.(いくつかの分類群の状況が丁寧に説明されている)
- 本州区画のそれぞれの哺乳類が北から来たのか南から来たのかというのは面白い問題になる.ニホンテンは近縁グループとの分岐から見ると北由来に見える.
- ニホンザル,ニホンカモシカ,ムササビ,ニホンアナグマ,ツキノワグマ,ニホンイノシシなどは近縁種との分岐からみて南由来だろう.(ここで南由来に思えるモグラ類についての渡来経路と現在の分布の複雑な問題が説明される)
- アカギツネ,オコジョ,ヒグマ,ニホンジカなどは複数回の渡来(さらにニホンジカやアカギツネについての南と北両方からの渡来)が考えられる.
- ニホンテンは北由来と考えられるが,現在北海道に分布していない.このように渡来経路に現在存在しないという問題に対しては,競争排除などの理由により一部地域でいなくなったなどの説明が必要になる.(具体例がいろいろと説明されている)
第3章 進化の痕跡
第3章では第2章よりスケールの大きな哺乳類進化がテーマになる.冒頭で核遺伝子を利用した系統解析という技術革新が解説されたあと個別テーマが取り上げられている.個別テーマはレッサーパンダの系統解析,有胎盤類の初期分岐と4つのグループ,アナグマ類の系統解析,新無盲腸目の初期分岐になる.
- レッサーパンダの系統的な位置については180年以上混乱が続いていた.形態学の研究においては,アライグマと近縁,クマと近縁,独自系統などの様々な系統仮説があった.遺伝子解析が行われるようになってもなかなかその由来は明らかにならなかった.
- レッサーパンダはミャンマー北部,中国南西部,チベット,ネパール.インド北東部という限られた地域のみに分布し,西洋には1821年に報告された.これはジャイアントパンダの1869年よりも早い.どちらのパンダも竹を主食にしており手には偽の親指があると言う共通点を持つ(しかしこれらは収斂形質であったことがのちに明らかになる).
- 私たちのグループは核遺伝子を用いて系統解析を行い,レッサーパンダがイタチとアライグマに近縁な独自系統であることを示した.(系統的にはイヌ亜目>クマ下目(ここにクマ科がありジャイアントパンダが含まれる)>アザラシ(鰭脚類)とイタチ上科を含むグループ>イタチ上科となり,イタチ上科の中でまずスカンク科が分岐,次にレッサーパンダが分岐,最後にイタチ科とアライグマ科が分岐する) イタチ上科の中での分岐時期は始新世から漸新世への移り変わり直後と推定され,急激な寒冷化の環境変動が影響したと思われる.
- 哺乳類の分野における分子遺伝学的な系統解析の最大の成果の1つは,有胎盤類を4つのグループに分けることができたことだろう.これを示した論文は2001年にNature誌に掲載された.4つのグループとはアフリカ獣類,異節類,ローラシア獣類,真主齧類だ.この中では真主齧類とローラシア獣類が近縁(あわせて北方真獣類)ということはわかっているが,北方真獣類とアフリカ獣類と異節類の分岐順序はわかっていない.
- イタチ科の中ではアナグマの分類が論争になっていた.生態や形態から「アナグマ」と呼ばれる動物は世界中に少なくとも13種存在する.これらはかつてはアナグマ亜科としてまとめられていた.GGシンプソンは1945年にアナグマ亜科を認めながら,逡巡しているともとれるコメントを残している.
- その後形態学や遺伝学の研究からアナグマ亜科の単系統が否定され続け,アナグマの位置づけが論争となっていた.そして私たちのグループの研究も含めた分子系統解析によりアナグマ類が系統樹上の様々な場所に位置づけられることがわかってきた(私たちは2016年に総説論文をまとめた).
- 論争が長引いたのはそもそもイタチ科における亜科レベルの関係性が不明であったからだ.核遺伝子を分析することでこの論争に終止符を打つことができた.結果はイタチ科とスカンク科の中に5つのアナグマの系統が散在しているというものだ.イタチ科の亜科間の分岐は寒冷・乾燥化が進んだ中新世の中期から後期の500万年間に生じており,一種の適応放散であったようだ.一気に多様化が進んだ結果,様々な収斂が生じ,形態からは関係性がわかりにくくなっていたのだ.
- 2つの分岐がごく短い期間で生じたり,3分岐が生じたりした場合には,系統関係を示す情報がDNAに残らないことになる.このようなものはポリトミー(多分岐)と呼ばれる(前者はソフトポリトミー,後者はハードポリトミーと呼ばれる).環境の激変によるハードポリトミーと思われる哺乳類の例にはよく遭遇する.その例の1つとして真無盲腸類の初期の多様化を紹介する.
- 真無盲腸類にはハリネズミ科,トガリネズミ科,モグラ科,ソレノドン科の4つの科が存在する.この関係性についてはハリネズミ科とトガリネズミ科が近縁であること以外よくわかっていない.分岐年代についても論争があるが,私たちの分析では新生代になってからということが支持されている.
- 私たちはこの3グループの分岐を639個の超保存エレメント(UCE)を用いて分析した.639個のUCEで最尤法を用いて分析したが,異なる分岐を支持するUCEがほぼ同数で.合意が得られなかった.これは白亜期末の大絶滅ののちに新生代になって急速に多様化したためと考えることができる.(ハードポリトミーのもう1つの例として後期中新世のイタチ上科の分岐も解説されている)
第4章 退化の痕跡
第4章のテーマはゲノムに残された退化の痕跡.退化も進化に含まれることを断ったあとで,使われなくなった遺伝子がナンセンス突然変異やフレームシフト突然変異などにより壊れていくこと,そのような遺伝子は偽遺伝子と呼ばれることが解説され,ここから具体例が示される.
- 味覚は,味蕾にある受容性タンパクが味物質をキャッチし,その情報が神経に伝わることで生じる.近年5つの味覚にかかわる受容体遺伝子の塩基配列が決定され,どのような受容体がどのような遺伝子にコードされているのかが明らかになっている.たとえば旨味と甘味の受容体は3つの遺伝子(Tas1r1, Tas1r2, Tas1r3)が作るそれぞれのタンパク質のうち2つの組み合わせによる二量体として機能する(Tas1r1とTas1r3で旨味,Tas1r2とTas1r3で甘味).苦味受容体は1遺伝子で決まるが,それは多数あり,ヒトで25種類ほど知られている.これは多様な毒物への進化的対応の結果だろう.旨味,甘味,苦味受容体はGタンパク共役受容体だが,塩味と酸味受容体はイオンチャネル型の受容体になっている.
- 塩味に付いては脊椎動物の祖先の段階で獲得されたENaCという受容体が知られている,これは海から淡水,陸への進化史において浸透圧の異なる環境にいかに適応するかという点で,その機能が重要であったと考えられる.実際にクジラ類のほとんどの味覚受容体遺伝子は偽遺伝子化しているが,ENaCは機能を保っている.
- 2010年の論文でジャイアントパンダのTas1r1遺伝子にフレームシフトがあることが報告された.彼らは旨味の検出が出来なくなっている.そしてのちにレッサーパンダでも同じ遺伝子が偽遺伝子化していることが報告された.これをきっかけに私は哺乳類の味覚受容体遺伝子に興味を持つようになった.
- ネコはTas1r2が偽遺伝子化している.純粋な肉食になり甘味を感じる必要がなくなったと考えられる.吸血コウモリは旨味,甘味,多くの苦味の遺伝子が偽遺伝子化している.血液のみを摂取しているので食物選択の必要がないためと考えられる.
- 鳥類のゲノムにはTas1r2が消失している.だから彼らは基本的に甘味を感じられないはずだ.ハチドリなどの蜜を摂取する鳥がどうしているかを調べるとTas1r1とTas1r3がコードするタンパクを使って旨味ではなく甘味を検出していることがわかった.
- 鰭脚類ではTas1r1が偽遺伝子化している.これは海に進出して獲物を噛まずに飲み込むようになり,舌で味を感じる必要がなくなったためと考えられる.またアザラシ系統とアシカ系統ではこの偽遺伝子化が独立に生じている.(鰭脚類は単系統であり,それまで海への進出は共通祖先で1回生じたと考えられていたが)この発見はこの両系統で独立に海への進出が進化したことを示唆している.
第5章 テクノロジーと進化
第5章では著者が経験してきたゲノム分析テクノジーの驚嘆すべき進歩が語られている.ここではPCRとDNA解読技術が詳しく解説されている.
PCRについては概説の後,「なぜプライマーは狙った場所に結合してくれるのか?」についても解説がある(20塩基程度の一本鎖だけで1兆種類あり,片方でゲノムは数十億塩基程度のオーダーなので大体うまくいく).
DNA解読技術については,サンガー法のあらまし*1,シークエンス技術の革新と第2世代DNAシークエンサー*2が解説されている.
第6章 なぜ進化生物学を学ぶのか
第6章では著者の進化生物学に対する思いがエッセイ風に綴られている.子供の頃に自然に触れた経験の貴重さ,進化の視点が小学生にも生物多様性が持つ意味を魅力的に説明してくれること,大学生が進化生物学を学ぶことは,自分自身の理解,さらに生物多様性の喪失や気候変動にどう向き合っていくかを考えることに役立つであろうこと,進化は生物学にストーリーを与えることができること,昨今その研究がどう「役に立つか」が問われることが多いが,役に立つかどうかは今の社会にはわからないことが多いこと*3,著者自身の教育者としての自負として「進化生物学の知識と技術はこれからの役に立つ」と考えていることなどが書かれている.
以上が本書の内容になる.1〜4章までの瀬戸内海の地史と哺乳類の分岐進化,日本列島の哺乳類の進化史,パンダとアナグマの系統の謎,味覚受容体の退化と生態の部分は佐藤淳による自伝的研究物語として構成されており,哺乳類の多様性の魅力,その研究の面白さにフォーカスが当てられていて,読んでいて面白い.5章の技術解説は初学者向けにわかりやすいし.最後のエッセイにも味がある.進化生物学,特に哺乳類の系統や進化史に興味のある人には大変楽しい一冊に仕上がっていると思う.