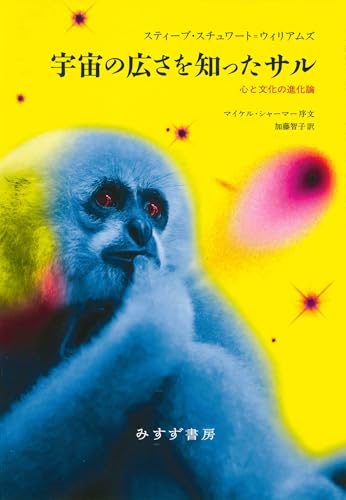本書は深野祐也による現在進行中で身近に観察できる進化現象を解説する一冊.深野は農学系の研究者だが,リサーチの対象範囲が進化生物学分野全体に広がり,目の付け所が鋭く一般市民にも興味深くわかりやすい研究を次々に発表していることで知られる.その中ではカタバミの都市環境における進化(これは本書第3章でも詳しく取り上げられている)や虫嫌いの進化心理的リサーチなどが有名だ.
第1章 これを読めば進化がわかる!
一般向け進化解説書の伝統にのっとり,冒頭には簡単な進化の解説がおかれている.進化とは何か,その中で自然淘汰による進化(適応進化)とは何か,適応進化が起こるための条件とは何か,適応進化にはどのような性質があるか,種分化はどのように生じるかが(架空の)タコ型生物の楽しいイラスト入りで解説されている.
第2章 進化は時としてあっという間に起こる
第2章ではまず進化が(一般人が通常考えているより)はるかに早く進むことがあることが指摘される.そして素早く適応進化が生じる条件(強い淘汰圧,世代時間の短さ),条件が満たされていれば素早い進化が生じることが予測できることが説明される.
例としては殺虫剤に対する耐性進化があげられ,進化が素早く生じることは予測できてもそれがどのようなメカニズムによるかは予測が難しいことも説明される.(ここでは実際に生じた耐性進化には,ナトリウムチャンネルの変化,殺虫剤分解,行動の変化などがあること,チャバネゴキブリはこれまで使用されたすべての殺虫剤に対する抵抗性を進化させ,さらに毒餌への誘引物質として使われる甘いものへの忌避まで進化させたことが紹介されている)
ここから様々な素早い進化の例が紹介される.有名な英国のオオフリシモエダシャクの工業暗化(さらに後の環境改善による再白化),トロフィーハンティングの淘汰圧に対して角が小さくなったオオツノヒツジ,メスの牙が無くなりつつあるアフリカゾウ,漁業淘汰圧によるタイセイヨウダラの体サイズの縮小と繁殖早熟化,同じくアトランティックサーモンの繁殖早熟化*1,漢方薬採集淘汰圧に対する薬用植物の変化(キク科の雪蓮花の小型化,ユリ科の一種のカモフラージュ的色彩変化)が取り上げられている.
第3章 都市で起こる進化
第3章のテーマは都市環境という新奇環境に対する様々な生物の進化.
冒頭は自身の研究であるカタバミの(通常の)緑葉タイプと(都市の高温環境に適応しているように見える)赤葉タイプのリサーチ.緑地環境と都市環境における両タイプの頻度比較,両タイプの高温ストレスに対する成長量や光合成活性の測定,DNA解析による赤葉タイプの(南関東での)進化史の推定*2,古文書からの証拠集め,iNaturalistを用いた世界中の都市における赤葉タイプ優占の検証などが語られている.
そこから様々な都市環境への進化例が紹介される.都市の夜間光環境への適応(フランスの蛾(スガ),アメリカのアメリカタバコガが都市環境で光に誘引されにくくなっている,日本の都市のオウトウショウジョウバエが夕方から夜明け前に活動時間を移している),都市の騒音への適応(世界中の複数の都市でシジュウカラの囀り音が高音にシフトしている.ただしこれが個体学習によるものか遺伝的進化によるものかは判別が難しい.ヒナバッタの鳴き方の高音シフト,高速道路下の鈴虫の一種マダラスズの鳴き声高音シフトは飼育実験により遺伝的進化であることがわかっている*3),都市環境の捕食圧低下に対する適応(シロツメクサの毒性低下が世界中の都市で並行進化している),都市環境の競争圧力低下に対する適応(都市のメヒシバ,オヒシバはより姿勢が低く横に広がる)などが解説され,この他にも強風環境,土壌環境(貧栄養,アルカリ化)などへの適応も生じているはずだとコメントされている.
第4章 外来種ももちろん進化する
第4章のテーマは外来種の進化.外来種はそれまでの環境と全く異なる環境下におかれるので急速に進化しやすい.
冒頭は自身のブタクサとブタクサハムシのリサーチ.日本には明治初期にブタクサが,戦後オオブタクサが北米から侵入し,瞬く間に全国に広がった.長い間両種には天敵がいなかったが,1996年ごろに原産地の天敵ブタクサハムシが侵入し,同じく瞬く間に全国に広がっている.深野は北米のブタクサ,日本のブタクサ,まだブタクサハムシが侵入していない日本の離島(対馬,壱岐,隠岐)のブタクサを比較し,天敵がいなかった日本ではブタクサの防御能力が下がり(トレードオフである競争力は上がる),ブタクサハムシ再侵入後防御力が上昇に転じていることを検証した.さらに北米ではブタクサハムシはオオブタクサを食べないが,日本侵入後は防御能力が下がったオオブタクサも食べるように急速に適応進化した(さらに日本の環境にあわせて休眠条件や顎の形状も適応進化している)ことも見いだした.
ここから,有名なハワイの(オーストラリアからの)外来エンマコオロギが(北米からの)外来寄生バエの寄生圧に対して鳴かなくなるように進化した例*4,オーストラリアに持ち込まれたオオヒキガエルの分布拡大速度上昇(移動傾向増大)を起こした進化および現地生物のオオヒキガエルの毒性に対する進化(忌避,耐毒性向上のほか,トビのオオヒキガエルの内蔵だけを食べる傾向,ヘビの小顔化(オオヒキガエルを飲み込めなくなる)などが知られている)が紹介され,さらに進化的知見の外来種管理への応用(拡大フェーズでは更なる適応進化を遅らせるために再侵入や在来種との交雑を防ぐこと,防除駆除フェーズでは駆除方策への対抗進化を予測して事業計画に入れ込むことなど)が語られている.
第5章 保全の現場で起こる進化
第5章のテーマは保全事業で生じる進化.
絶滅危惧種を動植物園で飼育して保全の一環とすることはよくある.ここでは動植物園で生じる進化として,動物の場合,捕食圧がないことなどの飼育環境への適応として鳴き声や動きの単純化,社会性の低下,警戒心の低下,視覚嗅覚の減退が生じること,植物の場合,不適切な季節における発芽を抑制する必要がなくなる環境への適応として種子休眠形質の喪失(これを防ぐためには飼育現場で早く発芽した個体ばかりを栽培せずに遅く発芽した個体も栽培すること,種子更新を遅らせて世代数を少なくすることなどが重要と指摘がある)がまず紹介される.
続いて(浮動についての簡単な解説の後)絶滅危惧種の集団が小さくなることによる浮動の影響(特に本来不利な形質の固定)の増大(これを防ぐためには他地域個体群の人為的な移入などの対策があり,「遺伝的救助」と呼ばれる),多様性喪失による近交弱勢の影響の増大など(これらの悪影響は,あわせて「絶滅の渦」と呼ばれる)が解説される.
遺伝的救助よりさらに踏み込んで進化理論を応用する試みは「進化的救助」と呼ばれる*5.ただし実行するにはいろいろ難しい点があることも指摘されている.
第6章 これからの進化を予測する
最終章は未来の生物の進化を想像を膨らませて語ってみようという楽しい試みになっている.
遠い未来の環境がどうなっているかの予測は難しいが,近未来なら気候変動(温暖化)の影響を考えることができる.ここではこれまでに生じた進化として,ミジンコの耐熱性上昇,シジュウカラの繁殖日程の早期化,植物の開花結実の早期化などがまず紹介され,(すべての生物が上手く進化できるとは限らないし,気候変動に対する進化は分からないことだらけであることを断った上で),気温の上昇(都市環境への適応がヒントになる),海洋の酸性化(プランクトンやサンゴが耐性を進化させる可能性がある),湖沼の富栄養化(プランクトンのアオコへの耐性進化,魚の派手な性淘汰装飾の喪失の可能性がある),マイクロプラスチックの増加(一部の生物にプラスチックを分解消化できる進化が生じる可能性がある)に対する進化の予想が語られている.
そして最後にヒトがこれからどう進化するかという話題(新興感染症に対する進化が継続して生じるだろう)にも触れ,さらにエピローグで(本章冒頭で難しいとしていた)遠い未来の進化を楽しく語って*6本書を終えている.
本書は身近に生じて観察可能な様々な素早い進化の例を次々に紹介する小気味のよい一冊だ.それぞれ大変わかりやすい解説がついており,楽しく読める.進化に興味のある人には嬉しい一冊だし,進化生物学学習の副読本としても充実した一冊と評したい.