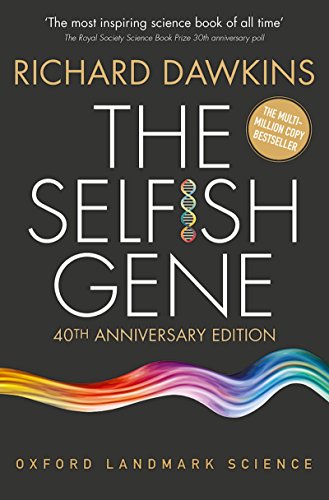本書はシリーズ群集生態学の一冊.既に2巻から6巻は10年以上前に刊行されており,本書は第1巻でありながら実質最終巻となる.なぜこんなに刊行が遅くなったのかと不思議に思いながらページをめくってみると,時間がかかるのも無理ないことが良く理解できるとんでもない労作だった.
このようなシリーズの場合,第1巻は入門編的な分野の概説書であることが多いが,本書は分野全体の勃興から今日までを描いた学説史になっており,どのようにこの分野が始まり,どんな仕事がなされ,どのような議論があったかを,一つ一つ原典の概要を紹介しながら解説がなされている.とにかくものすごい密度であり,この分野のことを知りたいならめちゃくちゃなお買得本になっている.私自身は,これまで群集生態学についてはところどころのトピックを囓っただけできちんと勉強したことがなく,一度分野の全体フレームを見透したいと思って購入したわけだが,あまりの密度に圧倒された一冊ということになる.
本書全体は5章構成になっており,19世紀から1970年代までの学説史,種間競争,群集の構造と機能(ネットワーク,相互作用,生態系),1950年代から1980年代までの群集の数理モデル,1980年代以降の群集生態学が扱われている.このあとに詳細に書かれたテクニカルなコラムが2つおかれており,群集の複雑性の指標(分布,指数,クラスター,座標など),他種系相互作用の解析法(パス解析,状態空間モデル,時系列解析など)が解説されている.
あまりに濃密な書物であり,その概要を簡単に示すことはとてもできないが,読んでいくと群集生態学がどのような問題意識から始まり,どのように進展していき,現在どこまで到達しているのかがわかってくる.それぞれの章で私的に興味深かったところを紹介しておこう.
第1章 群集生態学の成立
- 群集生態学は生物群集が形作るパターンを見いだし,それを生みだすメカニズムを解明する営みである.20世紀前半まではどのようなパターンがあるかの記述に止まっていたが,1950年代からその理論化が進んだ.当初の最も基本的な問題意識は,なぜ自然にはここまでの多様性があるのか(最も効率的な少数種による生態系にならないのはなぜか)というものだった.そしてまずそれは種間競争によるのではないかという群集平衡理論が発達した.
- 群集生態学に至る流れは,ダーウィンに始まる生物間の生存闘争を重視し,ニッチ,個体数変動,捕食者被食者相互作用などを捉える流れと,ビュフォンの植物地理学に始まる環境要因,植生遷移,類型を捉える流れの2つがある.
- 数理モデルに基盤をおく解析はロトカ,ヴォルテラ,ガウゼに始まる.これはロジスティック式,種間競争方程式を産みだし,実験により見いだされた競争排除則を説明可能にした.
- 生物群集をエネルギーの観点から説明しようとする試みは生態系の概念を生み,生態系の動的な変化と安定性,物質循環などが調べられた.
- 生物群集を個体群の動態と相互作用から説明しようとする試みは空間構造の重要性の認識(極相概念よりもギャップが重要)を生み,(それまでの平衡理論の枠組みを超えて)非平衡論から捕食や攪乱の重要性が指摘されるようになった.
第2章 競争と平衡の群集論の展開
- なぜ動物種はこんなにも多いのかという疑問はハッチンソンに競争と平衡による群集論の基礎を築かせた.それは種間競争がニッチを分化させるというアイデアを基本とする.この考え方は資源タイプごとの資源利用,資源競争の数理モデル化,ニッチ理論の一般化,それらの実証リサーチに発展した.さらにこの流れはギルド概念,ニッチの次元数などにつながる.
- 1970年代以降はこの競争と平衡の群集論の前提への批判がなされるようになり,平衡種と非平衡種の概念(これが後にr淘汰とK淘汰の概念に発達する),資源利用の速度と資源利用の効率,競争排除からの適応放散の説明,個体群や群集の時間動態の考察と動的平衡の概念,非平衡群集における環境変動の重要性などのリサーチにつながった.
- このようなリサーチにおいて,実証的には操作実験が行われるようになり,理論的には様々な数理モデルが組み立てられた.(ティルマンの資源利用モデルを用いたリサーチが詳しく紹介されている)
- 1970年代の終わりには攪乱の重要性が認識され,コンネルの中規模攪乱仮説が提出され,野外実証リサーチで検証されていった.
第3章 生物群集の構造と機能を通して群集生態学を振り返る
- 群集の構造と機能に関連した研究史は,ロトカの食物連鎖ネットワークから始まる.エルトンは生物のネットワーク,種のネットワーク,物質循環,エネルギー経路などを論じた.ハスケルは+,-,0で示される共作用理論を提唱し,共作用コンパスを描いた.ハッチンソンはこれらを数理的に解析しようと努め,オダム兄弟がこの仕事を受けて生態系のエネルギー流と代謝に関する体系化を進め,システム生態学を提唱した.
- そこでは「群集の多様性と安定性がどのような関係になっているか」(多様な生態系はより安定か?)が大きなテーマとなった.マッカーサーはシャノンの情報定理から多様な方が安定だと主張し,エルトンはそれを実証しようとした.メイはこの問題について群集の個体群動態が従う差分方程式の係数行列の固有値の問題として整理した.
第4章 1590年代から1980年代の生物群集の理論モデル
- ハッチンソンは逃亡種(競争には弱いが新たにできるパッチをいち早く専有する種)という概念を提案し,それはその後のメタ個体群理論における「競争と移住のトレードオフ」概念につながった.環境の時空間変動と群集動態については,スケラムやレヴィンズが数理モデルを構築し,メイによるロトカ-ヴォルテラ競争モデルの固有値分析は,ノイズの影響分析,マルコフ連鎖型の確率モデル,離散時間個体群動態モデルなどにつながった.
- 1970年代には3種以上の個体群からなる群集の数理モデルが吟味され,そこでは間接効果が重要であることやリミットサイクル,ヘテロクリニックサイクル,カオスなどの非線形効果が生じることが明らかになってきた.
- 群集食物網のネットワーク構造についてはコーエンが有向グラフとして表現し,スギハラは単体や回路などの概念を利用したネットワーク分析を行った.
第5章 1980年代鋼板からの群集生態学・生態系生態学
- 1980年代後半からは生物多様性と生態系機能や生態系サービスの関係が大きなテーマとなった.生産者(植物)の栄養段階の生物多様性が高いほど生産性が高いことは早くから明らかになっており,これを説明するためにニッチ相補性仮説(ニッチ分割が高度であるほど限られた資源を効率的に利用できる),選択効果仮説(多様であるほど生産性の高い種が含まれる可能性が高い)が提唱された.この両効果のどちらがどのような場合に優先するかについて多くの実証研究がなされた.
- このような実証研究は種数が群集全体の生物量の変動係数を減らし,「種間競争が生物量の種間の共分散を負にすることにより群集全体を安定化する」という主張につながり,これを検証しようとする数理モデル研究が始まった.ヒューズとラフガーデンは離散世代の2種のロトカ-ヴォルテラ競争モデルから始めて多種系に拡張し,限られた場合を除いて種数が群集全体の変動を減らす効果はないという結果を得た.アイヴズとヒューズは環境変動の影響を標準化した拡張モデルを作り,やはり種間競争が系を安定化させる効果は基本的にないという結果を得た.ロローとマザンクールは密度効果や確率的変動を加え,種間競争や環境変動への種によって異なる応答を導入したモデルを検討し,やはり競争が安定化に寄与するというアイデアを支持しないという結果を得ている.このテーマに沿った研究はその後も様々になされている.
- 生産者段階だけでなく「多栄養段階の群集において多様性が生態系機能を増加させる」というテーマについては21世紀に入って活発に研究されている.様々な生物群集について調べられた20年間の研究は基本的に生物多様性の増加が生態系機能に正の効果をもたらすことを明らかにしてきたとまとめられる.
- 生態系の多機能性についても21世紀に入って活発に研究されるようになった.単一機能の分析を足し合わせただけでは多機能の分析はできないことが明らかにされ,様々な生態系サービスが様々な要素と異なる関係を持つことがわかってきた.ソリヴェレスは9つの営業段階と類型化した生態系サービス群の関係を調べ,マイヤーは異なる機能間の相関構造を解析するために主成分分析により多機能性指数を算出した.デル・プラスはヨーロッパの森林において樹木の多様性と生態系の多機能性の関係が機能レベルによって異なることを見いだした.様々なリサーチの結果はレフチェックによりメタ解析されている.
- リーボルドとチェイスはニッチ概念を「種が存続できる環境条件とその種の個体の環境への効果」と再定義し,資源競争モデルに沿う形のゼロ純成長等傾斜線(ZNGI)とインパクトベクトルを用い,グラフと解析により複雑な相互作用を記述した.
- スチュワートとレヴィンスは2次元平面上にZNGI曲線を描いて資源競争における2種共存条件を吟味した.リーボルドとチェイスはこれを資源環境だけでなく捕食者やストレスを含むように拡張し,様々な2種共存条件を調べ「現代のニッチ理論」としてまとめた.
- チェソンはロトカ-ヴォルテラ型の競争モデルから2種の安定的共存条件を調べ,それを均一化機構と安定化機構により説明した.これは「現代の共存理論」と呼ばれる.この理論に関連する研究はさらに進展し,例えば2種共存は「侵入可能性」で議論できるが,3種以上になると侵入可能性だけでは議論できないことなどが明らかになっている.
- 食物網研究は限られたデータから始まったが,1980年代以降は標準化されたサンプリングにより集められた一貫した分類学的解像度を持つデータが求められるようになった.より詳細なデータを集めて調べると連鎖の長さやループの多さなど既往の理論の前提と異なる事実が明らかになる.1990年代以降はカスケードモデルの階層性を緩め,ループや共食いを許容するニッチモデル,入れ子階層モデル,一般化カスケードモデルなどが提唱され,活発にリサーチされた.コーエンはこれまで見逃されてきた生物の体サイズ要因が重要であることを見いだした.
- クライバーは測定結果から動物の代謝率は体重の(面積と体積の関係から予想される2/3ではなく)3/4乗に比例するという3/4乗側を提案し,それはウェストたちによって血管系や呼吸器系のフラクタル構造から説明された.この発見は生態ネットワークの生物エネルギーモデルにつながり,ニッチモデル型の食物網を持つ群集の安定性が調べられ,メイの結果が裏付けられた.
- また生物の群集の構造と動態を理解するために異なるネットワークの比較がなされ,食物網と相利系では安定性をもたらすネットワーク構造が異なることなどの知見が得られた.さらに層間にノードがある多層ネットワークにおける挙動が調べられている.
- メイによる固有値を用いた安定性解析は連続力学系だったが,これを離散力学系に拡張するリサーチもなされている.そこではレプリケータ方程式,統計力学などが応用されている.
- データ収集面ではDNAバーコーディングと次世代シーケンサーが手法の革新をもたらしつつある.また体サイズより広範囲な形質に着目したリサーチの流れもある.
以上ところどころのトピックを紹介した.これだけでもわかるように本書ではその勃興期から現代までの生物群集への学問的取り組みが大きなフレームワークの視点から提示されている.繰り返すようだが叙述はとにかく濃密だ.この分野をその分野的関心や歴史と共に通覧したいと考えるならまず読むべき本であるし,群集生態学に関連した話題がでたときにその背景を調べるためのレファレンスとしても手元に置いておきたい一冊だ.
シリーズ群集生態学
他巻は10年ほど前にすべて出されていて本巻の出版のみが遅れていた模様.