
- 作者: ニック・レーン,斉藤隆央
- 出版社/メーカー: みすず書房
- 発売日: 2007/12/22
- メディア: 単行本
- 購入: 4人 クリック: 88回
- この商品を含むブログ (32件) を見る
本書はミトコンドリアを軸に,いろいろな生物現象の謎を考えていこうという本で,同じくニック・レーンの前著「生と死の自然史」の続編ともいってよい内容だ.原題はPower, Sex, Suicideとなっているが,これは邦題の方がよいかもしれない.(「決めた」というのはちょっと気になるが)
最初に取り上げられる謎は,なぜ真核生物のみが多細胞生物となれたのかというものだ.
その前段としてそもそも「真核生物」とは何かと言うことが問題になる.真核生物の起源についてはそれまでの主流であったカヴァリエ=スミス説は,アーケゾアがミトコンドリアの祖先原核生物を摂食し,それが寄生となり,さらにエネルギー獲得を巡る共生に進化したというものだ.これに対して1990年代にビル・マーティンがとなえた水素仮説は,古細菌の一種メタン生成菌とα-プロテオバクテリアの水素提供に関する共生から真核生物が生まれたとするものだ.本書はこの説によっている.これは前著「生と死の自然史」で唱えられたシナリオの一部であり,より具体的に描かれている.
続いてミトコンドリアによるエネルギーの獲得の本質は何か.著者によるとすべての基本は膜の内側と外側のプロトンポンプによる電位差だという.これは呼吸と光合成に共通であり,酸化のエネルギーでポンプを回すのが呼吸,光のエネルギーで回せば光合成ということになる.
そしてではなぜ原核生物は大きく複雑になれないのか.細胞の淘汰圧はエネルギー効率と複製効率の世界だ.原核生物では栄養さえあれば複製する方が有利になる.そして細胞が巨大化する制約は呼吸効率にある.ミトコンドリアが内側にあれば細胞壁不要で膜の面積を稼げるので初めて呼吸効率が高いまま巨大化できるのだ.
では原核生物が内膜を進化させられなかったのはなぜか.呼吸を効率的に行うには,局所的な状況に応じた遺伝子発現が重要になる.ミトコンドリアなら,そこにある遺伝子を現場で活性化できるが,巨大細胞ではそのコントロールが難しいのだ.
さらに大型化するとエネルギー的には有利になるのかどうかが考察される.ここはやや議論が込み入っている.
まず代謝率と体重の冪乗則が取り上げられ,なぜ表面積と体積の関係2/3ではなく,言われているような3/4になるのかと問いかけ,実はそれほど単純ではないことを説明している.最終的に基礎代謝では0.75,最大代謝率なら全体で0.88.最大代謝は骨格筋でほぼ1,臓器ではもっと低い.多くの議論がなされているが,いずれにしても1より小さいと言うことは動物は大型の方が効率的だということになる.
次に内温性の問題を取り上げる.本書の依拠する考え方は内温性は有酸素運動能力を上げるための適応から生じたものだというものだ.その要素はスピードと持久力だ.まずスピードをつけるために最大代謝率を高くする.それは必然的に安静代謝率も上昇させる.なぜなら臓器のミトコンドリアを増やして,フリーラジカルを抑える必要があるからだと解釈している.アイドリング状態になって結果として内温性が獲得されたということになる.その後,獲得された内温性自体が有利になってさらに内温性のための適応が生じるというシナリオだ.
ここまで整理してから,真核生物のみが代謝的に有利な大型化できた理由を考える.結局大きな真核細胞のみが大きな核をもてる.そして大きな核をもてる動物のみが細胞間の分業による多細胞生物化ができたのだろうというのが本書の推測だ.この第一の問題に関する本書の説明は細部はなかなか複雑だが,大筋はわかりやすく説得的だ.要するにエネルギーを効率よく得るためには膜面積を持ち,そのそばに遺伝子発現できる仕組みが必要で,それはミトコンドリアによってのみ獲得できた.そしてそれが細胞の大型化,多細胞化に道を開いたというものだ.
次に2番目の問題,多細胞生物の細胞間コンフリクトにうつる.
ここでは前振りに,単細胞生物の世界ではドーキンスの「利己的遺伝子」説の評判がよくないことと,それが複製子と個体がほぼ一致している関係にあり,細胞単位で淘汰を考える方がわかりやすいためではないかというようなことがふれられている.本書の他の部分とはあまり関係のなさそうなことでもあり,本当は何を主張したいのかよくわからない部分だ.しかしマーギュリスがドーキンス嫌いだったというような話はエピソードとしては面白い.
続いてアポトーシスの仕組みとそれにミトコンドリアが重要な役割を占めていることについて解説が入る.アポトーシスの仕組みの骨格は,何らかの欠陥,理由によって細胞が分裂できなくなると細胞内でミトコンドリアのみ分裂をするために栄養不足になりフリーラジカルが過多になり,そしてそれがカスパーゼ連鎖反応に結びついて細胞がプログラム死するということになる.このカスパーゼ連鎖反応との結合の進化は独立に何度も生じているらしい.
続いて性の異型性について.
本書の異型性の説明はよくある説明とおなじだ.要するに細胞内オルガネルのコンフリクト抑制の理由から片方の性からのみミトコンドリアを入れるために異型性が大きくなったという説明だ.被子植物の雄しべの不稔性やヴォルバキアとミトコンドリアの差など興味深い話も交えながら語ってくれている.
面白いのはそのあとだ.上記異型性から接合子には2セットの核遺伝子と,1セットのミトコンドリアが混じることになる.ここでミトコンドリアと核遺伝子にいろいろな組み合わせの有利性の差があるとするなら,母親由来の核とミトコンドリアについて,卵母細胞から卵になるまでの間に組み合わせについて淘汰する仕組みがあるためにうまく働いているというものだ.
3番目の問題は前著でも詳しく取り上げられていた老化について.
著者の変わらぬ主張は,老化はフリーラジカルにより生じるものだということだ.フリーラジカルによるシグナルで,ミトコンドリア内遺伝子が呼吸鎖をより作ってフリーラジカルを抑制するフィードバックの仕組みにかかるいろいろ細かい議論がされている.前著より一歩進んで議論されているのは鳥とコウモリがより老化が遅い点について.本書はこれは鳥とコウモリが,より多くのミトコンドリアを持ち,より多くアイドリングをしているためによりフリーラジカルを抑えられるからではないかと推測している.そしてより多くアイドリングしているのは,究極の有酸素運動「飛翔」にかかる淘汰圧にかかる適応だというものだ.そして他の哺乳類でアイドリングを増やして長寿にならないのは,アイドリングにより何らかの効率が下がって,飛翔しない動物にとって逆に不利になるからだろうとしている.
この説明は非常に説得的だ.ハミルトンの老化にかかる議論などを読むと,個体にとって長寿になっても遺伝子の観点からの利益はほとんど無いことが明瞭だ.それを前提に考えるとアイドリングによりほんの少しでも何かの効率が下がるなら,何か大きなメリットがない限り高アイドリング状態は進化し得ないだろう.
全体を通して非常に濃密で粘着的な議論が続いている.論旨がわかりにくいところもあるが,それも著者の誠実性がそうさせているのだろう.個人的には多細胞化の議論はわかりやすくて買える.コンフリクトの議論はややミトコンドリアにこだわりすぎていてもう少し大きな視野から捉えた方がわかりやすいのではという感想.最後の老化についての部分は前著をさらに進めていて,特に鳥とコウモリの優れたミトコンドリア特性についての説明は前著に空いていた穴を埋めるものとして評価したい.読むなら前著とあわせて読まれることをお勧めする.
関連書籍
原書

- 作者: Nick Lane
- 出版社/メーカー: Oxford University Press (Japan) Ltd.
- 発売日: 2005/10/13
- メディア: ハードカバー
- クリック: 9回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
前著
酸素という観点から生命史と老化について語っている.私の書評はhttp://d.hatena.ne.jp/shorebird/20061104
いまよく見ると本書と出版社が異なっているようだ.

- 作者: ニックレーン,Nick Lane,西田睦,遠藤圭子
- 出版社/メーカー: 東海大学出版会
- 発売日: 2006/03/01
- メディア: 単行本
- 購入: 5人 クリック: 48回
- この商品を含むブログ (19件) を見る
その原書
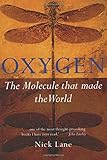
Oxygen: The Molecule That Made the World (Popular Science)
- 作者: Nick Lane
- 出版社/メーカー: Oxford Univ Pr
- 発売日: 2004/03/26
- メディア: ペーパーバック
- 購入: 3人 クリック: 6回
- この商品を含むブログ (3件) を見る