
- 作者: チャールズ・ダーウィン,堀伸夫,堀大才
- 出版社/メーカー: 槇書店
- 発売日: 1988/06/20
- メディア: 単行本
- クリック: 11回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
第6章 Difficulties on Theory
第6書からは自説の難点についての解説になる.冒頭でダーウィンは自説の難点として4点あげている.
第6章では最初の2つを取り上げている.
1. 種が祖先型から徐々に変化してきたのなら,なぜいたるところに無数の移行形が存在しないのか,あるいはきわめてまれなのか.そして世界は十分明確に分かれた種によって満たされているのか.
これは既に第4章で説明されている.ダーウィンは自然淘汰圧が主に生態的要因によるものであることから中間的な変種は絶滅することが多いのだろうと考察している.
さらにダーウィンはいくつか補強する議論も行っている.まず現在連続している地形も過去には不連続であった可能性があること,地形や気候が連続していても生態要因は不連続である場合があること,また広く分布した種の周辺域で変種から発端の種が生まれるとするなら,そのような移行形の個体は分布の周辺域に少数しか見られないはずであり,実際にそうなっていると指摘している.
(時系列で見たときには連続しているはずではないのかという疑問にについてはこれは化石の証拠が不完全であることを後の章で説明すると予告している.)
この問題は現在ではあまり議論されることはないが,こうやっていろいろな説明を読んでいると,なかなか面白い問題だということがわかる.恐らく非常に複雑な要因がたくさんあってこのような分布になっているのだろう.(だから実際に環状種などが存在する場合もあるわけだ)
2. 例えばコウモリのような特殊な形態や習性を持つ生物が,それを持たない生物から変化して生じたということがあり得るのか.眼のような完璧な構造を持つものが自然淘汰で作られうるものなのか.
これはドーキンスのいう「想像力の欠如による反論」というものだ.これがまさに種の起源の初版からあるというのも歴史を感じさせて面白い.
ダーウィンはいろいろな現象について想像できる中間形を示すという説明を行っている.陸生哺乳類から水生哺乳類にはカワウソの例を,コウモリについてはムササビやヒヨケザルをあげている.面白いのは現在不完全な飛行能力を持つトビウオからいつの日か完全な飛行能力を持つ魚類が現れる可能性があるとほのめかしているところだ.ダーウィンはそのような魚が現れれば,不完全な能力しかない移行形のトビウオは絶滅し飛行能力を持つ魚の系列には不連続が生じるだろうと説明している.
次に行動の進化についても考察している.ダーウィンはシジュウカラが様々な行動を示すことをあげ,続いてクロクマが空中の昆虫を捕らえるために口を大きく開けて何時間も泳ぐ観察例をあげて,将来これがクジラのようなものになるかもしれないとほのめかしている.眼についてもただ色素によって包被されているだけの視神経という状態から完全な眼まで様々な移行形を示している.想像力の欠如には想像力で対抗しているというところがなかなか面白い部分だ.
またダーウィンは適応が完全ではない例(樹上性でないキツツキ,着水しないグンカンチョウの水かきなどの様々な例が取り上げられている)を挙げて自然淘汰の証拠とする議論をここで行っていて興味深い.
なお本章のあとの部分でもダーウィンはこのテーマに戻って,適応が完全でないように見えるものの例として,ミツバチのワーカーは刺したあとに死んでしまうこと,ミツバチのワーカーが兄弟であるオスを多く殺すこと,女王バチが娘である若い女王バチと戦うこと,モミの木の花粉が必要以上に多いことなどをあげている.最初のものはなお適応が完全になっていないこと,次の2つは「community」の利益になっている適応と考えるべきであることとしているようである.最初のものはなかなか面白い論点だ.次の2つは事実誤認のような気もする.仮に事実だとしてなぜそのような形質が「community」の利益になると考えられるのかダーウィンは語ってくれていない.最後の例は個体の利益という視点からは完璧な適応であると思われ,珍しくダーウィンの考えに賛同できないところだ.
さらにダーウィンはここで,もし継続的な軽微な変化の累積によって説明できない器官が存在すれば,自分の説は崩れると自説の「反証可能性」を提示している.これもダーウィンの議論の誠実性を示している.そしてこのような変化の累積を考えるときには,適応目的は最初から最後まで同じである必要はないこともきちんと議論している.(ここではフジツボの負卵帯の細かな議論が出てきていかにもダーウィンらしい)これはいわゆる「前適応」とか「外適応」の議論だ.今から考えるとグールドとヴルバは何が主張したかったのだろう.
ダーウィンはこのような説明が難しいものの例として本章では魚の発電器官を取り上げている.
発電器官については移行形としては筋肉との関連をあげていてなかなか鋭い.ダーウィンが悩んでいたのは遠く離れた分類群にいくつか見られることについてだったようだ.ダーウィンはここでは相同と相似の違いを議論していて,発電器官は同じ適応課題について独立に進化した形質,つまり収斂ではないかという推測をしている.デンキナマズ,デンキウナギ,シビレエイの発電器官は実際に収斂進化によるものだということのようであるから,ダーウィンはここでも正しかったということになるだろう.
ダーウィンはここで,重要でないと思われる器官がなぜあるのかを議論している.これも大変面白い視点で,ダーウィンの思索の深さが感じられるところだ.ダーウィンはある器官や特性が重要かどうかを見極めるのはきわめて難しいことに注意を促した上で,過去の適応の産物が痕跡器官として残っている可能性,それが何らかの適応の副産物である可能性,性淘汰形質である可能性などを議論している,なおこの部分で既にダーウィンは人種差を性淘汰形質と考えていたことがわかる記述がある.
本章の最後では,先の相同と相似の議論について,相同は<型の一致>Unity of Type,相似は<生存条件>Conditions of Existenceであり,その要因はそれぞれ由来の共通unity of descent(つまり系統的な近縁性)と自然淘汰の原理 the principle of natural selectionに求められるとまとめられている.
なお「種の起源」第6版ではダーウィンは初版出版以降に寄せられた各種批判に反論する章を第7章として挿入している.
この各種批判はその大半がいわゆる「想像力の欠如による反論」であり,いかにこれが普通の人々にとって陥りやすいわなであるのかがよくわかる.
この第6版第7章では,まず長命が無条件に進化しないことを説明している.(ここもダーウィンの理解の深さが窺えるところだ)つづいて,一見有用でない形質については,本当に有用でないかどうかを判断するのは難しいことを説明したあと,第6章の議論に加えて,成長の相関,偶然的要素による変異などがあると補強している.その後,各種「想像力の欠如による反論」に対して反論するという構成を取っている.
この議論はマイヴァートが集約していたようで,ダーウィンはそれに一つ一つ丁寧に答えている.ここは読んでいてとても面白い.
<キリンの首が長いことについて>
マイヴァートはではなぜ首が長いのはキリンだけかと問い,ダーウィンはそのようなニッチがキリンにしめられていればその他の草食動物はそれとは異なるニッチに適応するからだと答えている.また別大陸に首の長い動物がいないのはなぜかと問われて,それはある歴史的事件が生じなかった理由を問うているのと同じであり,複雑な各種条件が満たされなかったとしか答えられない性質のものだと答えている.いずれも見事な反論振りだ.そもそもあることが生じなかったことを問題にするのはあまりフェアな議論ではないだろう.それでもコウモリやアザラシが島で陸生に戻らなかった理由について丁寧に答えているのにはダーウィンの粘着性が表れていて面白い.しかしさすがにヒト以外の動物が優れた知性を進化させなかった理由についてはまともに答えていない.ダーウィンの時代には脳のエネルギーコストがきわめて大きいことはあまり理解されていなかっただろう.
<ヒゲクジラのヒゲ>
ダーウィンはガチョウ,カモ,ハシビロガモのクチバシにあるフィルターの移行形を示しながら,クジラの場合もそれぞれ中間形は餌をとるのに有用であったはずで,クジラのヒゲが進化することを想像することに困難はないといっている.説明は大変細かい.
<ヒラメの眼>
ヒラメの眼が片側によっていく中間形に利益があったのかということについても議論している.
私は以前ヒラメの目の移行形にどんな利益があったのかについて疑問に思っていた.ダーウィンはいったん底に横になったあとで周囲を見ようとするときに身体をひねる必要があることを指摘している.残念ながらダーウィンはこのひねり運動による「用・不用」効果と自然淘汰の両方の働きがあるだろうと議論している.実際には途中の移行形態でもひねる量が少なくてすむことから自然淘汰が生じるに十分な利益があったのだろう.(眼には大きさと厚みがあるので底側の眼が上にずれた方がひねる量は少なくなる.ひねる量が少ない方が捕食者には見つかりにくいだろう)しかしこのようなところに利益があるかもしれないと思いつくということ自体脱帽せざるを得ない.なお最近まさに中間形の化石が発見されて話題になっているようだ.(参考http://www.sciencenews.org/view/generic/id/33976/title/A_wandering_eye)
<哺乳類の乳腺>
単孔類,有袋類,有胎盤類に見られる移行系列を示したあとで,これらの移行形態に少しずつ利益があることは疑えないとしている.
このほかに棘皮動物のハサミトゲ,コケムシ類の鳥頭体,振鞭体,よじのぼり植物の巻き付き運動,巻きひげ,ランの花粉塊,花柱の粘着性などについても同様の詳しい議論をしている.よじのぼり植物とランについてはそれぞれ一冊の本になっていて,ダーウィンが様々な批判に反論するために詳しく研究したことが想像される.
関連書籍
よじのぼり植物に関するダーウィンの本

- 作者: C.ダーウィン,渡辺仁
- 出版社/メーカー: 森北出版
- 発売日: 1991/11
- メディア: 単行本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
原書

The Movements and Habits of Climbing Plants
- 作者: Charles Darwin
- 出版社/メーカー: Univ Pr of the Pacific
- 発売日: 2001/03/01
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログ (1件) を見る
ランについてのダーウィンの本
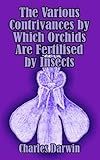
The Various Contrivances by Which Orchids Are Fertilised by Insects
- 作者: Charles Darwin
- 出版社/メーカー: Univ Pr of the Pacific
- 発売日: 2003/07/01
- メディア: ペーパーバック
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (3件) を見る