
- 作者: ピーター・ウォード,ジョゼフ・カーシュヴィンク
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2016/04/08
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
本書は地球環境と大進化のパターンについて探求している古生物学者ピーター・ウォードとスノーボール・アースを発見・提唱したことで知られる地球物理学者のジョゼフ・カーシェヴィンクによる地球史と生物進化史の関連を総説した本だ.環境条件については温度,大気成分(酸素,二酸化炭素,さらに硫化水素)が重要視されている.また大絶滅についても半数以上の大絶滅は隕石衝突ではなく温室効果絶滅であると論じていて読み応えがある.この分野ではニック・レーンが酸素濃度と進化について本を出しているし,ウォードの前著もやはりそれをテーマにしているが,より包括的に,そして全地球史的に扱っていて充実している.邦題は本書が生命の起源の謎解きにのみ焦点を絞っているような印象を与えるが*1,新しい視点から生命史全体を概説することが主眼の本だ.原題は「A New History of Life: The Radical New Discoveries about the Origins and Evolution of Life on Earth」
第1章 地質年代
冒頭で地質年代について簡単に解説がある.月や火星の地質年代区分,地質年代の役に立たない側面についての説明や,現状の命名規則の官僚的硬直性についての愚痴もあってちょっと面白い.最近の大きな改訂として原生代にクライオジュニアン紀(ギリシア語の「寒冷」と「誕生」からの造語.850〜635百万年前)とエディアカラ紀(エディアカラ動物化石の出土した丘陵名から命名.635〜542百万年前)が追加されたことについても背景説明されている.
第2章 地球の誕生 4600〜4500百万年前
1990年代以降,系外惑星の確認と火星由来隕石の生命の痕跡発見の主張の2つの出来事から「宇宙生物学」が勃興したとウォードたちは説明している*2.宇宙生物学ではどのような惑星に生命誕生が可能か,そしてどのような条件で現在の地球にいるような複雑な体制を持つ動植物が進化可能かをリサーチする.
ここから地球型惑星とは何か,火星や金星との違い,月を生んだジャイアントインパクト(4567百万年前*3)などが解説されている.また地球の大気成分の変化,炭素循環,気温の変化についての基礎科学や初期条件の推測についても詳しく解説されている.現在の初期大気成分のコンセンサスは,酸素はほとんどなく,二酸化炭素はかなり豊富にあっただろう(現在の1万倍以上の二酸化炭素圧があり,強烈な温室効果があっただろう)というものだ.炭素循環と気温については「惑星サーモスタット」の概念が重要だ.
二酸化炭素は火山から放出されて蓄積し,温室効果で気温を上昇させる.さらにそれは水蒸気を増やして温室効果をより強くする.気温が上昇すると化学的風化作用が活発になり,また雨に溶けた二酸化炭素と岩石中の成分が結合して大気から二酸化炭素を除去するようになり,温室効果が減少する.これにより気温が下がると風化速度は低下し,重炭酸イオンやシリカを成分とする生物骨格が沈殿する量が減ることにより火山から排出される二酸化炭素量も減り,さらに温室効果は減少する.寒冷化すると海洋表層や珊瑚礁の面積も減り,生物が必要とする二酸化炭素量も減るために,大気から二酸化炭素が固定化される量が減り,最終的には火山からの二酸化炭素排出量の方が大きくなる.そして新しい炭素循環サイクルが始まる.
また大気成分,炭素,気温には植生の様相や大陸移動(大陸の大きさと配置)も関連する.中でも生命の歴史に大きな影響を与えるのは酸素と二酸化炭素の量(そして硫化水素とメタンはそれに次いで重要になる)になることが解説されている.
第3章 生命の定義
ここで著者たちは「生きていること」と「死んでいること」の違い,その中間領域,生命の定義,ウィルスは生物かなどにこだわっていろいろと議論している.私としては生死や生命についてはリサーチしたいことによって操作的に定義しておけば十分ではないかと感じるので,やや退屈な部分になっている.とはいえこだわる人には面白いだろう.
第4章 生命の誕生 4200〜3500百万年前
火星の生命の話を前振りにして,最古の生命の痕跡は何かという話題が取り上げられる.教科書にも取り上げられているイスアの燐灰石の炭素同位体比(3850百万年前)は最近の計測で生命由来でないことがわかった.その他にも論争中の化石もあるが,現在最も確からしいのは3400百万年前のエイペクスから出たバクテリアの化石だそうだ.
ここから生命の誕生をめぐる考察になる.基本はRNAワールド仮説に依拠し,その最初のRNA生物の起源として,ヴェヒタースホイザーの熱水噴出口の硫化鉄ワールド説,ウーズの大気中の小滴の中のメタン代謝仮説,そして著者の1人カーシェヴィンクの火星の湖沼起源生物が隕石により運ばれたという説を取り上げ,(当然ながら)火星由来説について詳しく解説している.
またここでは進化の起源も取り扱っている.著者たちは進化は細胞の仕組みが一時的なものから恒久的なものに変わる段階をダーウィン境界と呼びそれ以降自然淘汰が生命史を形作った(それ以前は化学的な作用によるもの)だと考えているようだ.ここはやや納得できない.細胞の形成よりも(ドーキンスがいうように)自己複製の開始こそが究極的に重要で,それ以降はすべて自然淘汰と扱うべきであるように思う.
第5章 酸素 3500百万年前〜2000百万年前
冒頭でストロマトライトについては従前藻類のマットと考えられてきたが,それだけではないかもしれないという話を振ってから,本書の大きなテーマ酸素濃度の話に移っている.
先カンブリア時代は,現在冥王代,始生代,原生代に区分される.始生代から原生代への移行は約2500百万年前で,この頃酸素濃度が急上昇する.この経緯について本書では,メタンを利用する微生物,縞状鉄鉱石の謎,紫外線にかかわる光化学反応と酸素ワクチン,そして真打ちのシアノバクテリアの登場などの様々な話を積み上げて解説している.特にシアノバクテリアによる酸素発生型光合成の起源については,以前堆積岩コアのデータから2700百万年前とされていたのが最近コンタミの疑いから否定され,より若い年代(2400百万年前)に修正された経緯,「その当時はなおシアノバクテリアは酸素発生型光合成を行っておらず,水中の還元マンガンを利用した光合成を行っていた(これにより地層に酸化マンガンが大量にあるが酸素濃度はそれほど高くなかったことが説明できる)が,水中のマンガンを使い果たして2350百万年前までに酸素発生型に切り替えた」という著者たちの仮説などにも触れていて詳しい.
続いてスノーボールアースが取り上げられる.ここは提唱者でもある著者が学説史的も詳しく語っていて迫力がある.1950年代に先カンブリア時代に低緯度地域も氷結したことがあったと主張されたが,プレートテクトニクスの受容により一旦忘れ去られた.そして1980年代の後半からもう一度証拠が吟味され,1990年代にスノーボールアース仮説として提唱され,そして様々な証拠から受け入れられる.またそのメカニズムも詳しく説明がある.最古のスノーボールアースは2400百万年前ごろで,最長100百万年前ほど続いた可能性もある.またここでは2回目のスノーボールアース(717百万年前ごろ)も取り上げられている.
なお結局本章にはこの時期の酸素濃度の変遷の全体像については順序だった説明がなく大変わかりにくい.別の章にあるグラフも参照して著者たちの考えをまとめると以下のようになる.
3800百万年前までには嫌気性光合成が始まる.大気に酸素がない状態が継続する.その後2400百万年前までに酸素発生型光合成が始まり,酸素濃度を(5%程度に)上昇,温室効果ガスを減少させ,第1回目のスノーボールアースを引き起こす.これにより酸素濃度は下がる.スノーボールアースから回復後,光合成が活発になり酸素濃度が急上昇する.まだ呼吸する生物がいないので酸素濃度は一旦極めて高く(おそらく20%以上に)なる.2000百万年前呼吸型生物(ミトコンドリアの祖先たるバクテリア)により急激に酸素濃度は低下し2%以下となり,次のスノーボール期まで低酸素状態が続く.
第6章 2000百万年前〜1000百万年前
この時期海中には硫黄が存在し,(硫黄代謝型の方が容易であるため)最上部の薄い層以外では硫黄代謝型のエネルギー生物が優勢となり,大気中に酸素はあまり放出されない状態が続いた.しかし10億年以上経過し,大陸面積が広がり,海に流れ込む鉄が増え,硫黄と反応して沈殿していき,最後には酸素放出型光合成が優勢になった.
著者たちはこの低酸素の10億年間の生物史について,グリパニア(細胞が膜組織でつながっており初めての多細胞生物であると評価できる),アクリターク(トゲを持つ微化石)などを取り上げて解説している.いずれもあまりなじみのない生物で面白い.
第7章 スノーボールアースとエディアカラ生物群 850百万年前〜635百万年前
717百万年前から635百万年前の間に地球は再びスノーボールアースとなり前後2回凍結する.原因はなお論争中だが,著者たちは大陸移動による大陸配置の変化を重要視している.凍結の時期にバイオマスは極めて小さくなり,融氷後に藻類の爆発的な増加を生みだして酸素濃度を押し上げる効果を持った.
著者たちは635百万年前のスノーボールアースの終了とエディアカラ生物群の唐突な出現を結びつけようと,ボトルネック効果を持ちだし,さらに分子年代では後成動物のいくつかのグループの分岐年代がより古そうなことに対して「この気候の大変動が大規模な遺伝子置換につながった可能性がある」と主張しているが,やや苦しいのではないかという印象だ.
ここからのエディアカラ生物群の解説は楽しい.発見・報告の経緯,泥岩や頁岩ではなく砂岩に保存されているという謎(著者たちは微生物の薄いシートが形成されて安定したのではないかという説を主張している),エディアカラ紀の細分,いくつかの化石群集の特徴,生態系について推測できること(捕食者がいないことが大きな特徴になる),トゲの生えた微化石の謎,左右相称動物出現の意味(運動と地層の生物擾乱の開始であり,酸素濃度が高くなったことにより初めて可能になったと考えられる)などが扱われている.
第8章 カンブリア爆発 600百万年前〜500百万年前
カンブリア紀に突然複雑な動物の化石が現れ始めることにダーウィンが困惑していたという逸話を前振りにしてから,カンブリア爆発について詳しく解説がある.著者たちの整理によると複雑な体制の動物群の岩石中への発現パターンには4つの波がある.
- 575百万年前:エディアカラ動物群のアヴァロン爆発
- 560〜550百万年前:膨大な生痕化石が現れ始める
- 540百万年前:おびただしい微細な骨格要素の発現
- 530〜520百万年前:三葉虫や腕足動物などの大型の化石動物の登場(カンブリア爆発)
カンブリア爆発当時の酸素濃度は13%程度,二酸化炭素濃度は現在の数百倍,温室効果から気温も高かっただろうと推測されている.ここから著者たちは,チェンジャン化石,バージェス化石,量的にはどのような動物群が多かったのかを解説し,鰓を持つ体節が繰り返されている節足動物,鰓面積増加適応が見られる腕足動物が多いことは当時の低酸素から説明できるとしている.
さらにエボデボを簡単に説明して節足動物の急速な体制の変化は容易に説明できることを強調し,カンブリア爆発の様相をめぐるグールドとコンウェイ=モリスの間の論争を扱い,大方の見方はグールドの負けであるとまとめている.
カンブリア紀の年代決定についてのいかにも専門家的な論争を扱った後で,真の極移動とそれが進化史に与えた影響(気温が直接進化速度に影響を与えたことが前提になっており,やや微妙な印象だが,極移動の詳細は面白い),さらにカンブリア期末の絶滅の解説がある.著者たちの解説によるとこのときの絶滅はほかの大絶滅期とかなり異なっており,海底への有機物の大規模な埋没と酸素濃度の急上昇が起きている.これは炭素循環の攪乱を意味しており,著者たちはこれも真の極移動が生じたためだと主張している.ここはこれまであまり紹介されていないところであり,大変興味深い記述になっている.
第9章 オルドビス紀とデボン紀 500百万年前〜360百万年前
オルドビス紀に入って生物界はカンブリア爆発よりさらに大規模な多様化を示す.著者たちはこの多様化はカンブリア爆発が土台になっているとし,水爆起動のための核分裂とその本体である核融合に例えている.そしてその生態的なキーになったのは珊瑚礁の形成であり,さらに酸素濃度の上昇が重要だったと指摘している.
ここで著者たちは古生物の多様性の研究史を簡単に振り返っている.それは19世紀のフィリップスに始まり,20世紀後半にニューウェルとヴァレンタインが再検討を始め,ラウプとセプコフスキー,さらにマーシャルとアルロイにつながる.議論のポイントは生物は多様化し続けているのかどうかであり,問題になったのは化石記録のバイアスについての統計的な検討だった.
様々な検討の結果,多様性は,大絶滅とその直後の多様性回復を繰り返しながら,大きな傾向としてはオルドビス紀から中生代中期まで一旦頭打ちになり,中生代中期以降は増加傾向を見せていることがわかった.著者たちは多様性パターンの変遷には大気成分(二酸化炭素濃度と酸素濃度)が関連しているのだと主張している.低酸素高二酸化炭素時期には,生物にとって厳しい環境となるから絶滅率が高まる反面,斬新な新機軸が進化し,その後の高酸素濃度期に一気に花開くというパターンになるというのだ.環境だけにそれほど依存するとすれば驚きだが,強い統計的な支持があると著者たちは自信たっぷりだ.なかなか興味深いところだろう.
最後にオルドビス紀末の大絶滅(いわゆるビッグ5の第1回目)が論じられている.この大絶滅の原因はまだわかっていない.著者たちは(その原因はなお不明だが)小氷期に入って珊瑚礁が死滅したのではないかとコメントしている.
第10章 生物の陸上進出 475百万年前〜300百万年前
ティクターリク化石の発見が一つのミッシングリンクを埋めるものだったというちょっと煽り気味の前振りから,いろいろな上陸物語を取り扱う.
最初は植物.単細胞の光合成生物の上陸はかなり以前であった(最古の主張は26億年前まである)と考える学者が増えている.著者たちは7億年前頃に植物が上陸したと考え,最後のスノーボールアースの原因が植物の上陸であった可能性を示唆する.上陸後475百万年前には様々な構造が進化し始める.維管束植物の最古の化石は425百万年前だ.390〜380百万年前ごろ葉が出現し,370〜360百万年前ごろには8メートルを超す樹木の化石が現れる.植物は地形と土壌を変え,砂塵を減少させ,大気を澄み渡らせた.デボン紀(359〜299百万年前)後期には森林が陸地をほぼ覆い尽くすようになる.
著者たちはここで,乾燥に対して体内の水分を保持することと二酸化炭素の吸収・高温時の冷却の間にトレードオフがあり,高二酸化炭素・高温時には気孔が少なくても対処できるので葉は進化しないが,一旦植物が増え始めると土壌形成や根の作用による化学的風化作用により二酸化炭素濃度が低下し,それによる温室効果ガスの減少により気温が下がり,気孔を増やして葉が進化することが可能になったのだと説明する.
続いて動物が何度かに分かれて上陸を果たす.通常は植物進出により陸上に動物が利用できる資源が蓄積したことを重要視するが,著者たちはここではオルドビス紀からシルル紀にかけての酸素濃度の上昇と呼吸のための体制の有無がポイントだったと指摘している.(添付されたグラフによるとオルドビス紀からシルル紀初期にかけて酸素濃度は15%程度から25%程度に上昇する.その後シルル紀後期に17%程度まで下がり,デボン紀に増加傾向になりデボン紀後期から石炭紀に30%程度でピークをつける.そこからジュラ紀にかけて低下傾向になり,一旦15%程度まで下がる.その後白亜紀以降は20%程度に回復している)
最初の陸上進出はシルル紀後期かデボン紀初期(約4億年前ごろ)の節足動物で,すべての体節に鰓を持っていたり,クモやサソリのような書肺を進化させた動物だった.昆虫の適応放散は330〜310百万年前ごろだ.この2つの時期の間には酸素濃度が下がっていた時期があり,それが脊椎動物も含めて陸上進出に2つの波があるように見える理由ではないかと著者たちは議論している..
脊椎動物の上陸については,まずデボン紀の魚類相を概観し,淡水に棲む総鰭類から両生類が分岐したこと,化石が現れる時期は酸素急低下時期(400〜360百万年前)だが,実際の上陸は上記第一波の高酸素時期(400百万年前頃)だっただろうと説明する.そして一旦酸素濃度が低下し大量絶滅が生じ,さらにその後上記第二波の酸素濃度上昇とともに両生類は適応放散する.
第11章 節足動物の時代 350百万年前〜252百万年前
主に石炭紀からペルム紀の高酸素濃度時期(330〜260百万年前)を扱う.この時代に昆虫をはじめとする節足動物の一部は巨大化する.これは節足動物の身体の大きさの限界が呼吸効率で決まっているためだとして説明できる.大気中に酸素分子が多いために大気圧自体も高くなり,巨大トンボが進化できたのは揚力がより得やすかったためでもあると著者たちは解説している.
高酸素状態になったのは,石炭紀に大規模に石炭鉱床が形成されたうえに海におけるプランクトン埋没も多く,大量の有機物が地中に埋没されたためであり,さらにさかのぼれば,それは大陸が合体して巨大山脈が形成されて氾濫原の面積が増大したためだ.また著者たちはこの時代には樹木の有機物を分解できるバクテリアがいなかった可能性もあると指摘している.
著者たちは陸上での卵の水分保持と呼吸のトレードオフ状況から.脊椎動物はこの高酸素状態の中で初めて羊膜卵を進化させることができたと指摘し,またこの結果卵生が容易になって胎生の進化は低酸素状態を待たなければならなかっただろうと議論している.またこの時代の爬虫類はまだ呼吸と移動運動を同時にできなかった(この状態に対する適応が三室心臓だとも指摘している)ので高酸素状態によって初めて繁栄できただろうともコメントしている.
このほか爬虫類の分岐*4,内温性の進化なども高酸素濃度と関連させていろいろ考察している.本書の読みどころの1つだろう.
第12章 ペルム紀末の大絶滅 252百万年前〜250百万年前
ペルム紀末の大絶滅.これは史上最大の大絶滅で,回復が大幅に遅れたという特徴を持つ.著者たちはこの絶滅は開始から数百万年間続いたようであるとしている.そして当然ながらこの時期に急低下した酸素濃度を問題視する.
ここからこの大絶滅の原因が扱われる.シベリア洪水玄武岩説,隕石衝突説,隕石衝突説の最新版のバックミンスターフラーレン証拠説とその破綻を 簡単に解説した後,著者たちはカンプたちの温室効果絶滅説を好意的に紹介する.これは海洋が低酸素状態だったために深海の硫化水素がある閾値を超えて急速にかつ大量に海面に上昇し,オゾン層を破壊するとともに温暖化が著しく増幅されたというものだ.気候モデルによってこの時期に何度もこのような硫化水素の大量上昇が生じ得ることも示された.
著者たちは,酸素濃度の急低下によって生物の生息可能地域が縮小したこと(標高圧縮),海洋において硫化水素により動物プランクトンが絶滅する中で植物プランクトンのみ成長しその死骸が海底に沈んで最後に残ったわずかな酸素を使い尽くしたことなども絶滅規模の拡大の要因となっただろうと補足している.
これまではペルム紀末の絶滅原因についてはなおよくわかっていないとするものが多かったが,本書はそこへ踏み込んでいて,この温室効果絶滅の解説は(この後の三畳紀末絶滅,暁新世末絶滅の説明と並んで)なかなか説得的だ.ただなぜそもそも酸素濃度が大きく低下したのかにはあまり触れておらず,ちょっと残念だ.
第13章 三畳紀爆発 252百万年前〜200百万年前
ペルム紀末の大絶滅が温室効果絶滅であった余波として,三畳紀初期は高温の時代だった*5.そして大絶滅後当然ながら大放散の時代になる.著者たちは絶滅後の膨大なニッチの出現以外に当時低酸素状態であったこと(そしてそのような過酷な環境下でいろいろな新機軸が進化すること)を大放散の要因として強調している.
生物相の解説としては,二枚貝,アンモナイトの多様化を扱った後,爬虫類相を詳しく解説している.低酸素環境で様々な爬虫類が生まれたが,身体は大きくならず,また海に帰っていったものも多かった.新機軸としては移動運動と呼吸の両立のための二足歩行や二次口蓋と直立が重要で,著者たちは後の恐竜と哺乳類の基礎はこの低酸素時代に作られていると強調している.
最後に三畳紀末の絶滅が扱われる.オルセンはこの時期のイリジウムを見つけて隕石衝突説を唱えたが,著者たちはこのイリジウムは量的に少なすぎるとして却下し,やはり低酸素状態,そして高二酸化炭素状態であったことからこの絶滅も温室効果絶滅だと主張している.そして陸生脊椎動物群では簡単な構造の肺を持つものがより多く絶滅していることを傍証としてあげている.
第14章 低酸素世界における恐竜の覇権 230百万年前〜180百万年前
ジュラ紀は低酸素環境から酸素濃度が急上昇し,陸上脊椎動物では恐竜類が繁栄し,大型化していく時代だ.本書ではこの関連について濃密に考察されており,本書の最も充実した部分の1つになっている.
恐竜(特に竜盤類)は三畳紀の低酸素環境下で効率よい呼吸と運動システム(隔壁式肺と気嚢,二足歩行)を進化させて,ジュラ紀を通じて繁栄し,酸素濃度の上昇とともに大型化する(おそらく気嚢を持っていなかった鳥盤類は最後の高酸素時代に初めて多様化と大型化を果たす).本書ではさらに三畳紀から白亜紀までの時代ごとの恐竜類の栄枯衰退,鳥類の進化,卵と酸素濃度の関係(低酸素高温環境では胎生と柔らかい卵殻が有利で,その後酸素濃度上昇とともに炭酸カルシウムの硬い卵殻を持つ卵が有利になる)などが議論されている.
第15章 温室化した海 200百万年前〜65百万年前
ここではジュラ紀と白亜紀の海がテーマだ.これはあまり解説されないところで本書の魅力の1つだろう.
高温の水は酸素含有量が下がる.そしてこの頃の海はラグーン面積が大きく,サンゴではなく厚歯二枚貝による大規模な礁が広がっていた.そこでは溶存酸素量が少ない環境に適応した生物(アンモナイトとイノセラムスという二枚貝)が繁栄する.ウォードの専門領域ともあってアンモナイトの解説は詳しい.アンモナイトの隔壁や縫合線を持つ体制は低酸素環境への適応として非常にうまく説明できる*6.
続いてヴァーメイによる「中生代海洋大変革」の概念が解説される.これは海の捕食者が固い殻を割れるように進化したことをきっかけにした生物相の変化を指す.最初は石灰石の甲冑が強化され,その後貝類や棘皮動物が深い穴を掘って潜り込むようになり,殻や微少な骨格を持つ有孔虫,放散虫,円石藻類が繁栄する.カニやロブスターの進化(防御の強化と呼吸効率の向上)もこの環境への適応だと説明されている.
第16章 恐竜の死 65百万年前
白亜紀末の大絶滅.激変説と斉一説の学説史を背景にアルヴァレスたちの隕石衝突説の登場とそれが受け入れられる経緯を簡単に解説する.著者たちは,この絶滅について隕石衝突が最大のインパクトになっているのは間違いないが,アンモナイト絶滅より少し前にいろいろな場所で異なるタイミングでイノセラムスが絶滅していることから,大絶滅の直前に,まず寒冷化と高酸素海水の沈み込みによる絶滅,そしてもう一回デカントラップによる温室効果絶滅があったという見解を採っている.
第17章 哺乳類時代 65百万年前〜50百万年前
哺乳類の適応放散は新生代に生じるが,まずその前史についていくつか指摘がある.著者たちは,有袋類と有胎盤類の分岐は恐竜絶滅のはるか前の175百万年前頃で,有胎盤類の主要な分類群の起源も少なくとも100百万年前には既に生じていることを指摘し,化石から見て初期の分岐は南の大陸で生じており進化の波は南から北へ向かったのだろうと説明している.
また著者たちは,恐竜絶滅後暁新世に哺乳類は放散するが,大型化は気温が上昇する数百万年後を待たなければならなかったと指摘している.
最後に暁新世末期の絶滅が扱われる.著者たちはこの大絶滅はメタンを原因にする温室効果絶滅だと主張している.この時期の温暖化は極地方の海水温の顕著な上昇が特徴で,底生有孔虫の大規模絶滅を引き起こしている.また詳しく見ると陸上哺乳類相も大きく入れ替わっていて,現在の哺乳類相(偶蹄類,奇蹄類,食肉類など)はこの絶滅によって形成されたものだとわかるとしている.
またここでは始新世から中新世にかけての寒冷化と植物相の関係(C4植物は,この時期の寒冷化および二酸化炭素濃度の低適応して多くの植物群で独立に進化している.また乾燥による森林火事の増加はイネ科植物を有利にした)を議論している.C4植物は光合成効率が高いが,それは一方的に有利なのではなくトレードオフを持ち,二酸化炭素濃度に応じて有利性が変化するというわけだ.なかなか面白い.
第18章 鳥類の時代 50百万年前〜2.5百万年前
本章の章題は子供向けなどの時代区分で「両生類の時代」「爬虫類の時代(恐竜の時代)」「哺乳類の時代」という言い方がされるが,「鳥類の時代」がないこと(正確にはこれらの言い方が不適切であること)についてのちょっとした当てこすりでもある.実際にここはまず鳥類の起源論争が扱われ,恐竜起源説の圧倒的な証拠を眺め,白亜紀末絶滅を乗り切った古顎類の適応放散,その結果の分岐系統樹を見る.また新生代の恐鳥類も同時に扱っていてスコープは広い.
第19章 人類と10度目の絶滅 2.5百万年前〜現在
本書ではビッグ5(オルドビス紀末,デボン紀末,ペルム紀末,三畳紀末,白亜紀末)以外に大酸化事変,クライオジェニアン紀,エディアカラ後期,カンブリア後期,更新世〜完新世の5つを加えて10大絶滅としている.そしてこの章のテーマは人類の登場と現在進行中の大絶滅だ.
人類進化の解説は,性的二型,直立歩行,地理的な拡散などを扱っているが,著者たちの専門と少し離れる部分でさすがにやや浅くて物足りない.逆に更新世の気候の特徴(氷期と間氷期のインターバル複雑な要因が絡んでおり一定しない.これにより現在の間氷期はなお数万年続いてもおかしくないそうだ)については詳しくて読ませる.そして人類は拡散した先で大型哺乳類を次々に絶滅に追い込み,生態系に大きな影響を与え.現在のインパクトは植物や鳥類や昆虫に移りつつあると指摘されている.
第20章 地球生命の把握可能な未来
冒頭で進化は生物同士の相互作用だけでなく大気や海の物理的な変化にも影響されることがもう一度強調される.そして長期的に見ると,二酸化炭素濃度は下がり続け温室効果は下がっていくが,太陽が明るくなり続ける影響はこれをはるかに上回り,5〜10億年後には,これまで温室効果の際に効いていたサーモスタットが機能しなくなり,地球はハビタブルゾーンから外れて金星のような星になること,二酸化炭素濃度の減少はやはり5〜10億年後には植物の光合成を不可能にすること,植物がなくなると土壌は失われ砂塵の惑星になり,河川は網状になることなどが解説されている.
最後に著者たちは人類の将来的な進化についてエッセイ風に語り,5〜10億年後の破局を避けるには脱出しかないことを指摘して本書を終えている.
本書は酸素と二酸化炭素濃度と気温を軸に地球と生命の45億年史を最新知見の元に総括し概説するという野心的な試みの本であり,膨大なトピックを詰め込んだ濃密な書籍としてその試みは成功しているといえるだろう.とはいえ幅広いトピックを扱っている上に,著者たちの独自主張と通説的見解の区別が時に曖昧で,さらに著述スタイルが学説史的にあっちへ行ったりこっちへ行ったりして最後に結論があったりなかったりというもので,実は本書は大変読みにくい本でもある.しかし部分部分は時に非常にスリリングだ.大気成分や気温という環境条件が大進化のパターンに大きな影響を与えているという説明(本書の叙述ではあたかも環境条件に直接的に反応しているような表現もあるが,そうではなく生物相互作用の中で微妙なトレードオフの均衡点が大きく動くということなのだろう)や,繰り返す温室効果絶滅の主張は説得的で迫力がある.何度も復習しながら*7少しずつ読み進めていけば大変充実した読書時間を過ごせると思う.
関連書籍
原書

A New History of Life: The Radical New Discoveries about the Origins and Evolution of Life on Earth
- 作者: Peter Ward,Joe Kirschvink
- 出版社/メーカー: Bloomsbury Publishing
- 発売日: 2015/04/14
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
ウォードの前著.生物進化史を呼吸適応の観点から外接している.本書の多くのアイデアが既に見られる.私の書評はhttp://d.hatena.ne.jp/shorebird/20080324

- 作者: ピーター・D.ウォード,Peter Douglas Ward,垂水雄二
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 2008/02
- メディア: 単行本
- クリック: 42回
- この商品を含むブログ (21件) を見る
同原書

Out of Thin Air: Dinosaurs, Birds, And Earth's Ancient Atmosphere
- 作者: Peter Douglas Ward,David W. Ehlert
- 出版社/メーカー: Natl Academy Pr
- 発売日: 2006/09/26
- メディア: ハードカバー
- 購入: 1人 クリック: 14回
- この商品を含むブログ (8件) を見る
ニック・レーンによる酸素濃度と生命史を扱った本.私の書評はhttp://d.hatena.ne.jp/shorebird/20061104

- 作者: ニックレーン,Nick Lane,西田睦,遠藤圭子
- 出版社/メーカー: 東海大学出版会
- 発売日: 2006/03/01
- メディア: 単行本
- 購入: 5人 クリック: 48回
- この商品を含むブログ (19件) を見る
同原書
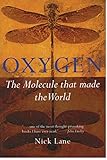
Oxygen: The molecule that made the world (Popular Science)
- 作者: Nick Lane
- 出版社/メーカー: OUP Oxford
- 発売日: 2002/09/26
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
地球史と生命史をあわせて概説するという同じ試みの(しかし著者たちによると内容がやや古くなった)リチャード・フォーティの本

- 作者: リチャードフォーティ,Richard A. Fortey,渡辺政隆
- 出版社/メーカー: 草思社
- 発売日: 2003/03/01
- メディア: 単行本
- 購入: 4人 クリック: 45回
- この商品を含むブログ (41件) を見る
同原書

Life: An Unauthorized Biography
- 作者: Richard A. Fortey
- 出版社/メーカー: HarperCollins Publishers Ltd
- 発売日: 1997/07/24
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログ (1件) を見る
*1:この方が売れるという版元の判断なのだろう.毎度のことながら残念なことだ.
*2:ウォードは最近自分のことを宇宙生物学者と定義しているようだ
*3:ジャイアントインパクト後4400百万年前まで地表は溶解状態にあった.その後ある程度隕石落下が減少するのは3800百万年前頃になる.
*4:著者たちはカメ類の分岐について主流の考えより古い解釈に従っているようでやや不思議だ.
*5:これについて証拠を得ていながら信じがたい高温に発表を見合わせていて,その後勇気ある研究者に出し抜かれたエピソードが書かれている
*6:今日のオウムガイはこの形質をやや深い海への生活に利用していると考えることができる
*7:特に時代ごとの二酸化炭素濃度,酸素濃度を整理しておくことをお勧めする.私は酸素濃度グラフを描き写し地質年代区分と絶滅ポイントを書き込み,常に参照できるようにしながら読み進めた