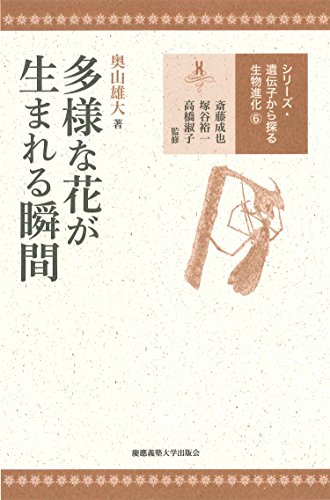
- 作者:奥山 雄大
- 発売日: 2018/06/20
- メディア: 単行本
本書は慶応義塾大学出版会の「遺伝子から探る生物進化」シリーズ全6巻の最後を飾る1冊.本シリーズは若手研究者による遺伝子解析などの遺伝学的手法を用いた進化生物学のリサーチを扱うもので,本書でも自伝的要素のある研究物語が生き生きと描かれている.著者の奥山雄大はチャルメルソウの研究者としてよく知られており,そのチャルメルソウ研究の一部は「共進化の生態学」でも紹介されていたが,本書ではさらにその背景まで含めて詳しく語ってくれている.
冒頭のカラー口絵はわずか4ページだがなかなか深い.第1ページははチャルメルソウが豊かに保たれていた京大の芦生研演習林(キャプションの最後に現在「シカの食害で変わり果ててしまった」とあり,深い悲しみが感じられる)と花と送粉者の関係,第2ページはチャルメルソウを訪花するミカドシギキノコバエの貴重なショット,第3ページはチャルメルソウの花の多様性(さらにその中に見られる系統間の相同形質と相似形質)と訪花キノコバエの関係,最後にきわめて近縁ながら形質間差異が大きいチャルメルソウとコチャルメルソウを提示している*1.チャルメルソウの花は花弁が細く独特でとても風変わりな形をしており,さらによく見るとその中に多様な花を持つ種が存在するのだ.なぜそんな風に進化したのか,いかにも興味深い.そして奥山の研究物語が始まる.
はじめに
冒頭はチャルメルソウの送粉者を突き止めようとしていたときの芦生演習林の思い出から始まる.生き物好きというと多くの人は動物のことだけを思い浮かべるが,実は植物と昆虫の関係も大変面白いのだということを,ツバキとツバキゾウムシの共進化系,バースニップの対ハナツヅリマルハキバガ防衛戦略,アケビカズラとアリの共生系を解説しながら力説する.本書はチャルメルソウとキノコバエの興味深い関係の物語になるのだ.
第1章 送粉生物学に入門する
物語は著者の京大理学部への入学から始まる.著者はそこで加藤真の「生物自然史基礎論」の講義をとりボルネオ熱帯林の一斉開花プロジェクトの話を聞き,分子ではない「生身」の生物を扱う生物学の重要性に目覚める.また分類学に遺伝的手法を持ち込み,新しい風を吹き込んでいた村上哲明の「植物系統分類学」の講義もとり,分類学の基礎を学ぶとともに,植物と送粉者の形質のQTL解析の解説にも興味を持つ.そして京大野生生物研究会の同期たちと切磋琢磨しながら,植物の研究者になる決意を固める.東南アジアを旅して熱帯林の素晴らしさにも惹かれるが,研究するなら身近な植物がうってつけだと考え,チャルメルソウに焦点を絞ることにする.チャルメルソウは(おそらく送粉者との関係に基づく)特徴的な花弁を持つ花を咲かせ,日本と北米に隔離分布し,さらに当時送粉者がよく知られていなかった.
そしてまず京大の演習林で固有種のモミジチャルメルソウの送粉者を特定すべく張り込み観察を行うことになる(これが「はじめに」の冒頭部分になる).送粉者はあっさり確認でき,それはキノコバエの仲間だった.キノコバエは送粉者としては珍しい部類で,それに頼る植物はしばしばキノコに擬態している.しかしチャルメルソウは擬態しているようでもない.著者は送粉者特定リサーチの幅を広げるが,調べた日本のチャルメルソウの送粉者は皆キノコバエだった.著者は袋掛け実験で確かにキノコバエが受粉させていることを確かめて初めての論文を書き,いくつかの雑誌からリジェクトをくらいながらついにリンネ学会植物学雑誌に受理される.それは修士1年の時だった.
第2章 分子系統学に入門する
チャルメルソウの謎を一つ解決すると次々に疑問がわく.何故日本に固有種が大半を占める10種が分布し,大陸アジアにはほとんど分布しないのか,キノコバエとの送粉共生はいつどのように始まったのか.著者はまずチャルメルソウ種間の系統関係を明らかにしたいと思い立つ.するとそれは既に都立大の若林グループが取り組んでいることがわかる.彼等は葉緑体のDNAを用いて解析を進めていたが,不可解な結果に困惑しているということだった.著者はそれはチャルメルソウでは葉緑体捕獲の影響が現れているのではないか(当時読んだソリティス博士の論文に示唆されていたそうだ)と考え,若林グループの了解を得て核DNAを用いた系統解析を川北篤と共同で試みることになる.核リボソームのITS領域を用いた分析を行うとかなり納得感のある系統樹が得られたが,なおモミジチャルメルソウとチャルメルソウの関係が怪しかった.
このあたりで著者は大学院進学時期になり,理学研究科植物分類教室から人間・環境学研究科の加藤真の研究室に進む.そしてチャルメルソウの系統解析を続けることとし,核リボソームの別のETS領域を用いた分析を行うことによりモミジチャルメルソウの問題も解決し(ITS領域だけに交雑の影響が出ていることを統計解析を用いて示すことに成功する),2本目の論文を出す.
第3章 太平洋をまたぐチャルメルソウ
2004年著者はアメリカに旅立つ.チャルメルソウは日本を含む東アジアの一部と北米にのみ分布し,しかもその大半は北米分布種なのだ.チャルメルソウ全体の送粉者との共進化の全体像を理解するには北米のチャルメルソウの理解が欠かせない.そこへ加藤の元へ著者の最初の論文の査読者でもあったアイダホ大学のベルミア博士からメールが届き,その機会を逃さずに3週間の調査旅行を決行する.挨拶代わりに覚悟を示すセミナー発表を行い,標本庫を見せてもらい,生息地を訪ねて観察のあと地ビールを飲む生活を続ける(旅で遭遇したトラブル集も掲載されている).観察してみると日本のチャルメルソウに似た緑色の花を付けるサカサチャルメルソウの訪花昆虫はキノコバエだった.また白い花を付けるものにはユッカガが,乾燥地域のものにはマルハナバチが訪花していることを知る.さらに観察を続け,著者には北米のチャルメルソウ類の訪花パターンの全貌が見えてきた.これを系統解析によりさらにリサーチしたいと考えた著者はDNA試料を集めることにし,最終的に9属すべて,(当時知られていた全76種中)53種の資料を手にすることに成功する.
解析の結果得られた系統樹は驚くべきものだった.それまで単にチャルメルソウ属とされていたものが5つのグループに分かれたのだ.そしてそれはそれまでチャルメラのような果実を付けるという特徴だけから1属にされていただけであり,おしべめしべ花弁の付き方を見ると今回の5グループが納得のいくものであることがわかるのだ(ここで口絵第3ページの深い意味がわかる).そしてその系統樹を眺めると,キノコバエとの共進化がただ1度進化したとは思えないことがわかる.著者は最尤法*2を用いた(送粉様式と相関する)花の形の祖先形質推定を行うために難しい論文を読み込み,手ごわいプログラムと格闘する.そしてその結果キノコバエ送粉と密接に関連する皿形の花が少なくとも独立に4回進化しているという結果を得る.
第4章 チャルメルソウの「種」の正体
ここで著者は「種問題」に踏み込んでいる.著者の問題意識は,そもそもチャルメルソウに興味を持ったのは日本に10種も分布しているということだったが,この10種は学生時代に学んだ「生物学的種概念」に則してもそうなのかというところにある.生物学的種概念に則しているかどうかを調べるには生殖隔離の有無を確認する必要がある.
著者は自分が集めた日本産チャルメルソウの試料を用いてDNA解析を行ってみることにする.第2章でも扱った核ETS領域と核ITS領域を用いて分析すると,それまで10種とされていた日本産チャルメルソウのうち6種は固有のまとまりを持つが,チャルメルソウ,コチャルメルソウ,コシノチャルメルソウは互いに近縁で遺伝子レベルでは明確に識別できず,オオチャルメルソウとトサノチャルメルソウはそれぞれ独立した2つの遺伝子グループに区別されることがわかった.
このオオチャルメルソウとトサノチャルメルソウ内のそれぞれの2グループは別の地域由来なのでそれぞれ独立した種である可能性が浮上する.著者はその予想される難しさに最初は躊躇するが,結局生殖隔離の有無を調べるためにチャルメルソウ種間の交配実験に進む*3.やってみるとチャルメルソウの種間ではすべて雑種が形成されるが,雑種の花粉稔性は大幅に低下することが確かめられた.そしてオオチャルメルソウ,トサノチャルメルソウの問題の2グループ間でも同じように雑種の花粉稔性は低下していた.これらは別種である可能性が高いと著者は結論づける.著者はこれらの結果(および葉緑体DNAの分析結果)をあわせて「チャルメルソウ節の種は核リボソームDNAを使えば遺伝子バーコーディングによる種識別が可能だが,葉緑体を用いては難しい」ことを示す論文に仕立て上げる*4.
なお本章の最後には新種アマミチャルメルソウの発見(地元の生物研究家森田氏が2011年に発見し,著者が2016年に記載したもの)についての紹介がある.また自分の研究の積み重ねとこの新種の発見により「日本のチャルメルソウの種数は14種である」と自信を持って答えられるとも書いている.専門家として研究してきた矜持というべきだろう.
種問題については実在を巡る哲学的議論がまず思い浮かぶが,本章では実際の第一線の植物学者の問題意識のあり方(種の定義については生物学的種概念のみが念頭にあり,実務的にDNAバーコーディングの有用性に関心がある)がよくわかる記述になっていてなかなか興味深い.
第5章 大きな転機,「岩手留学」と植物免疫研究
2007年秋,著者は博士過程最終年で,頼みの綱たる学振PDに不採用になり,博士号取得後の進路について途方に暮れていた.そこに岩手生物工学研究センターがポスドク研究員を探しているという話が舞い込む.同センターは次世代シーケンサーを積極的に取り入れて有用作物の農学的研究を行っているところで,陸封型イトヨの多回起源やナス科植物の自家不和合性の進化の研究論文を読んで遺伝学的研究に興味を持っていた著者はそれに乗ることにする.そこには海外からの研究者が多く集まり所内のミーティングはすべて英語という環境だった(それで「岩手留学」というタイトルになっている).
そこで著者はチャルメルソウ研究を一時封印してイネのいもち病抵抗性(いもち病菌の侵入に対して細胞死で対抗する性質)の研究に加わる.これはいもち病菌が「被病原性因子AVR」を持ち,イネが抵抗性遺伝子(R遺伝子)を持つ場合に発現する.著者はこのイネ側の抵抗性遺伝子のうちPiaの遺伝子を突きとめるというテーマを担当し,2100系統の中から突然変異体をスクリーニングし感染実験を行い,さらにその変異の染色体上の位置に当たりを付け,関連解析によりその正体をほぼ突きとめる.この部分の解説は研究の進み方に臨場感があり,途中の意外な展開や残された謎*5などがあって面白い.
ちょうどそのころ国立科学博物館筑波実験植物園のパーマネント研究職の公募があり,著者はそれに応募して選ばれる.著者自身は行き先ないところを拾ってもらった経緯もあり研究の仕上げを後任にまかせて去るのについて申し訳なく感じたようだが,研究所側は「相手が任期なしならしゃあないなあ」と送り出してくれ,著者は1年足らずで岩手を去り,チャルメルソウの研究に戻ることになる.
第6章 日本のチャルメルソウ類はどうやって生まれたのか?
晴れて筑波に着任した著者は自分の博士論文で取り上げていながら未解決だった課題「チャルメルソウ節(チャルメルソウ属の下位分類でタイワンチャルメルソウと日本の固有チャルメルソウ群合計14種からなる単系統群)はどのような共通祖先から進化したのか」に取り組む.この植物の分散能力の低さから日本において適応放散が生じた可能性が高いと考えられるが,起源植物はまだよくわかっていなかったのだ.
第3章で実施された系統樹を見ると北米大陸のタカネチャルメルソウが最も近縁だということになるが,実はタカネチャルメルソウは2n=14で,日本のチャルメルソウ節では全種が2n=28となっており,どこでどのような倍数化*6が生じたのかが問題になるのだ.これをDNAから解析するには遺伝子変換による協調進化が生じやすい核リボソーム配列は向いていない.そこで著者は新たに4つの核遺伝子をターゲットにして解析する.ヘテロ接合を減らすために一度自家受粉させるなどの様々な工夫を凝らしながら解析を進め,チャルメルソウ節の起源で一度だけ交雑による異質倍数化が生じたらしいという結果を得る.しかしどのような交雑だったのかについては遺伝子ごとに分析結果が分かれ行き詰まる.遺伝子ごとのデータを統合すればいいのだが,倍数化サブゲノムの場合コピーが2つずつあるので,このどちらのデータなのかを事前に知ることができないという問題が生じる.しかしある日,すべての組合せでデータを統合し系統樹とどちらのサブゲノムかという問題を同時に推定してしまえばいいとはたと気づく.そして系統推定やプログラムに強い共同研究者とともにこの問題を解決する.このブレークスルーのエピソードは印象的だ.そして得られた結果により日本のチャルメルソウ節の起源は北米のタカネチャルメルソウとテリマ・グランディフロラの交雑による異質倍数体であることが明らかになった*7.
第7章 種分化の鍵は「花の香り」
第4章の分析によりチャルメルソウは交配後生殖隔離のメカニズムを持っていることがわかっている.しかしチャルメルソウはしばしば同所的に他種が分布し,ほとんど交雑体は観察されない.著者はこの交配前の生殖隔離メカニズムにも興味を持つ.カンコノキとホソガの共生系においては種ごとの緊密な排他的共生系(絶対共生系)が成り立っており,花の香りが送粉昆虫であるホソガが別のカンコノキに向かわないようにする送粉者隔離の鍵だった.だからチャルメルソウでも同じようにキノコバエは花の香りでチャルメルソウを見分けているのかもしれない.
そこでキノコバエをよく観察すると口吻の長いミカドシギキノコバエと口吻の短いキノコバエが存在し,同所的に分布するチャルメルソウがある場合にはそれぞれ特定タイプのキノコバエが送粉しているようだった.これらのチャルメルソウの花の形態には大きな差が無い.そこで著者は花の香りを分析することにする.11種128個体の香り組成データを主成分分析し2次元プロットすると,それは大きく2つに分かれて送粉キノコバエのタイプと対応していた.しかしこれだけでは相同の影響を排除できていない.そこで著者は系統学的独立比較法を取り入れ,この対応関係がリアルでありミカドシギキノコバエ送粉と特定の香り(ライラックアルデヒド)の組合せが何度も独立に進化していることを示すことに成功する.
さらに著者はバイオアッセイ実験を行い,口吻の短いキノコバエがライラックアルデヒドを忌避すること,ミカドシギキノコバエにとってライラックアルデヒドが強い吸蜜刺激であることを見いだす.これらをあわせると花の香り組成の変化が種分化に大きくかかわっていると言えるだろう.著者はこの結果を自らの研究の集大成と位置づけ,論文にまとめNature, Scienceという有名どころの雑誌に投稿するがなかなか受理されない,著者は追加の実験を行い,最終的にこの論文はJournal of Evolutionary Biologyに掲載される.
この章の記述はチャルメルソウの生殖隔離メリットが中心に考察されており,キノコバエ側の(ある程度)排他的な共生関係のメリットについてあまり触れられておらず,肝心の所が少しわかりにくい.これはキノコバエの生活史や淘汰圧についてあまりわかっていないということなのだろうが,推測も含めてコメントが欲しかったところだ.いずれにしてもこの点にはなかなか興味が持たれる.一方論文の投稿,査読,査読コメントへの対応,受理にいたる部分は著者の本音やフラストレーションも含めてなかなか率直に書かれており,読んでいて臨場感を感じることができる.
第8章 多様な花が生まれる瞬間
この花の香りと種分化の関係をより詰めて考えるには,遺伝的に極めて近縁で同所的に分布しているにもかかわらず送粉者が分かれているチャルメルソウとコチャルメルソウがよいモデル系になる.著者はさらに考察を進めるべくこの両種の発現遺伝子の網羅的解析,および比較ゲノム解析を進めている.本書執筆時点ではこれに関する論文がまだ発表されていないとこのことで,この結果についてはあまり書かれていないが,このような解析が何を明らかにしうるのかが解説されている.そして最後に引き続き「多様な花が生まれる瞬間」を解き明かし続けたいという決意と今カンアオイとテンナンショウに興味があることを述べ,本書を終えている.
本書は学生時代にチャルメルソウに魅せられ,そのままその不思議な分布の謎に挑み,解き明かしてきた著者の研究物語だ.若手研究者としての夢と希望と現実もうまく書けているが,やはり本書の魅力は一般にはほとんど知られていない植物チャルメルソウが提示する謎とその解明の臨場感だろう.なぜあんな花の形なのか,なぜそしてどのようにして北米と日本にほとんどの分布があるという状況になったのか,キノコバエとの排他的共生系はなぜ成立したのか,日本での種分岐はどのように生じたのか,その謎解きを読者は1つずつ経験することができる.そしてまだ謎は完全に解けてはいないのだ.本書を読み終わった読者はチャルメルソウの魅力に惹き付けられ,さらなる謎解きの進展を楽しみにすることになるだろう.
なお奥山の研究のその後の進展はここで知ることができる.キノコバエの生活史も明らかになりつつあるようだ.https://sites.google.com/site/okuyamanokenkyuupeji/home/kenkyuu-gyouseki/
関連書籍
共進化の生態学.奥山がチャルメルソウに関する1章を寄稿している.私の書評はhttp://d.hatena.ne.jp/shorebird/20080517

共進化の生態学―生物間相互作用が織りなす多様性 (種生物学研究)
- 発売日: 2008/03/24
- メディア: 単行本
「遺伝子から探る生物進化」シリーズの中でやはり生態学の興味深い問題についての研究物語を扱った一冊.私の書評はhttp://d.hatena.ne.jp/shorebird/20170926
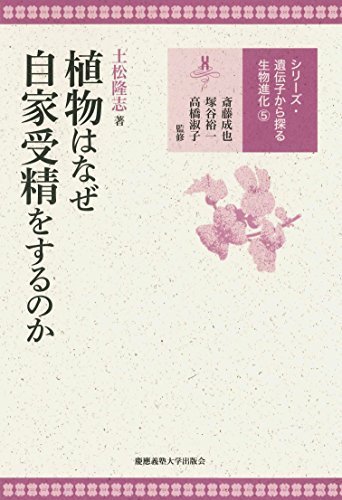
植物はなぜ自家受精をするのか (遺伝子から探る生物進化 5)
- 作者:土松 隆志
- 発売日: 2017/08/24
- メディア: 単行本
*1:これらの写真が示していることは非常に深く,本書を読み終わった後にもう一度眺めると大変感慨深く感じられる.
*2:著者はここで最節約法はまれにしか進化しない形質の分析には有効だが,しばしば繰り返し進化する花の形の変化のような形質には向かないという解説を置いている.ただ単なる進化頻度の問題というより,進化確率の異なる複数変化を扱うのに最尤法の方が向いているという説明の方がわかりやすかっただろう.なおここで進化頻度の低い例として,脊椎動物において翼の進化はコウモリと鳥で2回だけ生じたと書かれているが,翼竜の進化をあわせて3回だと思われる.
*3:踏み込めたきっかけは種生物学会で矢原徹一からもらった「迷っているくらいならやってみればええやん」というアドバイスだったそうだ
*4:この論文の受理にかかる苦労話も書かれている.
*5:そもそもなぜAVR-Piaの遺伝子座で抵抗性を持たないアレルが淘汰されてしまわずにアレルの多型がイネ集団全体で保たれているのかについては謎として残されているようだ
*6:同質倍数化か,異質倍数化か,異質倍数化ならどのような交雑が元になっているかが問題になる
*7:なおどこでこの交雑が生じて現在のような分布になっているのかというのは謎のまま残されている