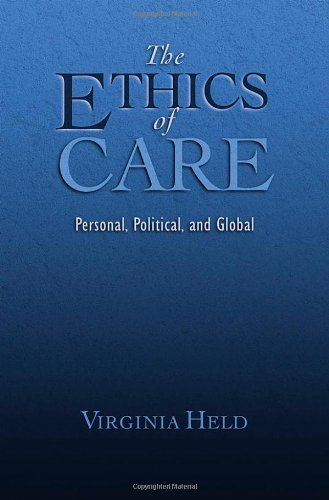第8章 自身とは何か その19
ヘイグによるアダム・スミスの道徳感情論の読み込み.ヘイグは道徳を本能と理性と文化による混合物であり,そこに再帰的な相互関係があるものとして捉えている.まず本能的な要素が解説され,続いて理性的要素が扱われる.これは直感的な道徳感情に対して熟考的な道徳判断として議論されることが多いものになる
理性的要素
理性は疑いなく道徳の一般的規則の,そして我々が道徳実践のために行うすべての道徳判断の源である.しかし最初の善悪の感知が理性から生じうると考えるのは全く馬鹿げた考えだ.そしてそれはその善悪判断が道徳の一般的規則の形成に関わるものであってもだ.・・・
直接感じられないなら,あることの是非は決められない.アダム・スミス 「道徳感情論」
そのような行為の一般的規則は,それを習慣的に熟考しているなら,ある状況下でどのような振る舞いが適切かの判断において,利己心からの間違いを正してくれるのに大いに役立つ.
アダム・スミス 「道徳感情論」
- スミスは私たちの道徳的直感は感情から来るが,道徳的規則は理性から来ると信じていた.私たちは,胸の中の自分の判断から一般的規則を導くのではない.そのような判断は自分の行いを冷静に公正に見ることはできない.
- 一般的規則は,他者の行動やそれについての第三者の判断を観察するときに感じる自然な感覚から導かれるのだ.特に私たちは自分たちの行動に対する賞賛を求め,非難を恐れる.私たちは道徳規則を,他者への第三者的観察の経験から導くのであり,自分たちへの第三者的観察から導くのではない.
ヘイグによるとスミスは道徳の理性的熟考的な判断についてそれは第三者的な観察から来るものだと議論している.純粋な抽象的な思考から演繹的に規則が生み出されるのではなく,第三者がある行動をどう判断するか,それが称賛されるのか非難されるのかの判断が道徳の理性的部分の基本だとしている.
- 理性は,自分たちの行動や意見を合理的なものとして説明し,自分たちや自分たちの立場を正当化するために使われるのかもしれない.ハイトは道徳判断における理性の最重要な役目は後付けの正当化理由を見つけることだと主張した.この見方によると道徳的推論には,問題をリフレームしたり新しい道徳的直感を引き出したりして他者の行動を変える力はあまりないということになる.
すると意識が後付けの理屈をひねり出す報道官だというハイトの考えと近くなる.しかしそれだけではないし,スミスはそこを深く考察していたというのがヘイグの指摘になる.その上でのヘイグのここからの考察はなかなか面白い.
- しかし理性は自分自身の理由を熟考するために使うこともできる.そして自分自身を他者と調和させるように変えることもできる.スミスは自己内省的な規則は束縛のない道徳的直感へのチェックとして働くと考えていた.道徳規則に従うように行動するというコミットメントは自己欺瞞を防ぎ,将来的に後悔するような行動への衝動に対抗することができる.
- 理性は論理的に一貫した公平な行動をとるように指示することもできる.「sympathy」は他者をより理解するように進化し,理性は選択肢のコストとベネフィットをうまく計算できるように進化した.あなたのコストにおいて私が利益を得られるような状況下で,私は自分がとれる選択肢のそれぞれの期待効用を計算し,あなたのとれる選択肢のそれぞれのあなたの期待効用を計算してあなたがとりそうな選択肢を予測し反応するために「sympathy」を使う.予測の正確性はあなたの選択のシミュレーションの質と私の論理の質に依存する.さらに予測において3人称視点をとるなら,自分とあなたの区別を無視できる.だとしたら,感情を交えない純粋に合理的な疑問として,何故私は自分の効用をあなたの効用より高く評価すべきなのだろうか.
- ここで感情が計算に入ってくる.そして感情は自分の効用があなたの効用より優先すると強く訴える.しかし理性は問題を両サイドから見て,私の効用とあなたの効用の評価の違いは,状況を非対称にするための全くの恣意的な基準に基づいているに過ぎないことを理解できる.実際に人々がどれほどこのような抽象的な思考で行動を選んでいるのかはよくわかっていない.しかしこのような合理的な議論は他者にある行動をすべきだと説得するときにはよく見られるものだ.
- スミスは,目的因の視点から見て,この自分の効用へ与える特別な卓越は「恣意的」ではないと考えていた:「すべての人間は自分を第1に気にかける.そしてすべての人間は他者よりも自分の面倒を見るのにたけている(道徳感情論)」 ヒトは自分の面倒を見る,それはもしそうでなければ「彼は自分や社会の効用を下げるような状況を避けるための動機を持たなくなってしまう.そしてそれらを慈しむ自然は,彼はそのような事態を避けようとすべきだとするだろう(道徳感情論)」
この部分は難解だ.ヒトは自分の効用だけでなく他者の効用をも気にかけることがある.それは(評判などを通じて)社会的に排斥されないためにというメカニズムが感情を通じてビルトインされているためでもあるが,理性を通じて自分を優先する態度が全くの恣意的な基準に過ぎないということが理解できるという部分もある.そしてそういう理解は他人を(利他的に振る舞うように)説得する際にはしばしば使われる.だが,(スミスのように目的因から考えると)最終的にはヒトは(評判を通じた利他的な行動をとることを含めて)自分の効用を優先するはずだということになる.
(正しく理解できているかやや心もとないが)要するに理性的には「自他を区別しない全面的絶対的利他的な行動原則が正しい」と導けても,進化適応的に考えるとそのような態度が定着することは難しいということを解説しているのだろう.









![マネーボール [Blu-ray] マネーボール [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/513NUKi-ruL._SL500_.jpg)