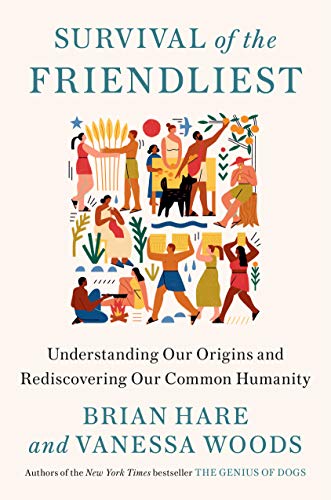- 作者:リチャード・ランガム,依田卓巳
- 発売日: 2020/10/21
- メディア: Kindle版
本書はリチャード・ランガムによるヒトの本性(特にその他者への寛容性と攻撃性)に関する本だ.本書のキーワードは「反応的攻撃性」と「能動的攻撃性」の区別,そして「自己家畜化」になる.ヒトが自己家畜化した動物であるという議論については先日ブライアン・ヘアとヴァネッサ・ウッズによる「Survival of the Friendliest」を読んだばかりでもあり,いろいろ深く楽しめた.ランガムはヘアと共同研究したこともあり基本的に同じ立場に立っているが,そのスコープと進化的なストーリーはより深く詰められている.原題は「The Goodness Paradox」.
はじめに 人間進化における善と悪
序章ではヒトにはジェノサイドを引き起こすような邪悪さと見知らぬ他人に親切にする善良さの両方があることが強調されている.本書はこれをどう説明するかという試みの本だ.導入部分にはこう書かれている.
- ヒトの無私と身勝手の矛盾した組合せについては古来より性善説と性悪説という2つの説明がある.どちらも従順さと攻撃性の片方は生得的だとするが,どちらを基本とするかによって分かれ,ルソーとホッブスはそれぞれの説明の象徴となった.
- 議論は白熱し時に政治化して収拾がつかなくなる.この泥沼から抜け出す道は議論自体の意味を問うことだ.ヒトは生得的に善良であり,同時に生得的に利己的なのだ.ヒトが本質的に善でありかつ悪であると認めると新たな疑問が生じる.それはどこから来たのだろうか.
- そして疑問の鍵はヒトの2つの近縁種チンパンジーとボノボがそれぞれ違った形でヒトと似ている理由にあるだろう.
この後本書全体の見取り図が描かれている.
第1章 パラドックス
第1章はヒトの本質に善と悪があることを示すものになる.説明は農業や国家以前の社会で生きるヒトの状況から始まっている.
- 国家による干渉がない小規模社会の生活がどんなものかはニューギニアで記録されている.ダニ族をはじめとした狩猟採集民は相互に依存し支え合う社会で生きる穏やかで優しい人々だったが,集団同士では断続的に激しく殺し合っていた.彼等は「共同体内での平穏」と「外での戦闘」をはっきり区別していたのだ.
- 集団内のヒトの攻撃性はチンパンジーに比べて非常に低い.チンパンジーは暴力的とされるようなヒト集団と比べても数百倍以上暴力的だ.ボノボのオスの攻撃性はチンパンジーの半分程度だが,メスはチンパンジーより攻撃的で,やはりヒトに比べれば非常に高い.いわゆる家庭内暴力(男性による女性支配)についてもチンパンジーやボノボはヒトよりよりはるかに高い暴力性を示す.
- しかし戦争は全く別の問題になる.ヒトにおいては,数十年間戦争がない場合もあるが,ひとたび生じればチンパンジーより高い割合で互いに殺し合うことになる.狩猟採集民や農耕民の小規模社会における集団同士の暴力による殺害の割合は霊長類平均より高いだけでなく.第二次世界大戦で多くの死者を出した20世紀のロシア,ドイツ,フランス,スウェーデン,日本よりも高い.
- ヒトは日々の生活で暴力的になることは少ないが,戦争時の暴力による死亡の割合は高い.これが善と悪のパラドクスだ.
第2章 攻撃性のふたつのタイプ
第2章では第1章で説明されたヒトの善と悪の二面性が,反応的攻撃性と能動的攻撃性を区別することで理解できることを説明する.
- ヒトの攻撃的な行動には豊かで複雑な生物学的能力と感情が絡む.近時ヒトの攻撃は2つの主要なタイプに分かれることが理解されるようになってきた.この2つは進化的には別々に考える必要がある.本書では「反応的」攻撃と「能動的」攻撃という用語を用いる.
- 反応的攻撃は脅威に対する反応でテストステロンの濃度が関係する.怒りを伴い,しばしば感情を爆発させる.些細な侮辱から生じる殺人などがこの例だ.現代社会の多くの殺人はこのタイプの暴力によるもので,しばしば名誉や敬意が絡み,経済的文化的な影響を受ける.
- 動物の種によってこの反応的攻撃性の高さには差がある.チンパンジーやオオカミなど大抵の動物はヒトより反応的攻撃性が高い.
- 能動的攻撃は冷静に計画された暴力だ.なんらかの目的のための意図的攻撃であり,怒りなどの感情表現は必須ではない.準備された奇襲攻撃がこの例だ.
- 能動的攻撃には意図的な選択があるので,世間や法律*1はより厳しく対処しがちだ.
- 生物学的な仕組みに基づいてこの2つのタイプの攻撃性の区別を考えることができる(前頭前野と扁桃体,テストステロン,セロトニン,コルチゾールの役割,サイコパスに関する脳科学的知見,動物実験による視床下部の相互抑制領域の役割の知見,行動遺伝学的知見が説明されている).能動的攻撃と反応的攻撃は異なる神経経路に制御され,遺伝の影響は様々だ.この2つは互いに独立して発達すると思われる.
- ヒトではほかの動物に比べて反応的攻撃性が低く,能動的攻撃性が高いのだ.これがなぜなのかが問題となる.
第3章 ヒトの家畜化
本書ではヒトの反応的攻撃性の抑制を自己家畜化から説明する.第3章ではこの「ヒトの自己家畜化」というアイデアが古来からあることが示され,それにかかる学説史が解説されている.学説史はなかなか興味深い.
- オオカミとイヌを比べると,イヌは家畜化され,オオカミに比べて反応的攻撃性が抑制されている.そしてヒトも同じく反応的攻撃性がチンパンジーに比べて強く抑制されている.
- ヒトが家畜化された種であるという考えは古代ギリシアからある.家畜化についてヒト普遍的だという考え(テオプラトス)と,集団(人種)により家畜化の程度が異なるという考え(アリストテレス)があった.不幸にして後者が有名になり,ナチスの蛮行の不吉な先触れになった.
- 科学的にはじめてヒトの家畜化を議論したのは人類学者のヨハン・ブルーメンバッハだった.ブルーメンバッハは家畜化はヒト普遍的な特徴だと主張した.リンネとモンドポーは「世界には野蛮な人間,野生児が存在する」ことを論拠にこれに反対したが,喧伝された野生児の正体がわかり,この反対論は消え去った.
- ダーウィンは家畜化が生じたとしたらそれはどのようにしてかということについていろいろ考察した上,ヒト集団がなんらかの主体に繁殖制御されたとは考えられず,脳が小さくなるという特徴もない(と考えた)ことからヒトの家畜化というアイデア自体を否定した.(なお考察の途中でダーウィンはヒト集団によって家畜化程度が異なるというアリストテレス的な考えも記している)
- 20世紀になりドイツの人類学者オイゲン・フィッシャーは家畜化程度の高いアーリア人の優越をとなえ,ナチに利用された.ローレンツはヒトは文明化により家畜化され退行したと論じ,やはり当時の優生学に利用された.第二次世界大戦後,集団の優越を主張しないヒト家畜化論がミードやボアズから出され,様々な学者が「ヒトの自己家畜化」を研究するようになった.
- それらの研究はヒトの自己家畜化の証拠を積み上げてきた.家畜化の共通の特徴(家畜化症候群)として,小型化,顔の平面化,性差の縮小,脳の小型化があり,それぞれサピエンスに当てはまっていることが認められてきている.
第4章 平和を育む
第4章ではなぜ家畜化症候群という現象が様々な家畜に共通して生じるのかが解説される.
- なぜ家畜化により共通の特徴が生じるのか.最も一般的な仮説は並行適応説になる.それぞれの特徴はヒトに飼い慣らされるという新しい共通した環境の様々な面についての個々独立した適応(ヒトについては文化的な環境に対する個々独立した適応)だというものだ.
- ベリャーエフのキツネ飼育実験は家畜症候群の多くの特徴が副産物であることを強く示唆している(実験の詳細が紹介されている).ベリャーエフはヒトに対する従順さ(反応的攻撃の抑制)だけに淘汰をかけたのだが,ブチ模様,垂れ耳,丸まった尾,繁殖周期の変化など様々な家畜化症候群が現れたのだ.その後同様な結果はミンクやラットでも得られている.
- この家畜化症候群は野生下に戻してもすぐに淘汰されて消え去ったりしないこともミンクで明らかになった.またイヌ,ヤギ,ブタ,ネコが野生化しても元の野生種に戻るわけではない.家畜化ミンクが小さい脳でも問題なく野生生活を送れるのになぜ祖先種の脳が大きいのかという疑問はもっともだが,その答えはわかっていない*2.
- では飼育はどのように家畜化症候群を引き起こすのか.これまでの研究で,神経堤細胞の遊走パターンがそれにかかわっていることがわかってきた.(神経堤細胞の遊走パターンがそもそもどのように反応的攻撃性と関連するのか*3,そしてどのように毛皮の模様や先端部の形状や脳の小型化に影響するのかが詳しく解説されている)
- そして子どもの方が反応的攻撃性が弱いので,家畜化においては神経堤細胞の遊走パターンの変化や細胞数の減少により関連システムの発達が遅れ,部分的に子どものままになること(幼若化)が重要だということが理解されるようになってきたのだ.
第5章 野生動物の家畜化
第4章で議論した家畜化はヒトの手による人為淘汰産物だ.では自然淘汰でこのような従順さを生む家畜化が生じるのかが第5章のテーマになる.
- ベリャーエフの実験からいえば,野生状況でも従順さに対して淘汰がかかれば家畜化症候群が観察されるはずだ.これまでこのような仮説を検証してきたリサーチはない.しかしチンパンジーとボノボの比較は非常に有力な手がかりになる.
- ボノボは自己家畜化したチンパンジーのように見える(チンパンジーとボノボの違いが詳しく説明されている.特にボノボの反応的攻撃性はチンパンジーに比べて弱く,交尾や遊びなどの行動も家畜化の特徴を示している.また頭蓋骨などの形状をゴリラやアウストラロピテクスを含めて系統間で比較すると,ボノボの系統においてチンパンジーとの分岐後家畜化症候群が生じていることが推定されることも解説されている).これを生じさせた淘汰圧は食糧の豊富さという環境要因から説明が可能だ(詳しい説明がある).これらは全てボノボが反応攻撃性を抑制する淘汰を受けて自己家畜化したことを強く示している.
- また島の生物群をよく見ると自己家畜化を示しているものが見つかる.(ザンジバルアカコロブスの例が説明されている)
第6章 ヒトの進化におけるベリャーエフの法則
第6章では化石から推定されるヒトの家畜化症候群の進化過程が描かれる.
- ベリャーエフの実験から反応的攻撃性を抑える淘汰が家畜化症候群を引き起こすことが明らかになった.このことから家畜化症候群があればその種がかつて反応的攻撃性抑制の淘汰を受けたと推論することができる.ヒトはおそらく進化過程で反応的攻撃性を抑える淘汰を経験したのだ.
- 人類化石の系列を見るとサピエンスの系列は少なくとも30万年前*4から(脳の小型化*5以外の)家畜化症候群の傾向を示している(ネアンデルタール化石との比較が解説されている).そしてその過程は現代に至るまで時とともに加速しているようにみえる.
この第4章から第6章の前半までの部分(および第9章の前半)で,(その神経堤細胞の遊走パターンという至近的メカニズムも含めた)家畜化症候群の存在,ヒトについては自己家畜化が生じたと考えられることが丁寧に論じられている.ここはヘアとウッズの本とも重なるところで説得力のあるところだ.そして本章の最後にはヒトの成功を考える上でこの自己家畜化が非常に重要だとランガムは主張している.ここからがランガムが最も議論したい本書の中心テーマにかかる部分になる.
- サピエンスの成功の要因については文化的的適応を蓄積する能力だと考えられている.考古学者カーティス・マリアンはこれを生んだのは知能の高さ,高度な協調性,社会的学習能力と考えた.そして様々な解剖学的な特徴については並行適応的説明と浮動的な説明がある.しかしこのどちらも家畜化症候群を考慮していない.全体を説明するにはサピエンスに普遍的にかかった淘汰圧を考える必要がある.そしてそれを始めて説得的に考察したのがクリストファー・ボームになる.
第7章 暴君の問題
自己家畜化という視点をとるとどのようにヒトを理解できるようになるのか.第7章からランガムは進化的な説明に入る.自己家畜化が生じた淘汰圧は何だったのか.
- ヒトに家畜化症候群を生じさせた淘汰圧は何だったのか.ボームは「処刑仮説:the execution hypothesis」を提唱している.攻撃性を抑える淘汰は極めて反社会的な個人を処刑したことによりかかったとするものだ.
- この考え方の萌芽はダーウィンにも見られる.ダーウィンはヒトの道徳を説明しようとしている部分で「犯罪者は処刑されるか投獄され,暴力的で怒りやすい男たちはしばしば残酷な末路をたどる」と書いている*6.
- 近時人気のある説に「偏狭な利他主義仮説」がある*7.この仮説は攻撃性の低下を説明する処刑仮説の代替案ではなく,協調が選好される理由(部族間戦争において有利であったから)を説明するものだ.
- 私は「偏狭な利他主義仮説」には問題があると考えている.まずチンパンジーにも集団間の衝突があるが,協調的性質は進化していない.またヒトの狩猟採集民での自己犠牲的行為の発生が確認できない.この証拠が見つかるまでは偏狭な利他主義は淘汰による適応形質ではなく文化的な行動だと考えておくべきだ*8.
- 協調性の進化については評判が重要だとする説も有力だ.チンパンジーは言語を持たず自分の評判を気にしない.だからこの考え方は有望だ.しかしなぜ悪評を気にしなくてはならないのかはもっと詰めて考えるべきだ.優しい男性が好まれるとしても暴力的な男性が思い通りに事を運べるなら悪評を気にする必要がないことになる.そこを埋めるのが処刑仮説になる.
- 狩猟採集民の社会では,暴力的な男性にはからかい,嘆願,排斥などにより連帯的に対処するが,それでもその男性が行動を改めないないときには「処刑:capital punishment*9」が用いられる.これこそが反応的攻撃性抑制への淘汰圧だと考えられる.
ダーウィンまでさかのぼる学説史は興味深く,偏狭な利他主義仮説の問題点の指摘は鋭いと思う.しかしランガムの進化仮説の説明はなかなか難解だ.処刑により攻撃性の低下が生じたという部分はわかりやすいのだが,協調性(あるいは利他性)の増進と反応的攻撃性の抑制の関連のところが明解に書かれていない.
そもそも進化的なパズルだったのは一見不利に見える利他性の進化だ.この観点に絞って考えると,それを説明しようというのが評判の個体利益を強調する間接互恵性仮説および(性淘汰を含む)社会淘汰仮説,そして戦争における部族の有利性を強調する偏狭な利他主義仮説になる.ランガムが処刑を避けるための攻撃性の抑制が適応産物で,協調性や利他性がその副産物だと主張するならこれは利他性進化にかかる新たな代替仮説ということになるが,そういうわけではなく,(協調性の上昇自体にも適応価があるのだが)暴君の問題が解決できなければ間接互恵や社会淘汰だけだは利他性の進化を完全に説明できないのではないかという主張になっている.そしてランガムはヒトの進化において重要だったのは攻撃性の抑制であり,協調性の増進についてはその中の補足のような位置づけだと書いている.
片方でランガムは評判を重視する仮説には穴があると主張しており,利他性の進化を説明するために間接互恵仮説や社会淘汰仮説があるが,それが説得力を持つために(処刑仮説自体ではなく)処刑仮説の前提である処刑制度の成立が必要だと主張しているようでもある.つまり間接互恵や社会淘汰が働くには「暴君への対処」が必要で何故ヒトでそれが可能になったかの説明が補足的に必要だ(逆に言えばこの穴さえ埋めれば間接互恵や社会淘汰で利他性が説明できる)といっているようだ.
この暴君への対処問題は,単に「処刑によって攻撃性が低下したから」では説明できず,なぜ(他の霊長類のようにアルファオスの君臨ではなく)下位集団による暴君の処刑が可能になったのか*10が説明されなければならない.そして処刑制度の成立は処刑仮説にとっても前提条件であり,果たして本当に広く成立していたのか,なぜ成立可能になったのかが重要になる.(これはそれぞれ第8章,第10章で扱われる)
すると処刑制度が成立することによって,処刑仮説による攻撃性の低下と間接互恵や社会淘汰説による協調性の上昇が並行して進化しうることになる.片方でランガムは第10章で利他性は処刑に対する保身に役立つ直接的な適応であるとするボームの考えも引用している.ランガムがこのあたりをどう考えているのかはやや曖昧であるように思う.
第8章 処刑
第8章の冒頭は開拓当時の17世紀アメリカでの公開絞首刑と大衆によるリンチの描写から始まる.実際にならず者の処刑は小規模ヒト社会に広く見られるのだ.
- それほど遠くない昔,ヒト集団は規範に従わないならず者に対して死刑で処するのが普通だった.すべての古代文明に死刑があった.狩猟採集民の死刑のリサーチは1980年代まであまり体系的に研究されていなかったが,調べてみるとそれは普遍的に存在し,様々な形で社会的に支援されていた.重罪とされる行為の1つは文化的なルールをないがしろにすることだ.
- 小規模社会では伝統という社会の檻が閉所恐怖症的な集団規範への服従を求める.決定権を握るのは1人のリーダーではなく大人の集団で,社会規範に従わないものから集団による専制を守るための死刑決定を行う権限を持っている.そして平等主義的な社会には独裁者になろうとするものの処刑が体系的に行われてきたという特徴が有る.(ボームの狩猟採集民のリサーチの詳細が紹介されている)
- 処刑されるリスクは恐怖を通じた社会的コントロールを可能にするが,処刑仮説のポイントはそこではなく,このような環境下ではとりわけ高い攻撃性を持つ個体は排除され,攻撃性が下がる方向へ淘汰圧がかかるというところにある.
- このような集団によるならず者の処刑が可能になった最大の要因は,武器ではなく,言語と意図共有による共謀の能力だと考えられる.
処刑制度が(事実の問題として)進化環境で成立していたかどうかについては,ボームが行ったような狩猟採集民のリサーチが非常に重要で,そして実際に進化環境では処刑制度(およびそれによる淘汰圧)が広く成立していたのだろう.ランガムはここでアメリカの開拓社会や古代文明の話も持ち出しているが,進化環境にある小規模平等社会とは言い難く,やや議論が散漫になっているようでもある.
第9章 家畜化がもたらしたもの
ここまでランガムはネアンデルターレンシス系統との分岐後サピエンス系統で攻撃性の低下について淘汰が働き,その結果自己家畜化が生じ,様々な(解剖学的特徴を含む)家畜化症候群が生じたという議論を行ってきた.ここで証拠の検討がなされる*11.
- 様々なヒトの解剖学的特徴について,従来の学説は並行適応と考えてきた.この考え方からするとヒトの従順さの起源はもっと古くてもいいことになる.また従順さは(脳の増大など)なんらかの適応の副産物だという主張もあり得る.
- 自己家畜化仮説とこれらの対立仮説をヒト系列で直接テストするのは難しいが,イヌを調べることである程度ヒントを得られる.オオカミと比較した場合のイヌの様々な特徴は幼若化による幼形形態形成として理解できる.従順さへの淘汰は(子どもは親よりも従順であることから)幼若化を引き起こす.そして幼若化は他個体への友好性を高め,その社会化期間を引き延ばす.
- ヒトが幼若化した類人猿だという主張はオルダス・ハクスレーの小説やグールドのエッセイでも取り上げられているが,本書の自己家畜化説にとって本来比較すべきなのは類人猿ではなく更新世のヒト属になる.そしてネアンデルタール化石を比較するとサピエンスは頭蓋と顔に幼若化の特徴がある.そしてネアンデルターレンシスとサピエンスの交代の要因にはおそらく(自己家畜化の結果としての)サピエンスの協力行動傾向がある.
- そして家畜化された動物の協調性は野生の祖先より高い.(指さしの理解などについてのイヌとオオカミの差,ベリャーエフのキツネと野生のキツネの差が解説されている)
- ヒトの同性愛も家畜化症候群の症候の1つだと考えられる.同性愛についてはこれまで様々な適応仮説が呈示されてきたが,検証に耐えるものはなかった.同性愛が反応的攻撃性の抑制と関連することを示唆する事実がいくつかある.ヒト以外で排他的な同性愛傾向が存在することが見つかっている唯一の動物は家畜化されたオスのヒツジになる.同性愛を示すヒツジはテストステロンの曝露量が少ない傾向がある.そしてヒトの男性の同性愛指向と(胎児期のテストステロン曝露量と相関すると言われる)指の2D4D比率には相関がある.また自己家畜化されたボノボはチンパンジーよりも同性愛的行動が多い.そして多くのリサーチがヒトの同性愛の適応的利点を示すことに失敗していることも,同性愛傾向が家畜化による副産物だとするとうまく説明できる.
最後の同性愛についての自己家畜化副産物仮説は本書のテーマと直接関わり合いがなく,とってつけたような話になっている.ランガムとしては面白い仮説として書き残しておきたかったということだろう.ヒトのある種の同性愛傾向についてのこれまでの進化的な説明仮説には決定的なものがなく,ランガムのこの説明はなかなか興味深い仮説になっている.ただヒツジ以外の家畜ではあまり見られないということなのでやや説得力が落ちる印象があるのは否めない.
第10章 善と悪の進化
第10章では道徳が取り扱われる.ランガムは利他性の問題と道徳の問題を明確に切り分けている.そしてヒトの道徳も処刑制度にかかる淘汰産物として説明できるというのがランガムの主張になる.
- ヒトの利他性の進化については「集団にとって有益だったから」というグループ淘汰的考え方に人気がある(ダーウィン,ハイト,ボーム,ボウルズ,ドゥ・ヴァール,トマセロ,ソーバー,DSウィルソンたちの名が記されている)
- しかしそれは利他性進化の唯一の理由ではない.それは結局個人にとって有利だったからであり,集団の利益は二次的だったと考えられる.ボームはその個人的利益は処刑されるリスクに対する保身だと考えた.
- では道徳はどうか.本書では道徳とは「善悪の感覚に導かれた行動」と解釈する.そして道徳の進化については次の3つの問題を考えよう.(1)何故ヒトは他者に親切にするように進化したか(2)いかにして道徳的決定を下すか(3)なぜ他者の行動にも目を光らすのか(道徳の干渉性)の3つだ.これまでの考え方はこれらをうまく説明できない.
- (1)何故ヒトは他者に親切にするように進化したか:ヒトには血縁淘汰や互恵性*12で予想される範囲を超えて他者に親切に振る舞う傾向がある.これは理性によるものだと考える人は多いが,幼児期から見られることや最後通牒ゲーム実験の結果からもそうではないと考えられる.グループ淘汰で説明しようとする人も多いが,狩猟採集民での道徳規範が男性に有利である(男たちは互いに向社会的に振る舞うが妻や親族の女性を搾取する)ことを説明できない.
- (2)いかにして道徳的決定を下すか:道徳の一貫性を求める学者たちは伝統的に功利主義と義務論の概念を用いて説明しようとしてきた.しかしどちらも一部にしか適用できず,全体的な説明にはなっていない.(それぞれの立場の問題点,道徳的判断におけるバイアスの問題が解説されている)
- (3)なぜ他者の行動にも目を光らすのか:チンパンジーには群れのためにならない行動を行った個体を罰するということがない.これはヒトと対照的であり,どう説明するかが問題になる.
- ボームは狩猟採集時代のヒト集団において,下位男性の連合が支配的な男を制御する能力を手に入れ,(自己家畜化をドライブしただけでなく)その権力を行使し始めたと考えた.そこでは集団内の男性間では平等主義が制度化され,女性支配を行うようになる(家父長制の誕生).
- この考え方は先ほどの3つの謎をうまく解決できる.(1)他者に親切にするのは処刑リスクへの適応だ(ボームはこれをグループ淘汰的に解釈しているが,個体利益で説明可能だ).(2)道徳判断の不作為,副作用,非接触バイアスは非難に対する弁明として考えると意味がある(自分は何もしていない,それが目的ではなかった,指一本触れていない).道徳的な行為とは集団からなされる非難から自分を守る行為なのだ.良心を「誰かに見られているかもしれないと警告する内なる声」と解釈するのは正しい理解なのだろう.(3)互いに行動を見張り合うのは,自分が非協力者と見做されないように身を守るためだ.
- そして自分が処刑される立場にならないために新たな情動反応が進化した.それが恥,気まずさ,罪悪感,仲間はずれにされる苦痛などになる.また何が「悪」かは文化によって異なるので,それを学習し身につけるためのメカニズムである「規範心理」が進化した
- ボームによれば道徳心理は処刑されないための適応だ.これは本書の核になる主張でもある.そしてこの説によればヒトの道徳の起源は意外と邪悪であることになる.それは男たちの権力争いの過程で生まれ,男たちの連合による絶対権力を持つ専制政治を生みだし,社会を拘束して道徳原則に従わせたのだ.
この道徳に関するランガムの主張はなかなか面白い.ここでランガムは「下位男性の連合が支配的な男を制御する能力を手に入れた」とするボームの考え方についてグループ淘汰解釈を否定した上で基本的に認めている.これは事実の問題としては第8章で扱われたとおりだが,どのようにそうなったかについては説明していない.
ここは私にとってはボームを読んだときにも感じた最大の理論的な謎だ.下位男性連合が権力をもつのは唯一のESSではない.優位男性を含むグループが成立して,その他メンバーを搾取する形もESSになりうる.通常このような複数ESSは初期条件によってどこに落ちるかが決まる.そして実際に農業革命以降はほとんどすべての社会で階層社会に移行している*13ので,なんらかの初期条件依存の力学がそこにはありそうだ.いずれにしてもここに説明できていない部分が残っているということになるだろう.
第11章 圧倒的な力
ヒトのサピエンス系統において狩猟採集社会で処刑制度が成立し,自己家畜化により反応的攻撃性は抑制された.第11章では能動的攻撃性がどうなったのかが扱われる.
- 19世紀の小説「ジキル博士とハイド氏」で描かれるハイドの悪徳はすべて反応的攻撃性だ.そして理性によりそれを抑えれば善になるという寓意は自己家畜化による攻撃性の抑制と整合的だ.しかしこの小説は能動的攻撃性を扱っていない.そしてこの能動的攻撃性に対する無関心はこれまでの進化生物学者にも見られる.
- ヒトを考える上で「連合による能動的攻撃性」,特に「勝利を確信できるほど有利な状況で計画的に相手を攻撃する行動」は非常に重要だ.通常,戦争における暴力的行動はほとんどこれだ(古典的奇襲戦法).市民社会の維持もこれによっている(警察による逮捕).
- 能動的攻撃性は動物界では稀だ.しかし社会性の霊長類や食肉目動物では見られることがある.典型例はハヌマンラングール,チンパンジー,ライオンなどで見られる子殺しだ.さらにチンパンジーやオオカミでは近隣群れのおとな個体への攻撃が観察されている.これらには適応的な価値があると考えられる.(観察事例を含めて詳しく解説されている)
- このチンパンジーの襲撃の適応的説明について,発見当初に心の準備がなかった人類学者たちは断固拒否の姿勢をとった.ヒトの殺人への考え方への影響を恐れたのだ.しかし今ではこれはチンパンジーの1つの特徴であり適応的に説明できるということで決着している.
- 適応的な価値があるならなぜ能動的攻撃は動物界で比較的稀なのか.それは通常の場合攻撃個体にも負傷などのコストが大きいからだ.連合を作って必勝のパターンで攻撃できる動物(社会性の霊長類と食肉目動物)においてのみこのような攻撃が進化することができるのだろう.
- では動物の能動的攻撃性とヒトのそれは同じものか.狩猟採集民のリサーチは答えがイエスであることを教えてくれる.彼等は集団間で頻繁に戦争を行う.攻撃隊は多くの場合男性のみ5~10名で自分たちが圧倒的な有利な状況での待ち伏せや奇襲を行う.これはチンパンジーによく似ている.ヒトの連合による能動的行動は集団間の争いが起源になり,それが精緻化したものだろう.
- そして起源としては集団間の争いのための能動的攻撃性が,集団内の権力闘争に用いられるようになり,専制政治の形式が生まれた.集団内では能動的な連合が権力を持ち,その他のものはそれに服従する.
- 能動的攻撃性は反応攻撃性の抑制と道徳(つまり善)を生んだが,同時に大量虐殺,奴隷制度,いじめ,生け贄の儀式,リンチ,ギャングの抗争,政治的粛正(つまり悪)の原因でもある.
この部分のランガムの考察も面白い.集団間の戦争は能動的攻撃性を精緻にし,それは狩猟採集時代には下位男性グループの権力掌握を可能にし,農業革命以降,様々な集団内専制政治の道具として使われることになったというわけだ.
第12章 戦争
第12章では戦争が扱われる.
- このような連合による能動的攻撃性を適応と考えることについて,ルソー派は「もしそうなら我々は戦争を避けられないことになってしまう」と考えて抵抗した(しばしば更新世における戦争の存在自体を否定した).しかしそれは間違った生物学的決定論であり,ある行動傾向が進化的産物であるとしてもそれを避けたり減らしたりすることはできる.暴力は社会的に影響を受け,社会的に防ぐことができるのだ.連合による能動的攻撃性は首謀者たちが犠牲を払わずに成功すると考えたときにだけ発揮されるのであり,そうした状況がなければ抑制されるのだ.
- では戦争はどう考えるべきか.戦争には単純なものと複雑なものがある.
- 進化適応的に説明しやすいのは単純な戦争であり,これはチンパンジーのオス集団の襲撃に似ていて,軍のような階層構造を持たない小規模な男性集団による短時間の奇襲攻撃だ.成功すると隣接グループの勢力を弱められ,戦士には女性や物品や名誉の報酬がある.殺しの快楽,報復,集団内の評判という社会的圧力が至近的な動機となる.また単純な戦争の長い歴史の中で自然淘汰は連合による能動的攻撃性に磨きをかけただろう.
- 複雑な戦争は政治的なリーダーシップがある社会で勃発し,指揮官が方針を決めて兵士が従う.組織化された軍において兵士に戦争参加の拒否権はない.兵士の戦闘への参加への至近的な動機は,生き延びるチャンスを広げることと親しい仲間に軽蔑されないことだ.後者は処刑への恐怖反応から進化した道徳感覚から着ているのだろう.
- 複雑な戦争において指揮官は純粋な能動的攻撃性を示す.指揮官は必勝の計画を立て奇襲を好む.そして実際の軍事史でしばしば見られる「軍事的無能」は進化環境で有利だった自信過剰や自己欺瞞が複雑な戦争という新奇環境とミスマッチしているとして進化的に説明可能だ.
- 本書はヒトの善と悪についての理解を深めるために書かれているが,その議論から戦争についての悲観論に反論することができる.
- 仮に更新世のヒトの攻撃性が適応だったとしても,それを減少させることは可能だし,実際に暴力に起因する死亡率は長期的に低下し続けている.
- ただしこの傾向を継続させるためには不断の努力が重要であり,強固な制度と警戒が必要だ.課題となるのは資源の分配が変わるにつれて既存の主権に対応する連合の再編成が繰り返される可能性があることだろう.
前段でよくある誤解を避けるための注意書きがあり,そこから(進化環境であったような)単純な戦争と,新奇環境である複雑な戦争が区別して解説されている.最後のリマークも深いと思う.
第13章 パラドックス解消
最終章はここまでの議論をまとめ,ヒトの善悪の本性のすべての起源が言語と意図共有にあると主張している.
- ヒトは反応的攻撃性が弱く,能動的攻撃性が強い.何故このような独特の組合せが進化したのか,そしてそれはヒトの理解にどう役立つのか.
- ヒトは言語による共謀が可能になり,横暴な上位者の殺戮が可能になったことにより自己家畜化が生じて反応的攻撃性が抑えられた.社会は平等主義になり道徳感覚が生まれ同調傾向は強化された.同調行動は道徳の強制者とその支持者の集団に恩恵をもたらした.
- 狩猟の化石的証拠から見ると,連合による能動的攻撃性の高さは少なくとも250万年前には発動されていただろう.そしてそれは言語と意図共有能力の発達により,利害を通じた説得による同盟関係が築けるようになって大きく変わった.主導権は横暴なボスから下位者の連合に移り,それは男性年長者集団の支配につながった.要するに言語が高い殺傷能力と低い感情的反応が同居するヒトを創り出したのだ.
- ヒトの理解という観点からいうと,まず本書の議論は(進化的に語られた壮大なストーリーではあるにしても)過去の説明であり未来の予言ではない.今日の社会的制度はみな進化的には新奇なものであり,これからも変わっていく可能性が高い.
- もう1つ,進化はヒトの心にバイアスを残しているということがある.集団も個人も常に権力争いに興味があり,暴力抑制には積極的な行動と緻密な組織制度が必要になる.私たちはその道を歩き始めているが,まだ先は長い.
以上が本書の概要になる.ヒトの善悪が同居するような本性について,反応的攻撃性と能動的攻撃性を区別し,自己家畜化をキーにすることにより説得力のあるストーリーを呈示している.利他性について間接互恵や社会淘汰の影響と処刑からの保身の影響(どちらがどれだけ効いているのか)についてどう見ているか,なぜ下位者男性集団の連合が成立したのか(その他の連合が生じなかったのはなぜか,農業革命以降階層社会になったのはなぜか)という点についてやや説明が欠けているとはいえ,その他の部分は見事に大きな構図を描けている.今後ヒトの利他性を議論する際には必須の参照文献の1つになるだろう.
関連書籍
原書
同じくヒトの自己家畜化を扱った本.ランガムの共同研究者の1人ブライアン・ヘアとその妻ヴァネッサ・ウッズによるもの.私の書評はhttps://shorebird.hatenablog.com/entry/2021/03/06/111046
本書の議論に大きく影響を与えているボームの本.私の書評はhttps://shorebird.hatenablog.com/entry/20141228/1419728069

- 作者:クリストファー ボーム
- 発売日: 2014/11/01
- メディア: 単行本
同原書

Moral Origins: The Evolution of Virtue, Altruism, and Shame (English Edition)
- 作者:Boehm, Christopher
- 発売日: 2012/05/01
- メディア: Kindle版
本署では批判されている偏狭的利他主義仮説にかかる本.私の書評はhttps://shorebird.hatenablog.com/entry/20180314/1520983936

- 作者:サミュエル・ボウルズ,ハーバート・ギンタス
- 発売日: 2017/01/31
- メディア: 単行本
同原書

A Cooperative Species: Human Reciprocity and Its Evolution (English Edition)
- 作者:Bowles, Samuel,Gintis, Herbert
- 発売日: 2011/05/31
- メディア: Kindle版
このほかのランガムの本
ヒト進化における火の使用あるいは料理の重要性を説いた本.私の書評はhttps://shorebird.hatenablog.com/entry/20100521/1274438472

- 作者:リチャード・ランガム
- 発売日: 2010/03/26
- メディア: 単行本
同じくランガムの本.暴力性の性差については古典ともいうべき本

- 作者:ランガム,リチャード,ピーターソン,デイル
- メディア: 単行本
編者や共著者として以下のような本にも関わっているようだ.いずれも邦訳はない.

Chimpanzees and Human Evolution
- 発売日: 2017/11/27
- メディア: ハードカバー

Primate Societies (English Edition)
- 発売日: 2008/06/03
- メディア: Kindle版

Ecological Aspects of Social Evolution: Birds and Mammals (Princeton Legacy Library, 3222)
- 作者:Rubenstein, Daniel I.
- 発売日: 2006/06/29
- メディア: ペーパーバック

Science and Conservation in African Forests
- 作者:Wrangham, Richard
- 発売日: 2008/08/14
- メディア: ペーパーバック
オルダス・ハクスレーの小説.不老不死を求める大富豪の話で,ヒトがネオテニー化した類人猿であるというアイデアがプロットに大きくかかわっている.

夏幾度も巡り来て後に AFTER MANY A SUMMER
- 作者:オールダス ハックスレー
- 発売日: 2012/10/01
- メディア: 単行本

After Many a Summer Dies the Swan: A Novel
- 作者:Huxley, Aldous
- 発売日: 1993/01/01
- メディア: ペーパーバック
あまりにも有名なスティーヴンソンの小説

- 作者:スティーヴンソン
- 発売日: 2017/04/25
- メディア: 文庫

Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde Annotated
- 作者:Stevenson, Robert Louis
- 発売日: 2021/04/23
- メディア: ペーパーバック
*1:英米法では謀殺(murder)と故殺(manslaughter)の差がこれになる.日本刑法にはこの区別はなく,人を殺す認識があれば,事前に計画があろうが,その場でかっとなってやっただけだろうがどちらも殺人罪で,あとは情状酌量の問題になる.もっとも英米法でも謀殺と故殺の境界はなかなか微妙な問題で,アメリカでも州によっては「殺人者が数秒間前もって行動を考えれば」謀殺にするに足りるということになっているそうだ.ランガムはこの区別についての普遍的に受け入れ可能な定義はないと説明している.
*2:これまでの家畜動物の野生化が野生種がいるところで生じていないことを考えると,種内競争が重要なのかもしれないとコメントがある
*3:扁桃体と視床下部の発達に関わる
*4:ランガムはモロッコのジュベル・イールドの化石をサピエンスと認める立場を採る
*5:脳の小型化についても議論されている.サピエンスで明確に小型化が見られるのは3万5千年程度前からだが,それが家畜化のためなのか身体の小型化に伴うものなのかについては争われているそうだ.
*6:ランガムはこれは処刑仮説の萌芽であるがダーウィンがヒトの家畜化を否定した部分とは矛盾すると指摘している.しかし実際にこの箇所を読むとダーウィンがあれこれ考えている部分の一部であり,基本的な道徳の進歩については「仲間による賞賛,共感の習性,お手本と模倣,理性,経験,自己の利益,教育,宗教的感情が要因であり,自然淘汰の効果はわずかである」としている.また貧困で見境がなくしばしば悪徳に犯されている人間が早く結婚して子どもを多くもうけること(そしてその淘汰的結果)に対する歯止めの1つとしても考察対象になっている
*7:ランガムはこれもその最初の提唱者はダーウィンだと指摘している.ダーウィンは戦争時の勇敢さは主に仲間からの賞賛によって強められたとしている.しかしそれがそういう個人の多い部族を有利にしただろうとグループ淘汰的な記述も行っている.これはダーウィンの膨大な書き物の中で唯一明確にグループ淘汰的な部分になる.
*8:このランガムの呈示する偏狭な利他主義仮説の問題点はなかなか説得的なところがあって面白い.なお私はさらに,そもそも協調的傾向が戦争で有利であったという証拠が無いこと(残酷な規律を持つ軍隊である方が有利かもしれない),戦士は男性であったのに協調的傾向にほとんど性差が見られないことも重要な問題点だと思う
*9:本書ではexecutionとcapital punishmentを共に「処刑」と訳している.しかしcapital punishmentは通常「死刑」の意味であり,なぜこう訳しているのかは不明だ
*10:理屈の上では処刑以外でも暴君に対処できればいいことになる.実際には次章にあるように狩猟採集民では広く処刑が見られることから処刑制度の成立が説明できればいいということなのだろう
*11:構成としてなぜこれを第9章に持ってきたのかはよくわからない.ストーリー的には第6章のあとの方がすっきりしただろう
*12:ランガムは本書において進化生物学的な互恵性について説明しているところでreciprocityではなくmutualismを用いており,訳者はこの訳語として「共生」を当てている.しかし仮説の名称としてはよく使われる用語を用いた方がわかりやすいと考えて本書評では「互恵性」としている.なおランガムの「mutualism」を生かすとしても「相利主義」とでも訳すべきであっただろう(「共生」ではsymbiosisと誤解されるリスクがあるように思う.)
*13:ランガムはこの移行についてもあまりきちんと解説してくれていない.どのような条件で移行するのかまだよくわかっていないので詳しい描写を避けたのかもしれない