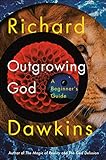
Outgrowing God: A Beginner's Guide (English Edition)
- 作者: Richard Dawkins
- 出版社/メーカー: Random House
- 発売日: 2019/10/08
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
本書はリチャード・ドーキンスの最新刊になる.ドーキンスは「The Selfish Gene(邦題:利己的な遺伝子)」で有名な進化生物学者だが,2006年に「The God Delusion(邦題:神は妄想である)」を著し,デネット,ハリス,ヒッチンズと並ぶ新無神論の主導者の1人となった.本書はそこで主張された新無神論をさらにかみ砕いて初心者向けに書き下ろしたものになる.2011年の「Magic of Reality (邦題:ドーキンス博士が教える「世界の秘密」)」では子ども向けに新無神論を含んだ内容を書いているが,想定読者層はそれより少し上からということなのだろう.
題名にある「outgrow」という動詞は(何かを超えて成長するというのが直接の意味だが)「子どもが成長して(おもちゃなどから)卒業する」という文脈で使われる.だから本書のタイトルは直訳的には「神様から卒業する」というほどの意味になるだろう.
序章やイントロダクションはなくいきなり第1部が始まる.
第1部 さようなら神様
第1部ではキリスト教,イスラム教などの教えがいかに奇妙で根拠の無い内容のものであるかが描かれる.
第1章 何と多くの神
ドーキンスは世界の多くの宗教が多神教であることから始めている.ギリシアやローマの神々の名を上げ,現代の西洋人はこの神々については無神論の立場に立っていることを指摘する.ここで一神教とされているキリスト教においても,父と子と精霊という三位一体教義,聖母マリア,様々な聖人,天使などの概念があり,多神教的であることをちょっと揶揄したのちに,核心に触れる.人はたまたまある宗教集団に生まれ,その神を信じるようになる.なぜたまたま自分が産まれた集団の神だけが正しくて,他集団の神が間違いだということになるのかという問いかけだ.
ここで不可知論についても1本入れている.不可知であること,つまり想像できるが誰もその不存在を証明できないことは何十億もあるが,その存在を信じるべき理由がない場合には普通はそれを信じない.我々は妖精やアポロ神に対してはそういう立場をとっている.なぜヤハウェだけ別扱いにするのかというわけだ.
第2章 でもそれって本当?
信仰者は信仰の理由としてしばしば聖書を持ち出す.では聖書はどの程度のものなのかが第2章のテーマだ.ドーキンスは伝言ゲームによる情報の劣化を説明した上で議論を始める.
最初は歴史的事実としてイエスは実在したか.ドーキンスは,4つの福音書は後代の書物で誰が書いたかもあやふやで信用できないし,パウロ書簡もイエスについての事実の記述がなく根拠とはしにくいが,ユダヤの歴史家ヨセフス,ローマの歴史家タキトゥスの記述を吟味すればそれは同時代的な記述であり,実在していた確率が高いとして良いだろうとする.
では聖書について同じように吟味するとどうなるか.福音書はイエスの死後何十年も経ってから書かれたまさに伝言ゲームの世界になっており,互いに矛盾する記述もある.そこに書かれているイエスが起こした奇跡についてはケネディ暗殺を巡る陰謀論と同じようなものだと示唆する.
そしてこの調子で,ヨハネの黙示録など福音書以外の新約聖書も事実を示す記述として信用できないものであることを延々と示していく.このあたりは現在キリスト教と聖書を何となく信じている人に対する丁寧なガイドということになるだろう.4つの福音書以外の様々な福音書の内容とそれが新約聖書に含められなかった理由の推測はなかなか面白い.そしてある記述を信じるかどうかを決めるに際しては,その記述にあることが本当に生じそうな確率とその記述が嘘である確率を比較することを勧めている.
第3章 神話とその起源
第3章は引き続いて旧約聖書を取り上げる.旧約聖書を理解するには,それは1つの神話であり,それがどう始まるのかを考察するのが良いというのがドーキンスの示唆になる.そしてアブラハム,エジプトからの脱出などの事実性についてまず何の根拠もないことを示す.しかしバビロン捕囚については歴史的な事実である証拠がある.つまり旧約聖書はそれが書かれた紀元前6世紀頃の事実と神話の混合物なのだ.ここも丁寧に紀元前6世紀以前の記述についてはでたらめだったり(家畜化された年代から見てアブラハムがラクダに乗って移動したはずはない)他民族の神話や伝承の借用(ノアの方舟の原型がシュメール神話にある)であることを延々と解説している.
そして神話は事実ではなく,それはいとも簡単に始まって広まりうるということをエルビス伝説,ニューギニアのカーゴカルト,モンティパイソンの「ブライアンの人生」,モルモン教の例を上げて説明している.
第4章 善の本か?
多くの宗教者は聖書には道徳が書かれており,それは聖書を信じる理由になる,あるいは聖書なしでは善悪が相対的になりこの世は地獄になると主張する.これが第4章のテーマになる.
ここでは旧約の神がいかに残酷で(ノアの洪水,イサクの燔祭),他神への信仰に対してジェラシーの塊である(他神信仰部族に対してジェノサイドを命じている)ことを示していく.次に新約では原罪への執着のすさまじさ(キリストの贖罪をよく考えるといかに醜悪な論理であるか)を指摘している.
第5章 善であるためには神が必要なのか?
宗教が善悪を教えないと人々は自分勝手な善悪の判断をして社会が崩壊するのか.アメリカでは今でもそう信じている人が多い.ドーキンスは,バーニー・サンダースを民主党の大統領候補にしないために,クリントン派がサンダースは無神論者ではないかというキャンペーンを行うことを検討したという逸話を紹介しつつ,この問題を論じる.
まず「神は天から人々を見張っている警官だ」という考え方を取り上げる.ドーキンスは誰から見られているところでは良い人であるように振る舞うという傾向は(残念ながら)確かにヒトの本性の一部だと認める.そして聖書では恐ろしい罰があると警告している.(ここでドーキンスは,ありそうもない罰であるほどそれは恐ろしいものだと強調せざるを得なくなるのだと示唆している)
しかし実証的に調べると,信仰心と行動傾向に相関はない.アメリカでは囚人がキリスト教徒である確率は無神論者である確率より750倍も高い(もちろんそう申告した方が仮釈放されやすいだろうというのが背景にあるだろうとはドーキンスも認めている)のだ.
次は「聖書は人々に良いロールモデルを与えている」という考えを吟味する.本当にそうなのか,ドーキンスはここで十戒を1つずつ吟味する.ちょっと詳しく紹介しよう
- (1)「他神を信仰するな」(2)「偶像を崇拝するな」:この2つは単にジェラシーに過ぎないだろう.
- (3)「神の名をみだりに用いるな」(4)「安息日に働くな」:これらがそんなに邪悪な犯罪なのだろうか.
- (5)「父母を敬え」:これはナイスだ
- (6)「人を殺すな」:確かにこれは重大な犯罪だが,(一神教以外も含んだ)どのような法体系でもこれは犯罪とされている.そして聖書の中では他部族への殺人は罪とされていない.旧約ではこれは「自分と同じ部族の人を殺すな」という狭い意味でしかない.
- (7)「浮気をするな」:これはわかりやすいが,しかし結婚が破綻しているなど許される状況があってもいい.
- (8)「盗みをするな」:これに異論はない.そしてやはりどのような法体系でもこれは犯罪とされている.
- (9)「隣人に対して偽証するな」:確かに偽証はするべきではない.しかしなぜ隣人にだけ限定するのか
- (10)「隣人の財産,妻.奴隷,家畜をうらやむな」:行動ベースでないものを犯罪とすべきだろうか.そして妻を財産扱いするのはどうなのか.
要するに十戒は時代遅れなのだ.そしてそこが重要だ.我々は紀元前6世紀から前に進んでいるのだ.
続いてドーキンスは新約に進む.「右の頬を打たれたら左の頬を差し出せ」というのは旧約にある報復主義を超えていてイエスは時代を先取りしていたと評価できる.しかしイエスが報復主義的な行動をした記述(マタイ伝:無花果の奇跡)もある.信仰のため家族を捨てるように命じる記述(ルカ伝:イエスに従うことの困難)もある.
そしてこのような記述に直面した現代の宗教家は,これを寓話だとして取捨選択する.ここがドーキンスの力点になる.一体その取捨選択する基準はどこから来るのだろうか(それが聖書にあるはずはない)というわけだ.
第6章 善をどう決めるのか?
ドーキンスはまずヒトの本性に利他的な部分があることを指摘し,しかし実際の道徳規準は時代と共に大きく移り変わっていることを強調する.旧約の世界ではもちろん,アメリカでもリンカーンの時代まで奴隷制は存続していたし,戦争時の残虐性の基準は第2次世界大戦以降大きく変化している.
なぜ変化するのか.ドーキンスはピンカーを引用しながら,それは我々が互いに影響を与え合っているからだと説明している.そしてここで道徳哲学を初心者向けに概説している.この帰結主義者と絶対主義者の対話篇は面白い.
そこまで予習した上で「善であるために神が必要か」の議論に戻る.我々の道徳的価値観は時代と共に変化している.それは聖書に固定されたような道徳律には収まらない.そして実際に我々の持っている21世紀の道徳観は聖書の道徳観と合わないのだ.つまり道徳を理由とした宗教擁護は成り立たないということになる.
第2部 進化,そしてそれを超えて
ドーキンスは第1部で,神を信じる根拠として,宗教が真実を教えているから,宗教が道徳の基礎であるからという議論を否定した.しかしもう1つ神を信じる動機がある.それはこの精妙で美しい世界にはデザイナーがいるはずだという感覚だ.第2部はここを取り扱う.そしてそれはドーキンスが新無神論にたどりついた理由でもある「進化」の説明が含まれる.
第7章 この世界にはデザイナーがいるはずなのか?
ドーキンスは様々な生物界の精妙なデザインを挙げる.ガゼルとチータの(草原を疾走する能力の)アームレース,カメレオンの舌,シャコの超高速パンチ,タコの体色変化,脳と神経細胞の複雑性,細胞内の化学反応の精妙さ,クジャクの羽の美しさといかにも楽しそうに解説する.これらの背後に完璧なデザイナーを見てしまうのはある意味無理もない話になる.
この議論に対してドーキンスはまずデザインが完璧でないこと,(脊椎動物の眼の盲点や反回神経の経路など)を指摘し,そしてもしこのデザイナーがチータにガゼルを狩る能力をデザインし,ガゼルにチータから逃れるデザインしたのだとすると,そもそも彼は一体何を意図しているのだろうかと問いかける.つまり全能のデザイナーは説明にならないのだ.
なおタコの体色変化についてのこの動画が紹介されている.何度見ても驚きの映像だ.
Octopus vulgaris Camouflage Change
第8章 ありそうもなさへのステップ
なぜ人々は適応形質の背後にデザイナーがいると感じるのか,それはその形質の(偶然で生じると考えるときの)ありそうもなさ(improbability)から来る.人々は形質の説明には偶然かデザインかの二択しかないと考えるからだ.これはウィリアム・ペイリーの議論でもある.
ダーウィンはここに3番目の選択肢を与えたのだ.ドーキンスは自然淘汰の説明に入る.この解説はさすがに手練れの手によるものでトレードオフやアームレースに踏み込み,簡潔で深い.
第9章 結晶とジグソーパズル
ここからドーキンスは適応産物が形作られる至近メカニズムの説明に入る.初心者に納得してもらうにはそこも重要だという判断だろう.最初に結晶の成長のメカニズムを解説し,そこからバクテリオファージの形成原理(3次元ジグソーパズル),化学反応と触媒の原理,そして様々な物質が細胞内でセルフアセンブリーされる仕組みに進む.この自動組立の鍵になるのは触媒のオンオフ調整であり,それがDNAによってなされていることまで解説される.
第10章 ボトムアップかトップダウンか
では生物個体はどう組み立てられるのか.ドーキンスは発生の仕組みに進む.発生がうまく進むことには強い自然淘汰圧がかかる.ここでドーキンスの十八番である「DNAによる発生指令はレシピであって設計図ではない」という概念が強調される.本書ではシロアリのアリ塚とバルセロナのサグラダファミリアの違いとして解説されている.このあと実際の発生の進行(分割,胞胚,原口形成)が図解され,この様子はレシピ的なコンピュータプログラムでかなりうまくシミュレートされることが示されている.
第11章 我々は宗教的になるように進化したのか.我々は善に向かって進化したのか
生物界のデザインは自然淘汰で説明できる.ではヒトの宗教心もそうなのだろうか.ドーキンスはおそらくそうだろうと答え,物事の背後にエージェンシーとその意図があると過剰に感じる傾向が,重大なリスクに対する火災報知器原理によって説明できること,両親や身近な大人に教示されたことを信じる傾向もそれが進化環境で有利だったとして説明できることを指摘し,神を信じる傾向はそれらの副産物として理解できると主張している.これは宗教の副産物説ということになる.
ドーキンスはここで副産物説とは別のミーム的な説明や「宗教がそれが属するグループや国家に有利だったから」というグループ淘汰的説明(これは真の進化的説明ではないがとことわりつつ,イスラム帝国やラテンアメリカのスペイン征服地の増大はそういう側面があるし,集団内の団結心に役立つこともあるだろうと認めている)も紹介している.ただここでは様々に互いに排他的でない説明があるというところにとどめている.ここで深入りするのは本書の目的から見て得策ではないということだろう.
続いて(宗教なしに善悪があるのかという問いかけに対する回答として)善の基礎の進化もここで扱っている.ここもあまり深入りせずに,血縁淘汰的説明,互恵利他的説明を簡単に行うにとどめている.しかしそれは基礎的な部分に過ぎず,現在のヒトの道徳を論じるなら時代と共に変わっていくいわば学習された道徳規準が重要なのだとコメントしている.いずれにせよ神を信じる心自体進化で説明でき,善であるために神が必要なわけではないのだというのが本章の結論になる.
第12章 科学から勇気をもらおう
ここまでの議論をしても宗教擁護派はギャップの神(まだ科学で説明されていないことは神の領域だとする主張)に逃げ込む.これに対するドーキンスの答えが本章の議論になる.それは最初にギャップだと思われたことでも科学が常識的にとても信じられないような答えを出してきたこと,そしてそれが真実だったことを見ていこう,その真実に立ち向かう勇気を持とうということだ.そしてその例としてガリレオの力学,月は地球に対して自由落下しており質量はあっても重量を持たないこと,地動説,大陸移動説,原子核と電子のあり方から見ると通常の物質はほとんど真空からなること,分子や原子の小ささ(あなたが今飲んでいるコップ一杯の飲み物にカエサルの尿に含まれていた原子が1個以上含まれている確率はほぼ100%であること),特殊相対性理論,量子論が挙げられている.
ここでドーキンスは後付けで考えるといかにも単純な自然淘汰の議論がなぜ19世紀まで見過ごされていたのかを考察している.そしてそれは自然界の複雑さ,美しさ,目的論的デザインがあまりにも強力に知性を持つデザイナー説を指し示しているように感じられ,そこを飛び越えるにはとびきり大きな知的勇気が必要だったからだろうとコメントしている.
そしてそのような勇気を持って取り組むべきなお解決されていない問題の例として物理定数の決定問題をあげ,この解決もマルチバース説と人間原理を用いれば見通せるのではないかとしている.ドーキンスは最後に,この見通しが真実だとするのはまだ早いが,これまでの科学の軌跡を考えれば,勇気を持って立ち向かい,成長し,神様から卒業できると思うと述べて本書を終えている.
新無神論を世に問うた「The God Delusion」は,論敵として宗教家,哲学者,宗教擁護的リベラルインテリなどを想定しており,ややテクニカルな議論が多く,厳しい指摘や皮肉っぽい批判もあって,多くの普通の人々に必ずしも共感を持ってもらえるような本ではなかっただろう.本書はそこを埋めるべき本で,神の実在に何となく疑いを持っているがなお踏み出していないような人達に向けて優しくカミングアウトの手伝いをするという本としてよくできている.宗教の主張は真実ではなく,宗教なしでも道徳は崩壊せず,自然界のデザインや宗教心自身も唯物的に説明できるのだというところに絞って扱っているのもそういう趣旨だろう.私的には結晶から発生のところの説明振りがなかなか楽しい一冊だったという感想だ.
関連書籍
ドーキンスが新無神論を世に問うた本.私の書評はhttps://shorebird.hatenablog.com/entry/20070221/1172066931
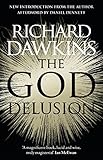
The God Delusion (English Edition)
- 作者: Richard Dawkins
- 出版社/メーカー: Transworld Digital
- 発売日: 2009/09/22
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
同邦訳.

- 作者: リチャード・ドーキンス,垂水雄二
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 2007/05/25
- メディア: 単行本
- 購入: 14人 クリック: 257回
- この商品を含むブログ (185件) を見る
第8章関連では唯一邦訳されていないドーキンス本.なかなか楽しい本だけに未邦訳のまま取り残されているのは残念だ.
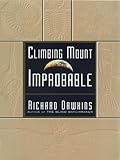
Climbing Mount Improbable (English Edition)
- 作者: Richard Dawkins
- 出版社/メーカー: W. W. Norton & Company
- 発売日: 2009/06/01
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログ (1件) を見る