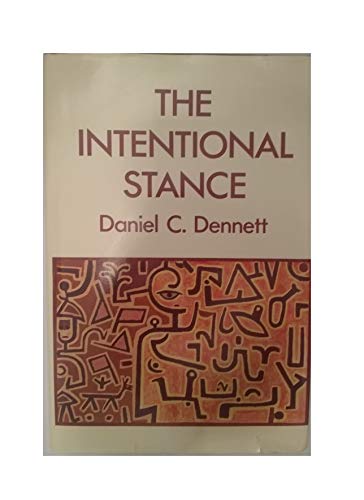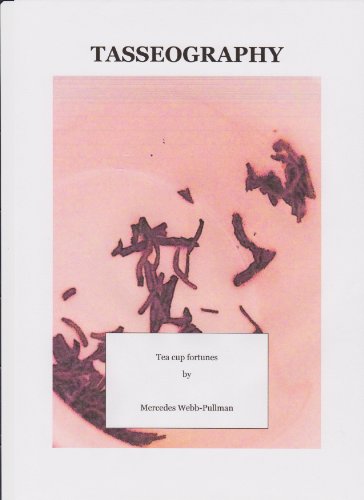本書は認知と文化が専門の認知科学者,心理学者であるトム・スコット=フィリップス*1によるヒトの言語の進化と起源に関する一冊.ヒトの言語の進化的起源については,霊長類などの信号システムとの連続性を前提に,再帰的構造を重視する議論*2が主流だが,本書においては,ヒトの言語と霊長類の信号システムとの非連続性を強調し,語用論の重要性を正面から採り上げる独自の議論が説得的に主張されていて,とても興味深い書物になっている.原題は「Speaking Our Minds: Why human communication is different, and how language evolved to make it special」
第1章 コミュニケーションへの2つのアプローチ
冒頭で,言語の持つ決定不十分性の問題(コンテキストにより様々な意味になる)を採り上げ,これは言語がそれまでの動物の信号システムと全く異なるコミュニケーション様式の上に乗っていることからくるのだと主張する.最初からなかなかスリリングだ.
- コミュニケーションについては,コードモデルと意図明示・推論モデルを立てることができる.ヒト以外の動物の信号システムはコードモデルに乗っているが,このモデルではヒト言語の決定不十分性を説明できない.
- コードモデルとは通信(コミュニケーション)についての導管モデルとシャノンの情報理論と整合的な考え方だ.信号は経路(導管)を伝わる情報であり,送信側でエンコードされ,受信側でデコードされる.そのポイントは世界のある状態が特定の信号と連合(association)しているというメカニズムにある.この連合は決定論的である必要はなく確率論的なものでもよい.動物の信号システム,ヒトのコミュニケーションのうち化学的刺激(乳輪から出る化学物質が乳児に乳首の位置を教えるなど)や不随意の感情表現(デュシェンヌ型笑いなど)を用いるものはこのモデルで説明できる.
- しかしほとんどのヒトのコミュニケーションはコードモデルでは説明できない.そこでは情報意図(受信者の行動を変容させたいという送信者の意図),伝達意図(自分が情報意図を持っていることを受信者にわからせようとする意図)が問題になる.伝達意図を持つ信号は意図明示的信号となる.そして受信者はこれらの意図を推論する.この様な情報意図,伝達意図を表出し認識するコミュニケーションモデルをコードモデルの代替案として意図明示・推論モデルと呼ぶ.
- 意図明示・推論モデルは本質的にメタ心理的であり,連合よりはるかに複雑で,認知的に高度なものになる.
- これまでのヒトの言語についてのアプローチはコードモデルに基づくものだった.言語の体系には明らかに連合があるし,ヒト言語は(コードモデルである)動物の信号システムから漸進的に進化したと考えることが自然に思えるからだ.そしてそういう立場からは,言語はコードモデルにより構成され,そうして生じたコミュニケーションが意図明示,推論を用いることでより強力になったと考えることになる.
- 私は,事実は全く逆で,そもそもヒトのコミュニケーションは意図明示・推論モデルで可能になったのであり,その後連合が広く生じて言語になったと主張したい.それは決定不十分性を深く考えると理解できる.言語はコードとしてはひどい欠陥を持ち,ヒトのコミュニケーションは意図明示,推論により始めて可能になっているのだ.いったんこれを理解すると曖昧性などの決定不十分性が逆にコミュニケーション上の大きな利点になっていることがわかる.
- ここでコードを自然コード(コードモデルのみで機能しているコード)と慣習コード(コードに先立って存在した意図明示・推論モデルを強化するコード)に分けて考えることは有用だ.慣習コードはヒトの言語のあらゆるレベルに観察できる.私は言語を「意図明示・推論コミュニケーションを増強する慣習コードが多数集まってできた構造体」と定義する.ヒトの言語の起源や進化を理解するには,自然コードではなく慣習コードを考察することが重要になる.
- 「意味」という概念もコードモデルと意図明示・推論モデルでは異なることになる.意図明示・推論モデルで用いられる「意味」には語用論がフィットする.ポール・グライスは自然的意味と非自然的意味を区別し,送信者の意図,受信者の送信者の意図の認識,そして受信者の認識が送信者の意図通りで受信者がそう認識する理由が送信者の意図の認識にあること,という3段階に分けて意味を分析した(3段階目が非自然的意味になる).この3段階目ではまさに意図明示・推論モデルコミュニケーションが想定されている.
第2章 コミュニケーションシステムの出現
第2章ではヒトの言語の特徴である「組み合わせにより表現範囲が無制限になっていること」は意図明示・推論モデルでのみ説明できることが主張される.
- ヒトの言語は組み合わせにより表現範囲が無制限になっている.これは意図明示・推論モデルからのみ説明できる.
- 動物の信号のようなコードモデルにおいては,信号と応答が進化するにはそれが互いに適応価が高いという互いの存在に依存して決まるしかない.そしてそれは契機: cue から始まる儀式化か,強要: coercionから始まる感覚操作しかない*3.おそらく大半の動物の信号は契機からの儀式化により信号となっているのだろう*4.だとすると信号の形式は現存する契機と強要の集合によって制約されていることになる.
- そしてコードモデルにおいて組み合わせ信号が進化するのは,(1)信号Aと信号Bが偶然一緒に産出され,それが(A,Bの個別の状況を越えた)何らかの事実を知らせる契機になり,それを他個体が利用するようになり,(2)発信者にとってもそれを産出することが有利になる場合でなければならない.これは極めて生じにくい状況であり,合成的な信号は極めて稀にしか観察できないはずということになる.そして実際に動物の信号では組み合わせ信号は稀だ.*5
- これに対して意図明示・推論モデルにおいては,そもそもコミュニケーションを試みていること自体が相手に伝わっていることが前提にあるため,(儀式化や感覚操作にたよることなく)相互に依存する適応価のある行動(送信と反応)を同時に発生させることが可能になる(直接経路による信号進化).そしてこの場合には信号の形式にも信号の意味にも制約がない.現実世界では,健常者の親と聾唖者の子どものいる家庭で生じるホームサインにこの例を見ることができる.(具体的に組み合わせ信号を用いた柔軟なコミュニケーションが可能になることが示されている)
- 以上の議論はヒトの言語が動物の信号システムと連続的だとする従来説に大きな疑問を投げかけるものだ.(連続性がないと考えるべきいくつかの傍証も提示されている)
- 連続性の想定を捨てれば言語へ至る別の道が現れる.まず認知機能が十分に進化し,その結果意図明示・推論コミュニケーションが可能になり,その後,この新種のコミュニケーションの表現力を強化する方法として慣習コードが創設されたという道筋だ.
- 旧来説の誤りは,進化が漸進的だというダーウィンの生物の形態についての議論にとらわれ過ぎたこと*6,言語コミュニケーションはコードの存在によって可能になり,語用論はそれを増強するものだと考えたことだ.
第3章 認知とコミュニケーション
第3章では,意図明示・推論コミュニケーションではどのような原理が働いているかが考察される.
- 意図明示・推論コミュニケーションの大きな特徴は同じ言葉がコンテキストにより幅広い意味を持つことができる点だ.ではこれはいかにして可能になっているのだろうか.
- 相手が推論可能になる言葉を選び,選ばれた言葉にある意図を推論する能力をここでは語用論能力と呼ぼう.意図明示・推論コミュニケーションは語用論能力があってはじめて可能になる.これはいかなる認知メカニズムであるかが問題になる.
- ポール・グライスはこの議論の出発点となる研究を行った.彼は協調の原理を打ち出し,それは会話が質の格率,量の格率,関係の格率,様態の格率に従うことだと説明した.(簡単な説明がある) この基本的な全体像に対しては数多くの反論が提起され,それを改善しようとする様々な試みが蓄積した.この結果,新・グライス派語用論は用法の原則の乱雑な寄せ集めのようになった.しかしこれらの原則の寄せ集めがどのような認知メカニズムに基づいているかは全く明らかではなかったし,そのアプローチには明らかに心理学的・経験的に妥当でない部分が含まれていた(具体的な説明がある).
- これに対し,ダン・スペルベルとディアドリ・ウィルソンは代替案となるポスト・グライス派語用論アプローチを構築し,関連性理論を提示した.関連性理論は,ヒトのコミュニケーションに意図の表出と認識が必要だとするグライスの観察は受け継ぐが,協調の原理の必要性を否定するものだ.
- 関連性理論においては,「関連性」をプラスの認知効果と処理コストのトレードオフとして定義する.意図明示的刺激の関連性は常に個別の事情に依存することになる.
- そしてコミュニケーションにおいて2つの関連性原理があると主張する.1つは「認知的原理」であり,「ヒトの認知は関連性の最大化に向けて働く」と考える.これはヒとの心には効率性があると主張していることになる.
- もう1つは「伝達的原理」であり,「あらゆる意図明示的刺激はそれ自体に最適な関連性が見込めることを伝える」というものだ.これは発信者は受信者にとっての関連性が最大になるような信号を産出するという意味だ.これにより受信者はその刺激を解釈しようとする動機を持ち,推論することが容易になることになる.(これは意図明示・推論コミュニケーションにおいて,信号を発信することそのものが,受信者に「これはあなたのための信号であり,あなたはこれに価値を見いだすだろう」といっていることになる)
- 認知的原理と伝達的原理は互いに作用しあって意図明示・推論コミュニケーションを可能にする.
- この関連性理論が代替的な語用論理論よりも優れていると考えるべき根拠は4つある.(1)関連性理論の予測は統制実験を含む相当量の経験的精査に堪えている(2)関連性理論は発達心理学や言語習得研究において応用され,そこから生まれた予測が検証されている(3)関連性理論は認知人類学,心理言語学,進化生物学などの隣接領域の理論的枠組みと整合的である(4)新・グライス派の説明は話し手の目標の事後的な記述に過ぎないが,関連性理論は意図明示・推論コミュニケーションを動かす原理を説明している.
- 意図明示・推論コミュニケーションにおいて特に重要なのが再帰的読心能力になる.まず出発点になるのは「心の理論」だ.しばしば相手の心について何かを知っていることは相手の意図する意味を理解したり,自分の発話を相手に合わせるために重要だという分析がなされるが,語用論にとって心の理論が正確にどのように寄与するかまで詳述されることはめったにない.
- そして心の理論が意図明示・推論コミュニケーションにとって重要であることについては,上述した理由よりもずっと根源的で基礎的な理由がある.意図明示・推論コミュニケーションという行為自体が,他者の心を読む行為であり,伝達意図と情報意図を細かく分析すると高次の再帰的読心能力が必要になることがわかる(具体的なシナリオに沿って分析があり,最低でも5次の再帰的読心が必須であることが解説されている).
- この意図明示・推論コミュニケーションには高次の再帰的読心能力が必須であるという主張にはしばしば「そこまで必要とは思えない」という懐疑をぶつけられる.その根拠とされるのは有名なサリーとアンの誤信念課題実験において,4歳未満児はこの課題をクリアできないが,意図明示・推論コミュニケーションはできるという事実だ.私は3歳児はこの課題をクリアできなくとも高次の再帰的読心能力をもっていると主張したい.「サリーはどこにボールがあると思っているでしょうか」と尋ねるかわりに,行動から推測するように実験デザインを変えると1歳半で誤信念課題がクリアできるようになる.再帰的読心能力にもシステム1的なものとシステム2的なものがあり,1歳半で前者が機能し始めるが,後者は4歳頃まで難しいと考えられる.システム1的な再帰的読心能力はシステム2的な高度の認知的な発達なしでも機能することが可能なのだろう.*7
- トマセロは意図明示・推論コミュニケーションについて,意図性の共有という観点から考察し,「協調的コミュニケーション」という議論を行っている.その主張を単純化すると,「意図明示・推論コミュニケーションとは,私があなたに話しあなたが私に話す出来事というよりも,我々が互いにコミュニケートするという出来事であり,それが成り立つには意図性の共有が必要だ」というものになる.
- この主張を考察する際に重要なのはどのレベルの協調を問題にするのかということだ.協調には(言語コードを慣習通りに使う)伝達的協調,(騙すつもりがあるかという)情報的協調,(コミュニケーションの中身が向社会的かどうかという)具体的協調がある.そしてトマセロのいう協調は伝達的協調だ.
- 私はトマセロの主張に納得していない.「意図性の共有」は意図明示・推論コミュニケーションが今あるような形になっているのはなぜかは説明できるかもしれないが,話し手と聞き手が理解しあうために自分たちを「我々」として心的に表示しなければならないとは思えないからだ.
- しかしトマセロの主張には重要な部分がある.それは「意図性の共有」には能力だけでなく「意欲」の側面もあるというところだ.ヒトはコミュニケーションしたがるが,これは動物界においては異常だ.これについては進化的な考察が必要だ.
第4章 意図明示コミュニケーションの起源
第4章では意図明示・推論コミュニケーションの起源と進化が考察される.
- 1960年代以降,大型類人猿に言語を習得させようとする実験が数多くなされてきた.その結果は「少なくとも類人猿の何匹かは人間の自然言語の特徴の(全てではなく)一部を備えたコミュニケーション能力を発達させた」というものだ.これらの研究は,(1)信号と応答の相互依存性が信号形式に与える制約(2)言語と他の動物のコミュニケーションが全く異なるシステムである可能性,の2つをあまり考慮していないものだと評価せざるを得ない.
- 問われるべきなのは意図明示・推論コミュニケーションについての問題であり,比較研究においては大型類人猿のコミュニケーションは意図明示・推論的かどうか,大型類人猿はそれを可能にする認知メカニズムを持っているかということだ.
- トマセロは「大型類人猿の身振りによるコミュニケーションは意図的だが,発声によるコミュニケーションは意図的ではない」と主張し,主流の考え方になっている.これには批判もあって論争になっているが,いずれにしても問題になるのは「意図的コミュニケーション」と「意図明示・推論コミュニケーション」の関係だ.ここでいう意図的コミュニケーションは「どのように信号が使われているか,制御されているか」にかかわっているのに対して,意図明示・推論コミュニケーションのポイントは「信号が何を表しているか,特に伝達意図を表しているか」であり,両者は(関係はあるが)異なる概念になる.
- 意図明示・推論コミュニケーションの4つの側面(情報意図の表現,情報意図の認識,伝達意図の表現,伝達意図の認識)についてのこれまでの大型類人猿の研究を詳細に分析してみると,決定的に重要と思われる実験がなされていないことがわかる.私はそれは研究者がそういう課題について大型類人猿がしくじるだろうと暗黙的に考えていることを示しているのだと思う.私は大型類人猿のコミュニケーションは意図明示・推論的ではないと考えている*8.
- 大型類人猿の身振りによる意図的コミュニケーションは,連合のメカニズムによる自然コードによるものだが,メタ心理学的な能力の存在によって表現力が強化され,自然コードを柔軟に使えるようになっているものだと考えるべきだ(そう考える根拠がいくつか議論されている).
- 大型類人猿の読心能力の研究は数多くなされている.チンパンジーは古典的な誤信念課題をクリアできない.他者の意図を理解しているように見える結果もいくつか報告されているが,いずれにしてもヒトと同じレベルではないことは明らかだ.いまのところ大型類人猿が意図明示・推論コミュニケーションに必要な高次の再帰的読心能力を示す証拠はない.大型類人猿が意図明示・推論コミュニケーションを行う能力があると主張するなら,この高次の再帰的読心能力があることを示し,かつなぜ類人猿が(少なくとも初歩的なレベルの)言語を持たないかを説明する必要があるだろう.
- 大型類人猿の認知能力が高いことは社会脳仮説で説明される.ヒトは特に大きく複雑な社会を形成するので,この中でも高い認知能力を進化させたことが説明できる.そしてこの高度の社会認知能力が意図明示・推論コミュニケーションを可能にしたと論じることができる.スペルベルは高次の読心能力がどのように意図明示・推論コミュニケーションを可能にするのかの具体的シナリオを提示している.逆に(第2章で示したように)意図明示・推論コミュニケーションなしに言語が出現することはできない.
- まとめると,意図明示・推論コミュニケーションの進化,言語の進化についての一貫した説明は1つしかない.社会的知能の二次的な適応として意図明示・推論コミュニケーションが可能になり,それが言語につながったのだ.そしてこのシナリオは次に意図明示・推論コミュニケーションがより円滑かつ効果的になるような適応,伝達上の慣習が生じることを説明できることになる.
第5章 個々の言語を組み立てる
第5章と第6章は言語の進化について考察される.第5章では文化進化としての個別の言語の進化,第6章では生物進化としての言語能力の進化が取り扱われる.
- 言語の進化という現象はコミュニケーションの意図明示的な性格の帰結として生じることは重要である.言語の変化は,話し手の言語形式の用い方の変化(メタファーなど),聞き手の解釈の変化の2通りで生じうる.意図明示・推論コミュニケーションにおいては話し手の自分が伝達しようとしていることを示す手がかりを提供し,聞き手は最善の推論をする.だから言語の変化の最善の方法は既存の慣習をメタファーとして使うことになる.意図明示・推論コミュニケーションがあれば,その表現力を強化する慣習コードが次々に生み出されることになる.
- 初期の言語を考える上で重要なのは,アイコン,インデックス,シンボルだ.最も初期に新しい信号として使われたのはアイコンやインデックスだっただろう.それが音声だったのかジェスチャーだったのかという論争があるが,あまり意味はないと考える.その時点で有用なものが適宜使われた(ジェスチャーの方が柔軟だが,発声には素早さと相手の視線の確保が不要という利点がある)と考えておけばいい.
- その後アイコンやインデックスが成立しにくい抽象的,あるいは複雑な概念を表すためにシンボルが慣習コードとして使われるようになっただろう.進化言語学の実験はそれを示唆している(実験の詳細について解説がある).意図明示・推論コミュニケーションの決定不十分性は,慣習コードの広がりにとって利点だったと考えられる.
- 次の段階は文法の成立になる.言語学では文法の起源,プロト言語の進化については,統合説(要素の統合を重視する)と合成説(要素の組み合わせを重視する)が主流の議論になっている.これらに対する代替説には分析説(原初の一語文が文法構成要素に分解していくと考える)がある.激しい論争があるが,私はこの2つの立場が排他的だとは考えていない.語用論的に考えると原初の言語は一語文的だったと想定されるが,(意図明示・推論コミュニケーションの)決定不十分性を考えると全面的な分析説は成り立たないだろう.当初限られた数の慣習が成立し,意図明示・推論コミュニケーションによって慣習が多様化し,それを組み合わせることで表現できる範囲が広がったのだろう.
- 言語においてはしばしば「文法化」現象(一部の語が豊かな内容を表現することを離れて文法機能を担う方向に変化すること)が観察される.この現象が生じる理由は意図明示・推論コミュニケーションで説明できる.内容語が文法機能の証拠とをして使える可能性の方が,文法的な語が内容に対する証拠として使える可能性よりはるかに高いからだ.
- 言語進化の最後のピースは文化的牽引(コミュニケーションの様式,認知メカニズムが文化要素に収斂を引き起こすこと)だ.(色彩語の発展,言語の声調の有無と脳で働く2つの遺伝子の頻度に相関があることについての文化的牽引からの説明がある) これにより言語はヒとの心の自然な直感と傾向,ヒトの行動の目標に合致するような形になっていく.
- 特に重要なのは言語において文化的牽引は意図明示・推論コミュニケーションを強化するように働くことだ.言語は習得容易性と表現の有用性に向けて,構造化が進み,同音異義語を減らし,最も覚えやすい形に引きつけられる.(関連する進化言語学の実験が解説される) そして意図明示・推論コミュニケーションにとっては曖昧性は有用であるので,(コンテキストにより解消される限りにおいて)曖昧性がなくなるようには引きつけられない.言語のコードに曖昧性があるとしても人々の日常会話においては曖昧性はほとんど解消されているのだ.
- 以上の議論から浮かび上がるのは,言語形式が全て何らかの文化的牽引の帰結である可能性だ.この「言語形式は文化的牽引の結果である」とするテーゼは,チョムスキーの「言語が今ある形式であるのは普遍文法の結果である」というテーゼへの反論となる.
第6章 進化的適応
最終第6章は言語能力の進化について.冒頭で進化,および適応主義についての簡単な解説があり,そこから議論が始まっている.ここは特に私の興味関心があるところなのでやや詳しく紹介しよう.
- 言語進化研究の世界では,通時的な進化史の問題に興味が集中し,適応主義的観点からの分析にはあまり関心が払われていなかった.
- 言語能力の進化における古典的な論文にピンカーとブルームによる「自然言語と自然淘汰」がある.これはチョムスキーなどの当時の言語学の主流がいかなる種類の進化的考えにも反発を示していた中で,適応主義を言語に応用することを宣言したものだ.
- 彼等の結論「言語能力は適応形質である」を導いた論理は完璧だが,2つの前提がある.それは「自然界の(精妙な)デザインの唯一の自然主義的説明は自然淘汰だ」というものと「ヒトには本当に言語能力がある」というものだ.この後者の前提は彼等がチョムスキー的な言語観を持ち,言語能力が「個別言語の獲得と処理を可能にしている生得的な認知メカニズム」(普遍文法)だと考えていることを示している.
- この普遍文法の存在については議論が続いている.チョムスキーは刺激の不足で普遍文法の存在を論証したとするが,これに対しては異論もある(議論の詳細には立ち入らないと断りがある).普遍文法が存在するならピンカーとブルームの主張は極めて説得的なものになる.
- 文化的牽引は文化的牽引によって諸言語が似通ったものになること(統計的な普遍性を持つこと)を説明できるので(ピンカーたちの第2の前提である)普遍文法への代案となる.ただし文化的牽引が(ピンカーたちの第1の前提である)生物の(この場合は文化的牽引の基盤となる)設計の適応説の代案になるわけではない*9.言語進化は自然淘汰と文化的牽引により異なるレベルで影響を受けると考えるべきだ.
- 言語進化についての自然淘汰の役割について,言語学者や認知科学者は内的・認知的なメカニズムを問題にする傾向があり,進化生物学者は社会的コミュニケーションを問題にする傾向がある.ここでは後者を扱う.
- 問題となるのは意図明示と推論だ.この2つはコミュニケーションにおいて相互に依存しているためにどのような行動が適応的かが見えにくくなっている.優れたコミュニケーションデザイン特性がどういうものかを理解するには話し手と聞き手のそれぞれの利害関心がどう相互作用するのかが重要になる.これを詰めて考えると認知的関連性原理と伝達的関連性原理になる.そして実際に意図明示・推論コミュニケーションはこの原理に沿っている.ヒトは伝達意図と情報意図を表明・認識することに適応しており,それにより複雑な社会生活の中でうまく生きていけるようになっている.
- 大型類人猿との連続性の問題については,コミュニケーションの面では断絶があるが,複雑な社会生活への適応という面では連続していると考えることができる.彼等は(コミュニケーションなしでも機能する)読心と心理操作能力を進化させ,ヒトははるかに有効に読心と心理操作が可能になる意図明示・推論コミュニケーションという新しい他者とのかかわり方を進化させたと考えられる.
- 言語の進化的機能については様々な憶測が発表されている.うわさ話,配偶者の誘引,性的競争,狩猟の計略,投擲の始まり,政事の始まり,生活史の進化などのタスクに有用だという議論だ.このアプローチには問題がある.まずこのようなタスクは他の多くの動物にもあるはずで,なぜヒトだけなのかを説明できていないこと,そして本来的機能と派生的機能を区別していないことだ.
- 本来的機能にフォーカスするなら,意図明示の本来的機能は他者の心の操作で,推論の本来的機能は他者の心の読解ということになるだろう.
- コミュニケーションは相互行為であるので,その進化を考える上では,話し手と聞き手の利害のコンフリクトをよく考察する必要がある.言語においてはどのような仕組みで嘘やごまかしの頻度がコミュニケーションを崩壊させるようなレベルにならないのかが説明されなければならない.
- 聞き手は明らかに悪意のある話し手や関連のない話をチェックする「認識的警戒」を行っている(これはコードモデルでは不要なものだ).この認識的警戒が効果的かどうかについてはほとんど調べられていない.
- 話し手はこの聞き手の認識的警戒に対して「説得」を行う.相手の説得のために論理的思考能力が進化したというのが論理的思考の論証説になる.確証バイアスの存在はこの傍証となる.
- 信号の進化的安定性については,ハンディキャップがよく取りざたされるが,これにはコスト以外の前提条件があり,必要不可欠なものでもない(相互利益がある場合は不要.インデックスやバッジでも良い.ハンディキャップはインデックスの特殊なケースと考えられる)ことに注意が必要だ.ヒトのコミュニケーションにかかる信号の安定性については,ハンディキャップ原理を不適切に用いている例がしばしば見られる*10.
- ヒトの言語の進化的安定性についてハンディキャップで説明しようとする説もいくつかあるが,どれもハンディキャップ原理の基本的条件を無視したものだ.言語も意図明示コミュニケーションもハンディキャップで安定性が保たれているわけではない.ヒトの言語はその言葉が本当だろうと嘘だろうとそれにかかるコストは変わらない.言語にハンディキャップ原理が効いているかどうかを考える上では,特に正直者と嘘つきでコストに格差が必要なこと,コスト負担能力にかかわらない内容にはハンディキャップが効かないことは重要だ.
- ヒトの言語コミュニケーションが安定している理由は種々の抑止力であり,特に世間の評判であると考えることができる.実際に自分の評判を落とさずに(有利に)嘘をつけると思い込んでいると嘘をつきやすくなることを示した実験がある.
- 最後にメイナード=スミスとサトマーリの「進化する階層」で議論された進化史の大転換に「言語の始まり」が含まれていることについてコメントしよう.この本の他の大転換が,ユニットが融合して上位化し,集中制御や分業を可能にしていることを採り上げているのに対して言語は単に新しい情報伝達法の出現として採り上げられている.あるいはそれほど深い意味はないのかもしれない.しかしもし大転換として採り上げるなら,それは「言語の始まり」ではなく,「意図明示・推論コミュニケーションの始まり」とすべきだというのが私の意見だ.
以上が本書の内容になる.私の感想をまとめておこう.
- 著者の「ヒトの言語がコードモデルとは異なる意図明示・推論モデルの上にある」という主張は説得的だ.それは会話において言語を使っているときに常に語用論的な意味がまとわりついていることや言語には決定不十分性がありながら実際のコミュニケーションにはほとんど不自由さがないことをうまく説明できる.そしてこの語用論的な意図明示・推論コミュニケーションが先に成立したのちに,様々な慣習コードが積み重なり,言語になったという仮説はとても斬新で興味深い.またコードモデルでは組み合わせ信号が成立しにくいが,意図明示・推論モデルでは成立しやすいという議論にも説得力があるように感じる.
- 意図明示・推論コミュニケーションには高次の再帰的読心能力が必要だという主張も興味深い.これらを幼児の誤信念課題実験の結果をどう整合させるかという問題を,システム1的読心能力とシステム2的読心能力を区別するという離れ業で解消しており,スリリングだ.また大型類人猿にはそもそもこの能力がないことを,研究者がそれを確かめようともしないことで補強するというという構成には笑ってしまった.
- ただし最終2章の進化的な議論についてはいくつかの違和感がある.
- まず著者の文化的牽引と言語能力の関係についてのコメントはわかりにくい.どうやら「進化で獲得した言語能力はほとんどが意図明示・推論コミュニケーションを可能にする能力として説明できるとし,普遍文法は否定する.そして言語間に共通の形式や法則があるのは文化的牽引で説明する」という立場のようだ.
- すると著者は意図明示・推論コミュニケーションのみが相同的な形質で,それを持つ様々な集団で個別に独立に言語が成立し,それらが共通の基本原則を持っているのは文化的牽引で(文化進化の収斂形質として)説明できると考えていることになる.
- これは極めてありそうもないシナリオに感じられる.まず,普遍文法の形式が全て文化的牽引で本当に説明できるのだろうか.述部と様々な格マーカーを持つ句という構造,動詞によりどのような格がとれるかが決まる制約などが例外なく牽引で決まるとは思えない.次に普遍文法的な生得的言語能力がないとするなら,なぜ言語習得には幼児期の臨界期があるのかをどう説明するのだろうか.この点についてチョムスキーの刺激の不足論証をどう反駁するのかについても明らかではない.また言語の比較から言語が系統樹的に分岐していることは少なくとも数千年の単位で確かめられている.これが(変わりすぎて比較が難しい)過去に延びていってどこかで単一起源があるという方が,過去において個別独立に言語が文化進化して似通ってきたというよりよほどありそうに感じられる.
- 以上の点を考え合わせると,普遍文法を認めた上で「祖先集団で意図明示・推論コミュニケーションが成立し,その後プロト言語と生得的普遍文法言語能力が進化し,さらにその後集団の分岐拡散に応じて言語が分岐していった.ただし色彩語の発展過程などの一部の特徴については言語間で収斂的な文化的牽引事例も見られる」というシナリオの方がはるかにありそうだろう.
- また細かな点になるが,著者のハンディキャップ原理の捉え方には同意できない.著者はコストはシグナルを発する際にかかるものでなければならないと考えているが,グラフェンの定式化にはそのような制限はない.だから特定の信号を発するための身体の発生や成長にかかるコストや,特定の信号を発した後の同種個体からのハラスメントコストもハンディキャップとなることができる.そう考えればインデックスも(例えば大きな身体でなければ低い声が出せないとしても,そのような大きな身体を作るためのコストまで考えると)ハンディキャップシグナルと捉えられるし,ハラスメントを生じさせるバッジもハンディキャップシグナルと考えることができる*11.つまりコードモデルで利害相反的な状況で信号が正直になる原理はハンディキャップしかないと考えるべきなのだ.ここは理論的に残念な部分だ.
- とはいえ言語が崩壊しない理由をハンディキャップでは説明できないという著者の議論は正しいと思う.特に重要なのはハンディキャップシグナルはそのコスト負担力にかかる内容の正直さしか説明できないが,言語の内容はそれよりはるかに広いということだ.この点を特に強調し,正直者と嘘つきでコスト負担能力が異なる構造でもないことを付け加えれば十分ではなかったかと思う.そして著者は言語の信号システムが崩壊しない理由として社会的評判のみを挙げているが,ここはやや考察が雑に感じられる.社会的評判は大きなファクターになるだろうが,それ以外にも相手との直接互恵的関係(たとえば友人との信頼)の維持,相利的状況の頻度,(著者が挙げている)認知的警戒の効率性なども考察すべきだろう.
いくつか批判的なコメントも書いたが,全体として言語進化について主流ではないが極めて興味深い考えが説得力を持って論じられている啓発的な書物だ.言語進化について興味がある人にはとても刺激的な一冊だと思う.
関連書籍
原書
*1:学問的にはダン・スペルベルとトマセロの影響を大きく受けているようだ
*2:ハウザー,チョムスキー,フィッチの論文がきっかけになっていると思われる
*3:コミュニケーションが成立するのは送信者の信号が受信者に反応を引き起こし,これが双方の目的に沿ってデザインされている場合となる.そして送信者の信号のみがデザインされている場合には強要になり,受信者の反応のみがデザインされている場合には契機になる.
*4:契機からの儀式化の例としてイヌがナワバリの境界で恐怖感から排尿していたことが,他のイヌにとってはナワバリの情報をもたらし,それがナワバリにシグナルになったという仮想例が示されている.また強要からの感覚操作の例としてはメスに餌を与えて,メスが餌を食べている間に交尾を試みるというオスの行動があり,メスは(十分大きな)餌の提示を交尾のサインとして受け取るようになったという婚姻贈呈の仮想例が挙げられている
*5:ここでは旧来の論者は動物の信号に組み合わせ信号が稀であることを,信号総数が小さいなら組み合わせ信号の方が効率が悪いという数理モデルで説明しようとしてきたが,それが妥当でないことについての説明がなされている.
*6:著者は機能の変化は不連続的に生じることがあるとしているが,やや勇み足的な議論だと思う.漸進的な道筋がいくつもありうる中で一つに絞ってしまった問題という扱いをすべきだっただろう
*7:このほかここでは成人に対する高次の再帰的読心能力テストの結果との整合性,ASD患者についてどう考えるべきかなども詳細に論じられている
*8:4つの側面を調べるために具体的にどのような課題をクリアすべきかの詳細が説明されている.それを見るとチンパンジーがこれら全てをクリアすることは難しいという著者の感覚がわかる.なおここではイヌが理解できる指さしによる指示をチンパンジーが理解できないという話も紹介されている.ただし著者の見解によるとイヌによる指さし理解は情報意図の理解ではなく命令の理解であり,自然コードによるものだとされている
*9:著者によると言語学者や認知科学者の中には文化的牽引で言語にかかわる自然淘汰を全て否定しようとする論者がいるそうだ.そしてその主張は成り立たないということがここでのポイントになる
*10:献血についてのライルの議論,コストを払う謝罪についての大坪の議論,デュシェンヌ型笑いについてのシュミットたちの議論,囚人の自傷行為についてのギャンベッタの議論がやり玉に挙げられている.これらの議論には正直者と嘘つきでコスト負担能力に差があるという条件を無視していると批判している.献血や自傷行為についての議論についてはよく承知していないが,大坪のコストをかけた謝罪については著者に誤解があるのではないかと思う.相手のとの関係が謝罪にコストをかけてでも引きあうかどうかが問題になっていて,これは正直者と嘘つきでコスト負担能力に差があることを意味している.基本的に大坪の議論はグラフェンの条件を満たしていると思う.これに対してデュシェンヌ型笑いなどのフェイクしにくい感情表現は(著者のいう通り)ハンディキャップではないだろう.なぜ一部の感情表現が(フェイクできれば他者操作上極めて有利になりそうなのに)フェイクしにくいのか,そして(いかにも自然な感情表現で観客を魅了する女優のように)極く一部にそれが得意な人がいるのはなぜか(なぜそれが淘汰により広がらないのか)は大いなる謎だと思う.
*11:ただしこの部分については進化生物学者たちの間にも意見の相違がある.例えばメイナード=スミスはインデックスとハンディキャップを峻別する立場に立っている.